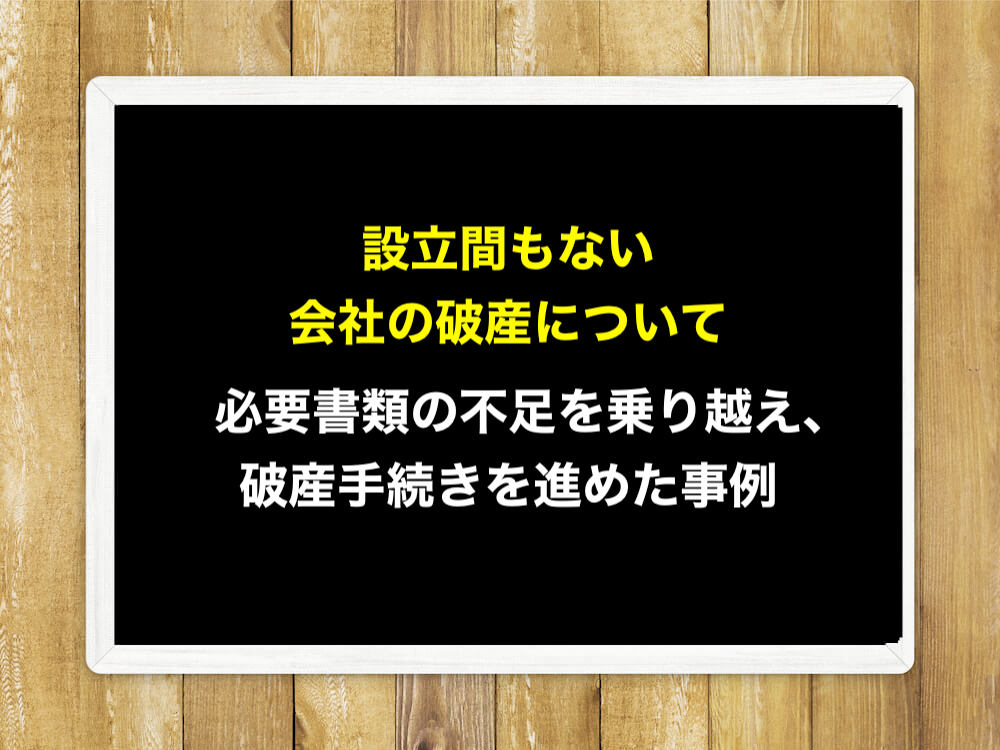
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 渕山 剛行
出身地:北海道札幌市。出身大学:大阪大学法学部法学科。主な取扱い分野は、「著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法、労務・労働事件(企業側)、債権回収、インターネット上の違法記事の削除請求、発信者情報開示請求、歯科医院関連、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「ソフトウェア開発会社」の事例です。
2,事案の概要
相談者は、ソフトウェア開発会社です。
会社資金は、金融機関からの借入れと取締役の個人資産から準備されていました。代表者は、長年ソフトウェア開発のお仕事をされており、業務経験を生かしての独立でした。
しかし、懸命な営業活動にも関わらず、売り上げが伸びず、資金がショート間近であったことから、法人の破産手続きの検討のためにご相談に来られました。
法人破産の手続に進むかどうかの検討にあたり、役員報酬の受領のこと、代表者個人が受けるデメリットのこと(ローンを組めなくなるか等)、破産手続きにかかる期間のことなどについて、不安に思われていました。
3,問題の解決結果
本件では、会社のみの自己破産を申し立てました。会社の主な債権者は、会社資金を借り入れた金融機関でした。代表者は融資の際に連帯保証人になっていなかったため、代表者個人は自己破産の申し立てを行わずにすみました。
必要書類の不足などさまざまな問題点がありましたが、ご相談者にもご協力いただき、円滑に手続を進めることができました。
4,問題の解決における留意点
法人破産の場合に、どのような点に注意して進めなければならないかは事案ごとにケースバイケースです。
今回のケースでは、「相談者の不安の解消」と「資料の不足などを乗り越えるための事前の準備」が大きな課題となりました。
以下で順番にご説明したいと思います。
(1)ご相談時の不安の解消
法人の破産を検討する場合に、真実入り混じったインターネットなどの情報をご覧になられ、必要以上に破産手続きを怖がっている方も少なくありません。
そこで、咲くやこの花法律事務所では、まず、相談者のご質問にお答えし、正しい情報をお伝えするよう心掛けています。
1,役員報酬の受領について
相談者は会社から役員報酬を受け取っていましたが、会社の資金ショートの危険性が現実化する中、いつまで役員報酬を受け取っても問題がないのかを心配されていました。
この点、本件では、弁護士がご相談を受けて、直ちに役員報酬の支払いを止めるようにアドバイスしました。なぜなら、破産手続においては債権者を平等に扱わなければならないというルール(債権者平等原則)があるからです。
金融機関への支払が難しくなったにも関わらず、役員報酬を受け取ってしまうと、会社が一部の債権者(役員)にのみ支払いをしたことになり、債権者平等原則に反する結果となります。
債権者平等原則に反して、役員報酬を受領すると、破産を申し立てた後に、一度受け取った役員報酬の返還を求められる可能性があるうえ、破産手続に必要な調査等にも時間がかかることになり、破産手続きに支障が生じます。
2,代表者個人のデメリット
個人の破産であれば、少なくとも数年間は信用情報機関に登録され、車や住宅のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする際に支障があることはよく知られています。
これに対して本件では、会社の破産のみであり、相談者個人の破産は必要ありませんでしたが、それでも、個人として何らかの不利益が生じてしまうのではないかと心配をされていました。
この点については、会社と代表者は別人格なので、個人が破産していなければ、不利益が生じないのが基本です。但し、破産した会社の代表者であったことが信用情報として残ることは否定できません。
このため、仮に後日、新会社を設立して代表者となった場合、金融機関からの融資を受けにくくなることもあり得ることをお伝えしました。
3,手続きが終了するまでの期間
相談者からは、破産手続きが終了するまで1年程度かかると言われているが、本件では債権者の数が少ないので、もう少し早く終わらないかとのご質問を頂きました。
しかし、破産手続きにどの程度、期間がかかるかは、債権者の数よりも、会社財産の処分(建物の明け渡しや、動産の売却又は廃棄処分、会社の債権の回収など)にかかる期間に左右されます。
そこで、弁護士からこのことをご説明し、破産の申立て前に、法律上処分可能な財産については、出来る限りの処分を進めておくことで、手続を早く終わらせることができることをお伝えしました。
(2)資料の不足などを乗り越えるための事前の準備
会社が破産した場合、代表者は、裁判所や破産管財人に対し、会社が所有する財産や借金の内容等について説明を行う義務があります。
破産管財人は、破産会社の財産の管理及び処分を行う者であり、通常は弁護士の中から裁判所によって選ばれます。
法人の破産手続きをスムーズに進めるためには、裁判所や破産管財人から指摘されることが予想される項目について、事前に対応しておくことが重要です。
本件では、破産申し立て後に、裁判所や破産管財人から以下の3点が問題点として指摘されることが予想されました。
- ア:申立資料(決算書及び税務申告書)の不足
- イ:会社財産の保全
- ウ:破産に至る経緯の説明
1,提出資料(決算書及び税務申告書)の不足について
法人の破産手続きでは、裁判所が法人の財務内容を把握するため、通常、裁判所から過去2年分の決算書及び税務申告書の控えの提出を求められます。
しかし、本件は、設立後1年未満の申立であったため、一度も決算を迎えておらず、決算書も税務申告書もありませんでした。
そのため、明らかに、裁判所への提出資料が不足していました。
2,会社財産の保全
破産を申し立てる場合、会社財産をそのまま(例えば、会社名義の口座に保管したまま)にしていれば、債権者によって差し押さえられるなどして、口座から引き出せなくなる可能性があります。
そうなると、法人は破産管財人に会社財産を引き渡すことができず、破産手続きをスムーズに進めることが困難となる恐れがありました。
3,破産に至る経緯の説明
本件は、金融機関から多額の資金を借り入れ、1年をまたずに破産申し立てを行うことになりました。
このように設立後、比較的短期間で破産申し立てを行うケースでは、債権者や破産管財人から、事業を継続することができなくなった具体的な理由について詳細に説明を求められることが予想されました。
すなわち、何年も続いた会社であれば、複数年の決算報告書を見るだけで、営業を続けていたこと及び経営状態が悪化した経緯が想像でき、破産に至る経緯の説明も比較的容易です。
しかし、設立後間もない会社には資料が少なく、特に債権者の立場からは、初めから返済する意思もないのに借り入れを行ったのではないか、詐欺的な借り入れをしたのではないか、と誤解される可能性すら否定できないのです。
融資を受けたにもかかわらず、短期間で破産に至った事情を説明し、融資された資金を会社の営業のためだけ使い、私的流用等をしていないことについて十分な説明を求められることが予想されました。
5,担当弁護士の方針
本件では、「資料の不足」、「会社財産の保全」、「破産に至る経緯の説明」という3つの問題点に対処するため、以下の方針を立てて会社の破産申立手続きを進めました。
(1)申立資料の不足については代替資料の提出で対応
本件では、決算書はありませんが、売上や経費がわかる帳簿類や資料は残っていました。そこで、帳簿類と、帳簿を元に作成された貸借対照表を資料として提出しました。
これらの資料により、裁判所に会社が債務超過状態あり、破産手続きを開始するための条件を満たすことを認めてもらうことができました。
(2)会社財産の保全のために預金を別口座に移す
本件では、会社財産のほとんどが会社名義の預金口座に保管されていました。そのままでは、会社債権者により預金が差し押さえられる危険性もありましたので、これを別の銀行口座に移しました。
その結果、預金が債権者から差し押さえられることを避け、会社財産をいつでも破産管財人に引き渡せる状態におくことができました。
(3)破産に至る経緯についての十分な説明
前述の通り、本件は、営業の実体があったことを裏付ける客観的な資料(数年分の決算報告書)がありませんでした。そこで、破産に至る経緯を説明する前提として、営業の実体があったことを明らかにするよう以下の点を心掛けました。
1,各種資料の保管
会社が実際に事業活動を行うと、通常、事務所を借り入れたり、必要な事務用品等を購入したり、電話等の契約をしたりすることになります。
経費を節約するため、自宅兼事務所でスタートされるケースもあるかと思いますが、本件では、事務所を賃借されていました。そこで、事務所を借りた際の賃貸借契約関係の資料や領収書等を裁判所に提出するなどして、これらの資料からも、会社に実体があったことを裏付けようと考えました。
2,日々の営業活動の詳細な説明
事業を行っていた期間が短期間であったとしても、例えば、少額商品の販売であれば、仕入れや売り上げが頻繁に帳簿に記載され、帳簿を見ているだけで、活発な営業活動があったことが容易に想像できます。
しかし、本件の業種はシステム開発であり、注文を受けてから仕事(開発)を始めるという性質もあって、頻繁に売り上げが発生する業種ではありませんでした。
このため、帳簿の記載のみから活発な営業活動を読み取ることはできない状態でした。
しかし、帳簿に「売上」という目に見える形がなくても、会社は日々「活動」しており、目に見えない「活動」が会社の存続において重要なものであることも少なくありません。事実、本件では、特定の顧客が存在しなかったこともあり、注文を取ることが最重要課題であり、そのために、真摯な努力を続けておられました。
そこで、具体的にどういう営業活動を行っていたかを聞き取り、書面にまとめて提出し、資料からは読み取りにくい部分について説明を補充しました。
6,まとめ
本件では、懸命な営業活動にも関わらず売り上げが伸びず、資金がショートする寸前で営業を停止し、自己破産の途を選ばれました。
相談者は、「これ以上周りに迷惑をかけたくない」というご希望をお持ちであり、ご決断も早かったため、債権者も多くはありませんでした。
上記のとおり十分な説明をしたため、債権者との間に大きなトラブルもなく、破産手続きを進めることができました。また、破産の際の事前準備を丁寧に行ったことなどから、手続き的な負担も少なくて済み、代表者の日常生活にも大きな支障は生じませんでした。
法人の破産を迷われる場合は、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことで、周囲にかける迷惑や、手続の負担を最小限にすることができます。
法人破産をご検討される場合は早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の法人破産に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「法人破産に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】法人破産テーマに関連した解決実績
今回は、「設立間もない会社の破産について必要書類の不足を乗り越え、破産手続きを進めた事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した法人破産関連の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・代表取締役が死亡したことによる会社の破産をサポートした事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






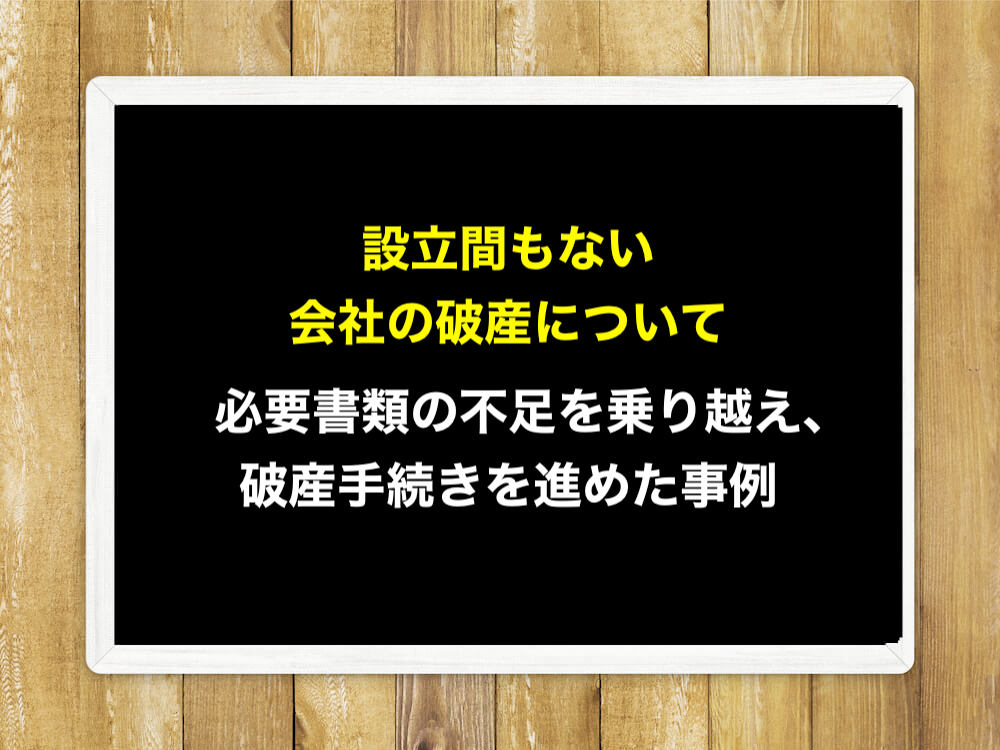

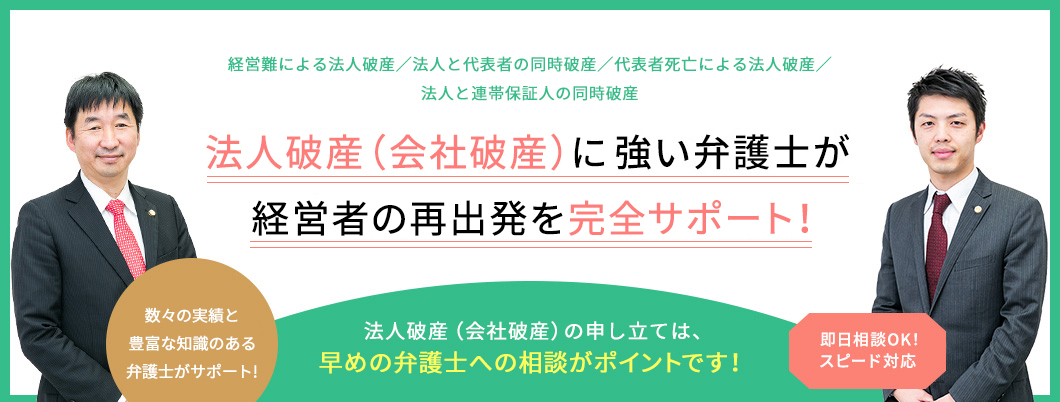
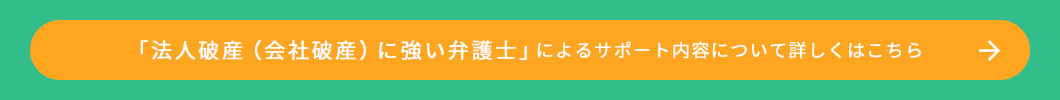
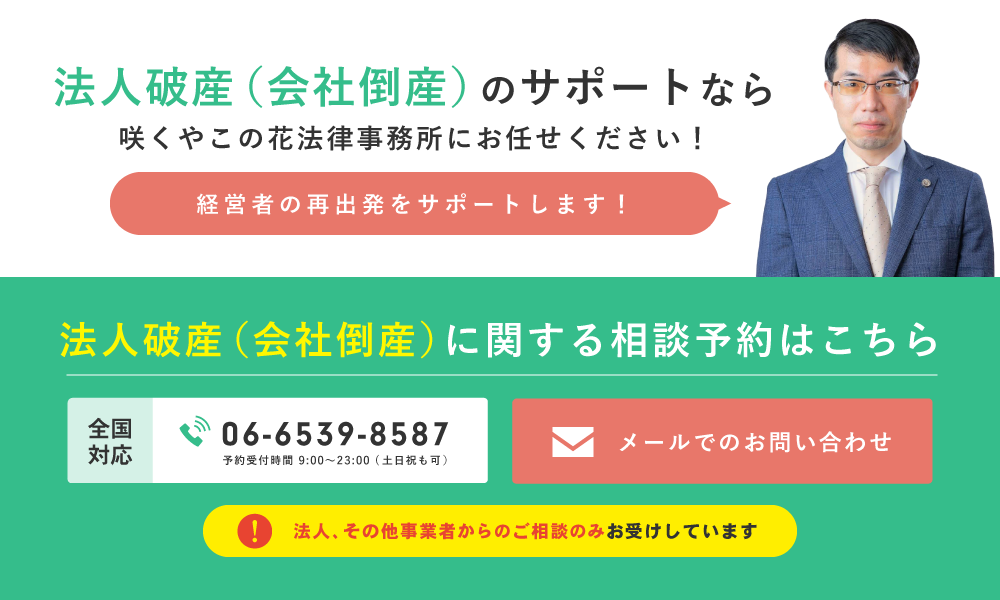
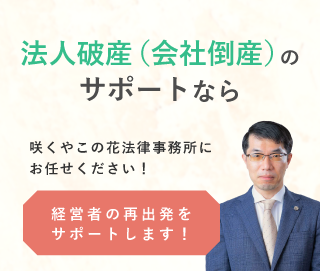





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















