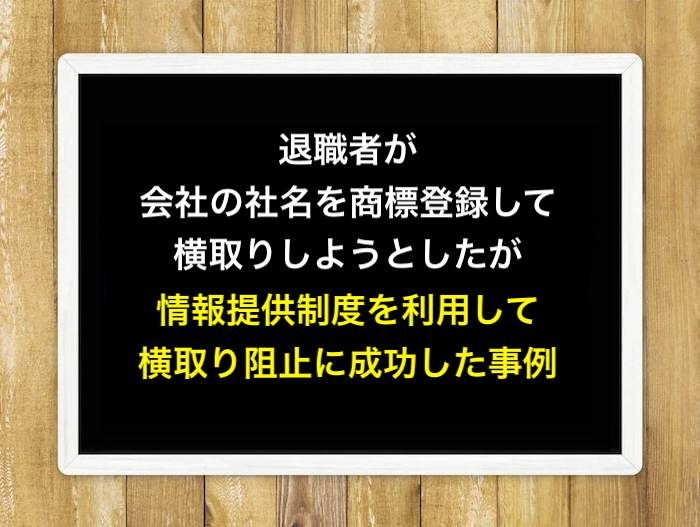
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 小田 学洋
出身地:広島県。出身大学:広島大学工学部工学研究科。主な取扱い分野は、「労務・労働関連(企業側)、債権回収、システム開発トラブル、運送業関連、フランチャイズ契約トラブル、顧客クレーム対応、インターネット上の誹謗中傷対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「運送業」の事例です。
2,事件の概要
本件は、相談者(運送業)が自社名を商標登録していなかったところ、相談者の元役員が会社名を会社に無断で商標登録出願し、社名を横取りしようとした事例です。
弁護士が会社の依頼を受け、特許庁への情報提供など横取りを阻止するための活動を行った結果、退職者による商標登録を阻止できました。そして、無事に相談者が会社として商標登録することに成功しました。
その詳細は以下のとおりです。
(1)自社が商標登録していなかったことが問題の発端となった
今回の相談者である会社は、創業時に考案した自社名のロゴや社名を、長年使用し、パンフレットや会社所有の車両、ホームページなどにも表示していました。
しかし、相談者はそのロゴや社名を、商標登録していませんでした。そのような状況で、相談者の元役員が退職後に自分が使用する目的で、相談者に無断で、社名やロゴについて商標出願し、横取りしようとしました。
(2)相談者が自社名の商標出願がされていることを偶然発見した
相談者が元役員による商標出願に気が付いたのは偶然でした。
元役員が相談者を辞める際に、「会社の商標は自分がもらう」などと述べていたことから、気になって調べたところ、元役員の個人名で会社の商標の登録出願が出されていたことを発見しました。
相談者はあわてて、自社でも同じ商標を出願しました。しかし、その後どうなるのか不安に思い、相談に来られました。
(3)商標登録は早いもの勝ちが原則
商標法のルールでは、商標は早く申請した人が取得することが原則です。
そのため、前記のような横取りのような事情があったとしても、そのまま放置した場合、先に申請していた元役員の商標登録がみとめられます。
そして、相談者が行った自社名の商標出願は、同じ商標が相談者の出願より前に出願されているとして登録を認められないことになります。
このような商標についての「早い者勝ち」のルールを先願主義といいます。
(4)相談者が商標をとるためには退職者による商標登録の阻止が必要
このように商標については早い者勝ちのルールがあるため、相談者の出願がみとめられるためには、元役員の商標を無効にしなければなりませんでした。
そのためには、元役員の商標登録がされてから、「無効審判」という制度で無効を主張することが原則です。
しかし、それでは、登録してから無効が決定するまでの期間中は、元役員が権利者となるので、相談者は自社の社名を使うことができなくなります。また、元役員が審査期間中、自社名を自分の商標として使用すれば、取引先が混乱し、会社の信用が損なわれる危険もありました。
そこで、できるだけ早く元役員による商標登録を阻止して自社の商標登録を実現する必要がありました。
3,問題の解決結果
会社の依頼を受けた弁護士が特許庁への情報提供制度を利用して、元役員が商標出願により会社名を横取りしようとしていることを特許庁に伝えました。
それにより、元役員の商標の審査で、特許庁から商標の登録を認めない旨の通知を出させることに成功しました。その結果、元役員は申請をとりさげ、無事に相談者の申請した商標が登録されました。
4,問題解決における争点(弁護士が取り組んだ課題)
以下では、問題解決において担当弁護士が取り組んだ課題について詳しく解説していきます。
(1)特許庁の情報提供制度の利用を提案
前述の通り、相談者が気づいた段階で、元役員はすでに商標出願していたため、放置すれば元役員を権利者とする商標が登録されてしまう状況でしたが、幸い、特許庁は元役員の商標出願の審査をまだ開始していませんでした。
そこで、弁護士は、特許庁が設けている情報提供制度(商標法施行規則19条)を利用して相手方の登録そのものを阻止することを相談者に提案しました。
▶参考情報:情報提供制度(商標法施行規則19条)とは?
この制度は、第三者が、他人の商標出願に拒絶されるべき理由があると気が付いたときにその情報を特許庁に提供し、特許庁に登録を認めないように働きかけるものです。
▶参考情報:商標法施行規則19条
第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
・参照:「商標法施行規則」の条文はこちら
▶参考情報:情報提供制度については、特許庁の以下の「商標登録出願に関する情報提供」のページも参考にしてください。
・特許庁「商標登録出願に関する情報提供について」はこちら
この制度を利用すれば、相手方の商標が登録される前に、商標登録を阻止できる可能性がありました。
(2)拒絶理由を適切に主張し、裏付け資料を提出することが重要。
情報提供制度で他人の商標出願を拒絶するべき理由として主張できる内容は商標法により限定されています。
そこで、自社名の横取りという事実が、商標法で規定されているどの拒絶理由にあたるとして特許庁に伝えるべきかということも問題になりました。また、情報提供制度では、提供された情報について、裏付けとなる資料が必要です。しかも、提出まで時間がかかるようでは元役員の商標出願が認められてしまいますので、商標の審査までに提出を間に合わせる必要があり、短期に集めることができる資料でなければなりませんでした。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の見解について詳しく解説していきます。
(1)拒絶理由として公序良俗違反を主張することにした
情報提供制度で拒絶理由として主張できる内容は商標法4条1項に「商標登録を受けることができない商標」として記載されています。
今回は、元役員が無断で会社の使用していた商標を、個人で出願したという「商標の横取り」という事情がありました。
このような商標出願は「剽窃的商標出願」などと呼ばれます。
しかし、商標法の中には横取りした商標の出願を認めないことを直接定めたものはありません。そこで、弁護士としては、元役員の横取りによる商標出願は、商標法4条1項7号に「商標登録を受けることができない商標」としてあげられている「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」にあたるから、商標出願を認めるべきではないという主張をしました。
(2)提供資料の選択も重要
本件では、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」にあたることを主張するために、特許庁に対して、元役員が会社で使っている名称であることを知りながら商標登録申請をした、ということを主張する必要がありました。
そのため、まず、元役員が出願当時、相談者の会社の役員であったことがわかる資料として、会社の登記事項証明書を提出しました。
また、その商標が相談者の会社で実際に社名として使われていたことがわかるように、会社のウェブサイトを印刷したものや会社が使っているパンフレット等を提出しました。
(3)弁護士による情報提供の結果、元役員の商標登録を阻止できた。
上記のような資料をつけて特許庁に公序良俗違反であることを情報提供した結果、特許庁はこの元役員の出願に対し、商標出願を認めない予定であるという内容の拒絶理由通知を送りました。
なお、情報提供制度では、情報提供の際に、利用情報のフィードバックを希望する旨を記載しておくことにより、後日、特許庁より、提供した情報が商標の拒絶理由に使われたか否かの通知を受け取ることができます。
本件では、弁護士による情報提供から約1か月後に、特許庁から提供した情報を元役員に対する拒絶理由に利用した旨の通知が届き、情報提供制度の利用が功を奏したことがわかりました。
(4)自社の商標登録を認めてもらうためにはさらに対策が必要になった
特許庁が元役員に拒絶理由通知を送っても、制度上、すぐに元役員の商標出願が却下されるわけではありません。元役員には意見書などを提出して反論する機会が与えられるため、まだ元役員が出願した商標の審査は続くことになります。
本件では、情報提供制度の利用により元役員の商標を認めるべきではないことを特許庁に伝えるのと並行して、会社として自社名の商標登録を申請していました。
しかし、元役員による商標出願の審査が続いている間に、会社の出願した商標の審査が始まると、会社の出願した商標は、すでに出願されている商標と同じであるという理由で認められないことになります。
そこで、弁護士から、元役員の商標の審査が終了するまでは、会社の商標の審査は停止するべきであるということをあわせて主張しました。
その結果、元役員は会社名の商標出願を取り下げ、その後に相談者の商標出願の審査が行われて、無事に会社を権利者とする商標登録がされました。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、弁護士が退職者による商標申請の弱点を検討し、特許庁の情報提供制度を利用することによって、退職者による商標横取りを阻止することができました。あわせて、会社を権利者とする商標登録を実現することができました。
本件は、たまたま、元役員が相談者を辞める際に、「会社の商標は自分がもらう」などと述べていたことから、会社が調べた結果、元役員の個人名で商標の登録出願が出されていたことを発見できたケースです。
しかし、実際には、自社名を他人が商標出願していても、気づくことは多くありません。
むしろ、他人による商標登録がされてしまってから、商標権侵害の主張などを相手からされて、はじめて自社名について他人に商標をとられてしまったことに気づくケースが大半です。
このように気づくのが遅れると、「情報提供制度」により相手の商標を無効にすることはできず、相手の商標権を争う方法としては、商標法の規定にある「無効審判」を請求することになります。
しかし、無効審判の請求では、商標の無効を認めてもらうために多大な時間や費用がかかります。
今回は、相手の商標出願を審査段階で見つけることができたため、登録される前に阻止することができました。
今回のようなことが起きないようにするためには、自社で使用中の名称やロゴについては、できる限り早く商標権を取得しておくことが非常に重要です。
くれぐれも自社の大事な社名やロゴ、商品名、サービス名について商標登録を怠り、他人に商標権をとられることがないようにしてください。
しかし、万が一、商標登録をうっかり忘れていたというような場合には、本件のように早く対処することがなによりも重要です。早めに専門家である弁護士までご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の商標権トラブルに関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の商標権トラブルに関する弁護士への相談サービスへの問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回の解決実績は、「退職者が会社の社名を商標登録して横取りしようとしたが、情報提供制度を利用して横取り阻止に成功した事例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した商標権トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・自社が使用する商標が不正に他社に登録され、商標登録異議の申立てにより登録取消しに成功した事例
・靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例
・【特許庁から拒絶理由通知された商標出願トラブル】弁護士が特許庁に意見書を提出することで商標登録に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






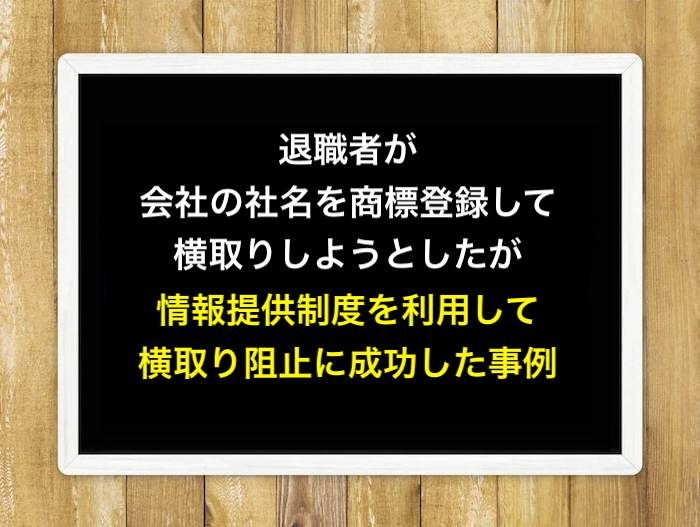

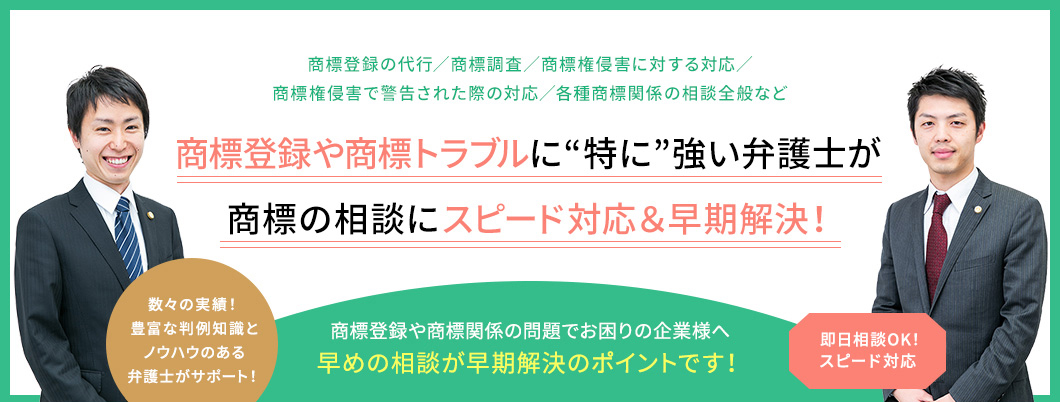
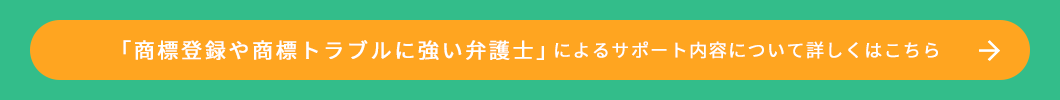
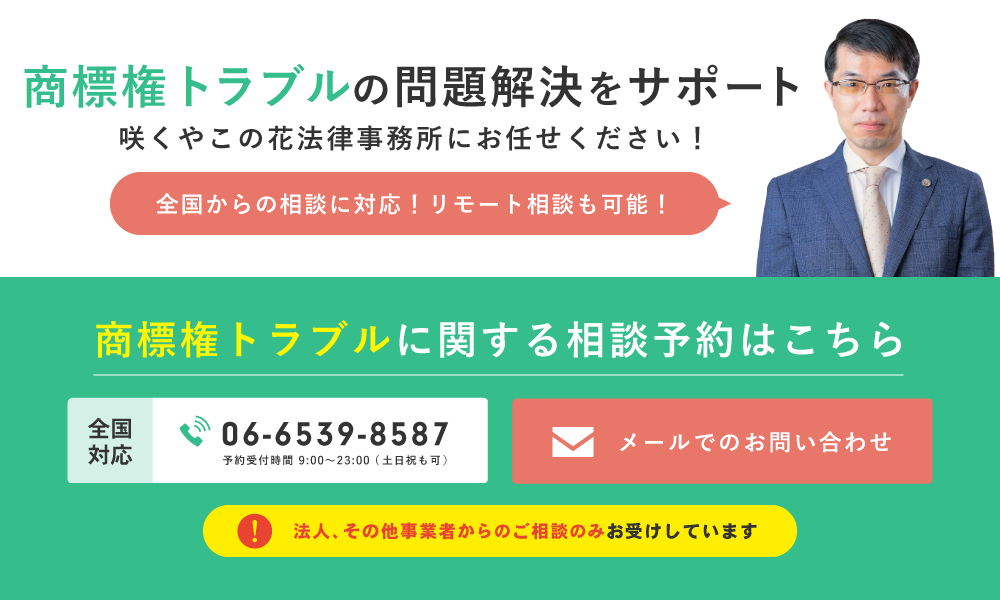
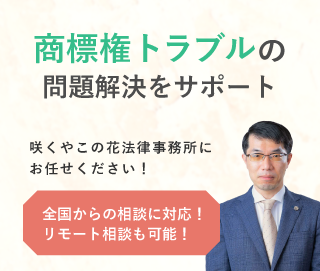





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















