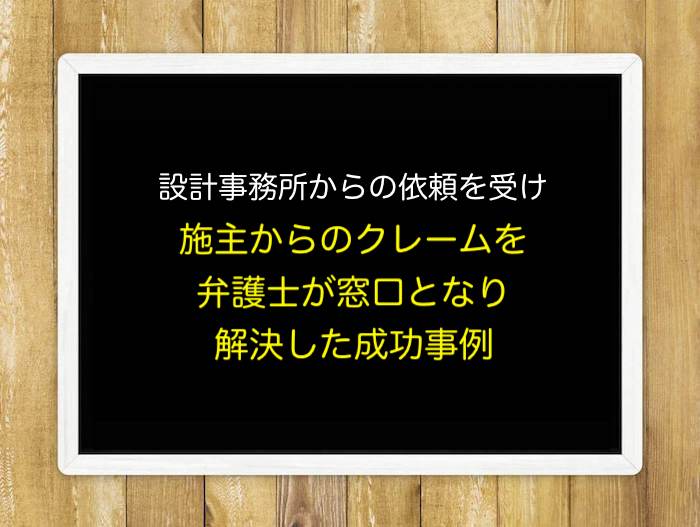
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕
出身地:兵庫県姫路市。出身大学:大阪府立大学総合科学部。主な取扱い分野は、「労務・労働事件(会社側)、保険業法関連、廃棄物処理法関連、契約書作成・レビュー、新商品の開発・新規ビジネスの立ち上げに関する法的助言、許認可手続における行政対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
本件の依頼者は設計事務所です。一戸建て住宅の施主から住宅を設計した設計事務所に対してクレームが入り、設計事務所からご相談をうけて弁護士が対応した事案です。
施主からのクレームの内容は「上の階に階段から家具を搬入できない」というものでした。
事案の詳細は以下の通りです。
- ●(1)設計事務所は施主からの依頼を受けて住宅の設計をしましたが、施主から設計事務所に対して、事前に、上の階に大きな家具を階段から搬入したいという要望はありませんでした。
- ●(2)設計事務所は、できあがった設計図については、施主に確認を求めてご了解していただいており、実際に施工された階段の寸法も設計図どおりでした。
- ●(3)施主から「階段から家具が搬入できない」というクレームが入ったのは、施主が住宅が購入してから約2年経過してからです。それ以前には施主からのクレームはありませんでした。
- ●(4)クレームは、施主本人からだけでなく、施主の知人を名乗る氏名不詳の人物からもありました。氏名不詳の人物からは、設計事務所に対する金銭の請求や設計事務所を刑事告訴するというような趣旨のメールが設計事務所宛てに送信されました。
このような経緯から、設計事務所が自社で対応することが困難になったので、クレームの対応について咲くやこの花法律事務所に依頼がありました。
2,問題の解決結果
弁護士名義で内容証明郵便を送り、クレームに理由がないことを伝え、今後弁護士が対応することを通知したところ、クレームを止めることができました。
3,問題解決における争点
住宅の設計トラブルで設計事務所が責任を負うかどうか判断するためのポイントは以下の4点です。
- ●争点1:建築基準法上の基準をクリアしているか
- ●争点2:図面どおりの施工がされているかどうか
- ●争点3:設計事務所が図面以外に施主との間で「特別な約束」をしていないか
- ●争点4:施主からの要望に対して、専門家として適切な説明をしているか
本件でも、上記4つのポイントが争点となりました。
4,担当弁護士の見解
弁護士において上記の4つの争点を検討しましたが、依頼者である設計事務所に責任が無い事案でした。
以下で争点ごとの弁護士の見解をご説明します。
争点1:
建築基準法上の基準をクリアしているか
設計トラブルに関して、必ず参照しなければならない法律は「建築基準法」です。
建築基準法施行令23条1項で、住宅の階段の寸法については、「幅:75cm以上、蹴上:23cm以下、踏面:15cm以上」にしなければならないと決まっています。上記建築基準法の規制をクリアしていれば、階段から家具が搬入できなくても、設計事務所が賠償責任を負うことはありません。これが原則です。
本件では、階段の幅は、「幅:75cm以上、蹴上:23cm以下、踏面:15cm以上」という建築基準法上の基準を当然クリアしていました。
争点2:
図面どおりの施工がされているかどうか
住宅の設計トラブルでは、建築基準法の基準をクリアしていたとしても、図面通りの施工がされているかどうかが別途問題になります。
建築基準法の基準というのは、最低限度の基準を定めたものです。そのため、設計事務所と施主との間で、図面により建築基準法を上回る寸法で階段を施工するという約束がされていた場合、話しは別です。
このような約束があるにもかかわらず、約束を下回る寸法の階段が建築された場合、仮に建築基準法上は問題がなくても、設計事務所は施主に対して責任を負う可能性があります。
この点、本件では、階段の寸法も含め、設計図面どおりに施工されており、施工についても問題ありませんでした。
争点3:
設計事務所が図面以外に施主との間で「特別な約束」をしていないか
住宅の設計トラブルでは、図面以外に施主との間で特別な約束をしていないかも問題になります。
実際にトラブルになる多くのケースでは、図面どおりに施工されています。つまり書面だけみると、約束どおりの設計がされているのです。しかし、図面とは別の口約束があったと施主に言われてしまうことがあります。
例えば、以下でご紹介する「東京地裁平成23年10月14日判決」は、施主から設計事務所との間で図面とは別の「特別な約束」があったと主張された事案です。
参考判例:
東京地裁平成23年10月14日判決
●事案の概要:
この事件でも、階段の幅が問題になりました。
つまり、施主は、「建物の階段室については荷物を上下階に搬入できる状態にすることを約束しており、階段の幅を120cm以上とする必要があった。にもかかわらず、設計事務所は、荷物を搬入できない狭い階段を設計した。」として、設計事務所に対して損害賠償を請求した事例です。
これに対して、設計事務所は、「施主に対して、荷物の搬入は2階の窓を外してそこから行うことを何度も説明しており、施主もこれを了解していた。」と反論しました。
●裁判所の結論:
裁判所は、設計事務所に責任が無いと判断し、設計事務所を勝訴させ、施主の請求を認めませんでした。
●裁判所の判断の理由:
裁判所が設計事務所を勝訴させた理由は、以下の2点です。
- ・理由1:施主が主張する120cmの設計幅は、階段室から家具等の荷物を搬入できる状態にすることを設計事務所が施主に約束していたことを前提とするものであること
- ・理由2:設計事務所と施主の間で、階段室から家具等の荷物を搬入できる状態にする約束をしたことを証明する証拠がないこと
つまり、この判例の事案では、設計図面とは別の口約束があったことを施主側が証明できず、設計事務所側が勝訴しました。
しかし、設計図面と別の口約束があり、施主側がそれを証明した時は、図面通りの施工がされていても、口約束が守られていないことを理由に設計事務所が敗訴する危険がありますので注意が必要です。
ご依頼の件では、階段から家具を搬入できるようにするなどという口約束がされていた事実はなく、この点でも設計事務所に責任がないことを、弁護士から施主に対して通知しました。
争点4:
施主からの要望に対して、専門家として適切な説明をしているか
住宅の設計トラブルでは、設計事務所が施主からの要望に対して適切な説明をしたかどうかも問題になります。
設計士には、法律上、施主に対する説明義務があります。建築士法18条2項で、「建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。」とされています。そして、説明義務に違反した場合は、設計事務所が施主に対して損害賠償義務を負うことになります。
この設計士の説明義務については、以下のような裁判例もあります。
参考判例:
東京地裁平成19年3月9日判決
●事案の概要:
この事案は、建築途中で、市から設計内容が建築基準法に違反することを指摘され、建築を継続することができなくなった事案です。
施主は建築を継続することができなくなったことによる損害の賠償を、この設計を担当した設計事務所に請求しました。
これに対して、設計事務所は、施主が本件建物の設計が建築基準法令に違反することを承知しながら、あえてその建築を強く求めたので、責任は、施主にあると主張しました。
●裁判所の判断:
裁判所は、施主側を勝訴させ、設計事務所に対して約900万円の損害を施主に賠償するように命じました。
●裁判所の判断の理由:
裁判所が施主側を勝訴させた理由は次の2つです。
・理由1:
まず、裁判所は、「施主は建築の専門的知識がないのだから、たとえ施主の要望が建築基準法令に違反する内容のものであったとしても、設計事務所としては、建物を建築基準法令に適合した設計にするように適切な説明、助言をして、施主の指示の再考を求めるなどの義務を負う」と判断しました。
・理由2:
そのうえで、裁判所は、「単に、施主が違法建築を求め、設計事務所がそれに従ったという場合は、設計事務所は建築士法上の説明義務を果たしたことにはならない。」と判断しました。
このように説明義務の観点からすると、単に形だけ施主の要望に従っていたというだけでは不十分と判断される可能性があることにも注意が必要です。
ご依頼の件でも、仮に、2階に設置する家具の種類や大きさまで事前に施主から伝えられていた場合は、設計事務所として、家具の搬入についても必要な説明を行う義務がありました。
しかし、実際には、事前に施主から2階に設置する家具について設計事務所が説明をうけたことはなく、代理人弁護士として、その点も指摘して、説明義務の違反もないことを内容証明郵便で通知しました。
5,解決結果におけるまとめ
設計トラブルについては、設計事務所として責任を負うべき事案かどうか見極め、不当な要求については、会社として毅然と要求を拒絶することが必要です。
今回の件では、弁護士が、設計事務所に責任が発生する事案ではないことを、施主に対して毅然とした態度で通知したことでクレームが解決しました。
自社では解決が難しいクレームでお悩みの方は、本件のように弁護士が窓口となってクレームに対応する方法がおすすめです。以下の「弁護士によるクレーム対応における、取扱い分野や解決実績、よくある相談事例」などの詳しい説明をご覧いただき、ぜひ、気軽にお問い合わせください。
6,咲くやこの花法律事務所のクレーム対応に強い弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「クレーム対応に強い弁護士への相談サービス」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回は、「設計事務所からの依頼を受け、施主からのクレームを弁護士が窓口となり解決した成功事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連したクレーム対応の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・化粧品販売会社が購入者から「まぶたが赤くなった」とクレームを受けて解決した成功事例
・衣類の購入者からの色落ち、色移りに関するクレームトラブルに対して弁護士が対応し、金銭賠償なしで解決した成功事例
・水道工事の騒音等に対する近隣店舗からのクレームや金銭要求に対し、弁護士が交渉して要求を断念させた解決事例
・休日、深夜にわたり執拗に電話を入れてくるクレーム客に弁護士が対応した解決事例
・化粧品の皮膚トラブルのクレームが発生!慰謝料等350万円を請求された事件が35万円の支払いで和解に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






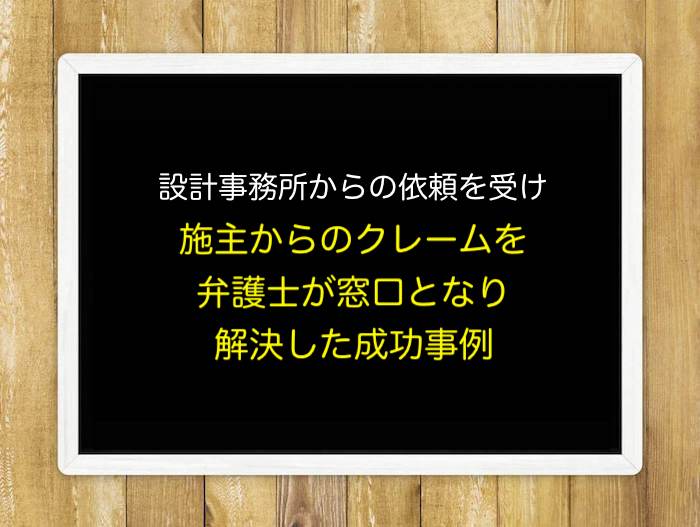

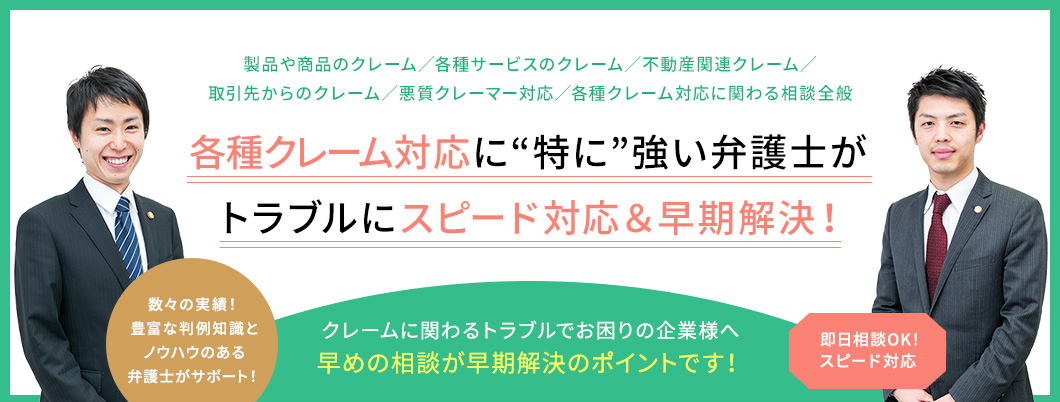


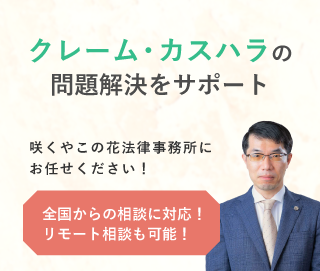





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















