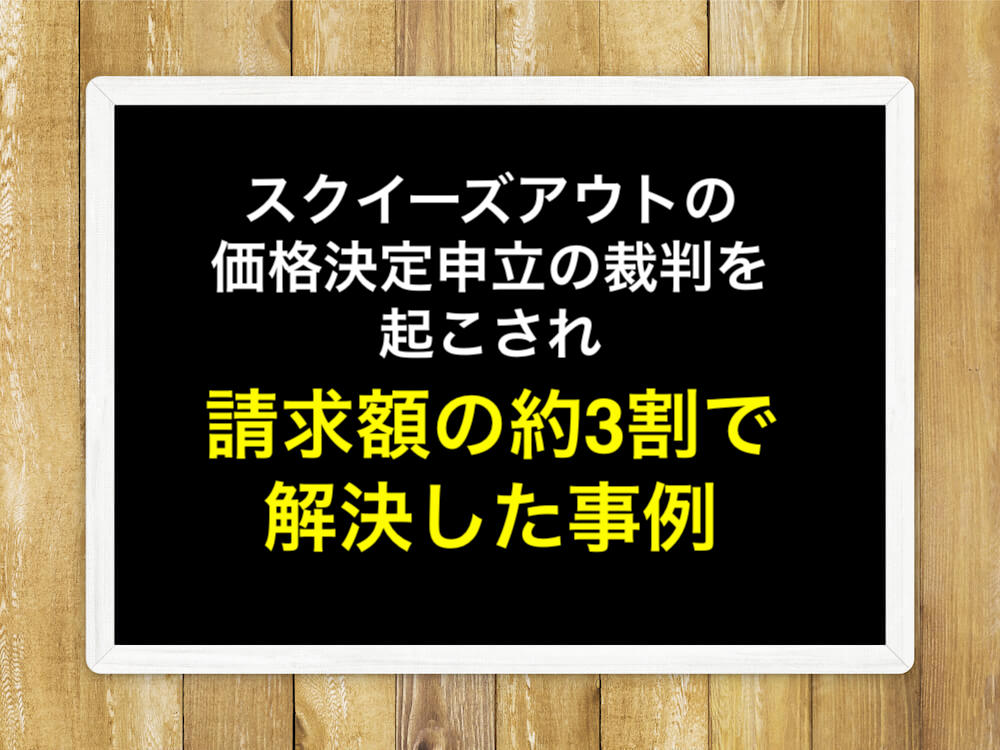
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「マンション賃貸業」の事例です。
2,事案の概要
最初に、本事案の概要についてご説明します。
本件は、一棟の賃貸用マンションを所有する不動産所有会社の多数株主が、対立する少数株主の株式の強制的な買い取り(スクイーズアウト)を行ったところ、株式の買い取り価格をめぐって、少数株主と争いになった事件です。
当方の依頼者はこの不動産所有会社の代表取締役です。
この代表取締役はこの不動産所有会社の多数株主でしたが、友好的でない少数株主(相手方)が1名いたことから、この少数株主から株式を買い取りたいというご相談をいただきました。
(1)まず9割以上の自社株を確保
当方の依頼者(多数株主)は、相手方少数株主と以前から折り合いが悪く、依頼者から相手方少数株主に株式の買い取りを提案しても、相手方少数株主が応じないことが予想されました。
そこで、弁護士から、会社法上の「特別支配株主の株式等売渡請求」の制度を利用することにより、少数株主から自社株を強制的に買い取ることも視野に入れることを助言しました。
この「特別支配株主の株式等売渡請求」は、議決権の90パーセント以上をもつ株主が、少数株主から強制的に株式を買い取ることを認める手続です。
ただし、本件の依頼者である多数株主は、ご相談の時点では、この不動産所有会社の株式の9割以上を持つには至っておらず、そのままでは、この制度の利用はできない状態でした。
そこで、まずは、本件の相手方以外の別の少数株主との交渉により自社株の買い取りを進め、9割以上の株式を確保することを助言しました。
そして、依頼者も助言通り自社の株式の買い取りを進め、自社株の9割以上を確保するに至りました。
(2)特別支配株主による株式等売渡請求制度を利用
依頼者が9割以上の自社株を確保した段階で、弁護士から、相手方少数株主に対して、まずは、合意による株式の買い取りを打診しました。
しかし、株価等について合意に至ることができなかったため、「特別支配株主による株式等売渡請求制度」を利用して、強制的な買い取りを行いました。
(3)価格決定申立に関する裁判を起こされる
「特別支配株主による株式等売渡請求制度」では、会社が相手方少数株主に対して、多数株主が決めた買い取り代金を通知します(会社法第179条の4)。
相手方少数株主としては通知された価格に異議があれば、裁判所に売買価格の決定の申し立てをして、適正な株価の決定を求めることができます(会社法第179条の8)。
本件でも、相手方少数株主から、裁判所に売買価格の決定の申し立てがあり、裁判所で、株式の価格が審理されることになりました。
3,問題の解決結果
裁判所での審理の結果、株式の買い取り価格について、相手方少数株主主張額の約3割の価格で株式を買い取り、解決することができました。
4,問題の解決における課題
本件の解決にあたっては以下の点が課題となりました。
裁判所での審理では、相手方少数株主から、高額な買い取り価格を主張されました。
相手方少数株主の主張の根拠となったのは、この不動産所有会社が所有する資産であるマンションの敷地について、土地価格の値上がりにより多額の含み益がでていた点です(以下では、このマンションのことを「本件マンション」と呼びます)。
不動産所有会社の決算書(貸借対照表)では、本件マンションの敷地の帳簿上の価格として、この会社が、敷地を購入したときに支払った代金額が計上されていました。
しかし、これは約30年も前の価格であり、敷地を時価で評価しなおすと、帳簿上の価格よりもはるかに高額になる状況でした。
そのため、相手方少数株主からは、時価で評価しなおした敷地価格をベースに、本件マンションの価値を算定したうえで、それを踏まえて、この不動産所有会社の株価を算定するべきだという主張がありました(時価純資産方式)。
当方の依頼者としては、できるだけ安い価格で、株式を買い取りたいと考えていましたので、相手方の主張にどのように反論していくかが課題になりました。
5,担当弁護士の見解
本件マンションの敷地が、敷地購入当時よりも大幅に値上がりし、それにより、会社の価値が上がっていることは否定できない状況でした。
しかし、その中でも少しでも買い取り価格(株価)を下げるために、以下の点を弁護士から主張しました。
(1)相手方提出の不動産査定書の矛盾点を追及
相手方は、2社の不動産業者に本件マンションの買い取り査定書を提出させて、この査定書を根拠に、本件マンションの価値が高額であることを主張していました。
こういった場面では、専門業者の査定書が提出されたからといって、それをうのみにせず、相手方提出の不動産査定書をよく検討して、矛盾点や不合理な点を徹底的に追求することが必要です。
本件では、例えば以下の点を指摘しました。
- ●都心部のマンション用地では一般に最寄り駅に近ければ近いほど高額になるのが通常であるのに、本件マンションよりも駅に近い別の土地の取引事例における地価よりも、本件マンションの敷地が高く査定されていたこと
- ●相手方が提出した2社の不動産業者のマンションの査定書に内容の食い違いがあること
- ●マンションの保全状況などを不動産業者に確認させないまま、外見だけで不動産業者に査定させたと考えられ、査定が正確とはいえないこと
(2)マンションの保全状況がよくないことを主張して反論
さらに、株式の価格を下げるために、本件マンションの保全状況がよくないことも主張しました。
本件マンションは築30年近いマンションでしたが、1度しか大規模修繕がされていませんでした。
国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」によると、マンションについて外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は、12年程度が適切とされています。
本件マンションはこのようなガイドラインと比較しても十分な修繕がされておらず、今後、多額の修繕費が発生する見込みであるから、株価もその点を踏まえて算定すべきだということを主張しました。
この主張は裁判所でも採用され、株価を下げることに大きく貢献しました。
(3)建築基準法上の問題点を指摘
建築基準法上、マンションを建築する際は、建築確認申請をしたうえで、建築後に完了検査を受けることが必要です。
この建築後の「完了検査」は、建築確認申請の際に申請された建築計画の内容通りに建物が建築されているかどうかを確認する重要な手続きです。
しかし、本件マンションが建築された当時、半数以上の建築物がこの完了検査を受けていない実態があり、本件マンションも完了検査を受けていませんでした。
完了検査を受けていないことは、本件マンションを売却する際の値下がり要因になります。
そのため、本件の審理でも、本件マンションが完了検査を受けていないことを考慮して、株価を押し下げる方向で考慮されるべきだという主張を行いました。
6,解決結果におけるまとめ
裁判所での株価の算定方法には、DCF法式、収益還元法式、配当還元法式、時価純資産方式などがありますが、現実には、複数の方式で算定したうえで、その算定結果の中間的な値を採用する判断がされることが多くなっています。
本件では、相手方少数株主から、特に時価純資産方式の立場から、マンションの敷地の時価が大幅に値上がりしていることを株価に反映すべきだとして、高額の株価での買い取りを主張されました。
しかし、前述した反論の結果、相手方少数株主の主張額より大幅に低い約3割程度の価格で解決することができました。
本件では、この株式の強制買い取りにより、当方依頼者は、会社のすべての株式を取得しました。これにより、今後の会社経営において、少数株主の意向を気にしなくてよくなり、また、株主総会の招集や開催も必要なくなりました。
これは非常に大きなメリットでした。
少数株主からの株式の買い取り(スクイーズアウト)についてお困りの方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の株式関係に強い弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「株式関係に強い弁護士への相談サービス」への今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 06-6539-8587
06-6539-8587






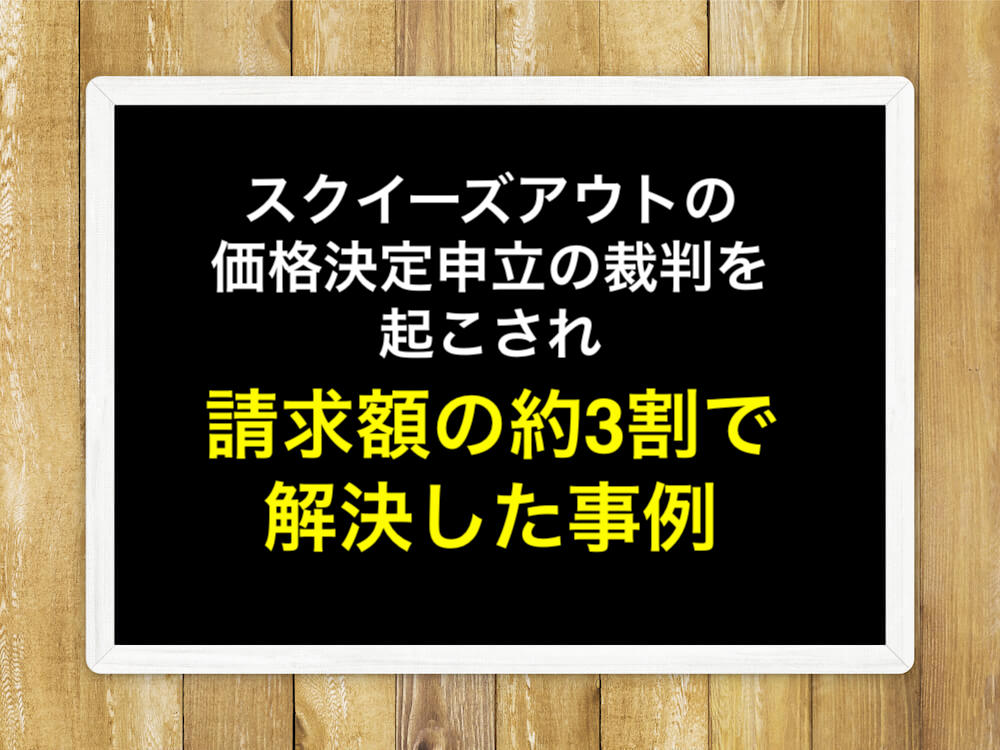

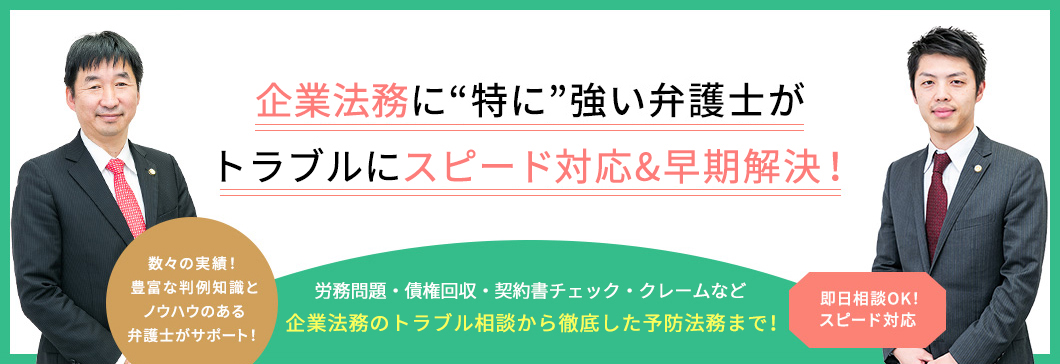

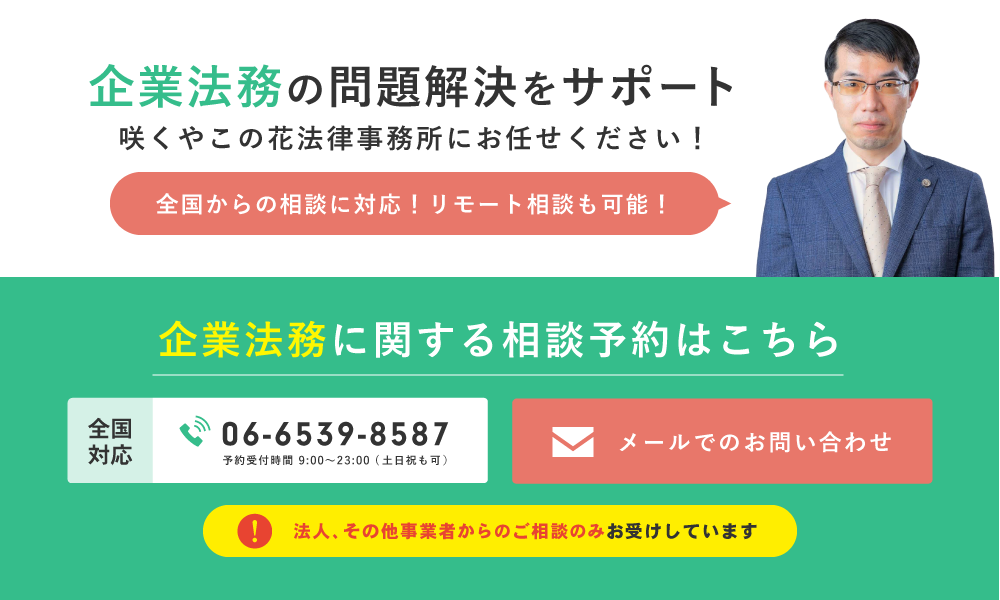
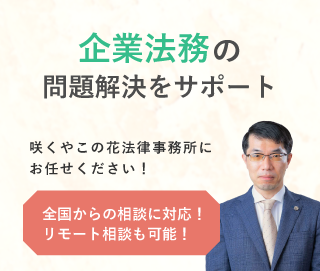





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















