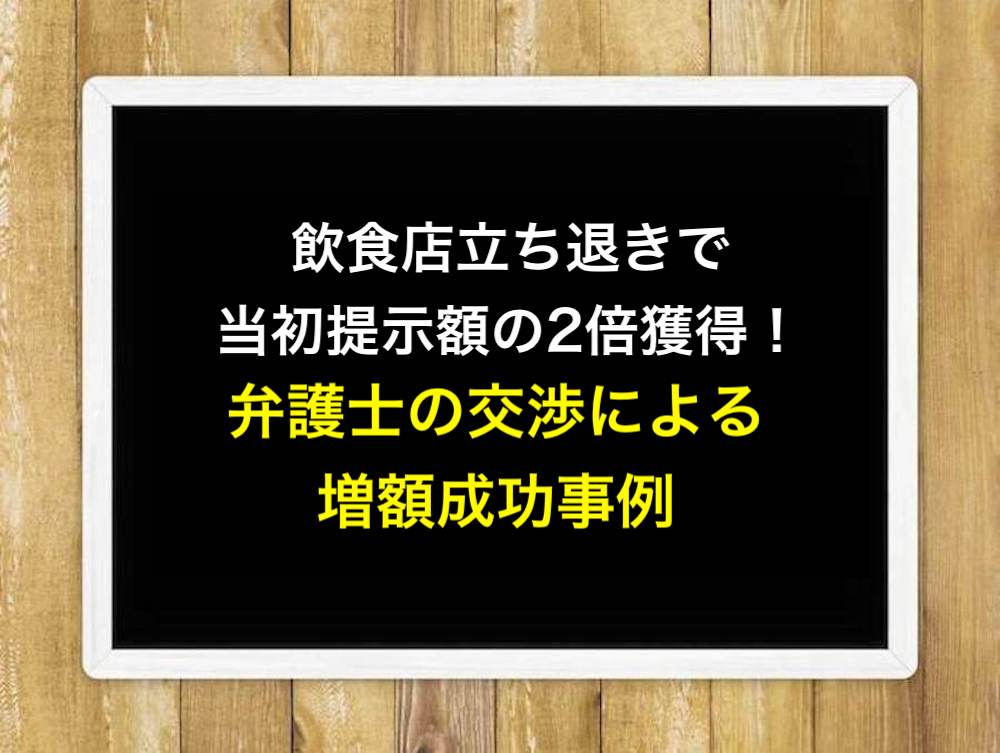
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 片山 琢也
出身地:大阪府。出身大学:京都大学法学部。主な取扱い分野は、「労働関連(組合との団体交渉、就業規則や契約書作成・チェック、残業代請求・解雇トラブルへの対応、従業員のメンタルヘルスから職場復帰へのアドバイス、従業員間のトラブルへの対応等)、債権回収、システム開発トラブル、建築業の顧客トラブル対応、インターネット上の悪質記事の削除請求など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
本件は、再開発に伴い、飲食店が立ち退きを求められた事案です。相談者は、その場所で10年間、飲食店を営んでいました。店舗物件の家主は個人オーナーでしたが、ある日、家主が不動産会社に変更になったとの通知を受けました。そして、その直後に今年中に立ち退くように求められました。
立ち退き理由として、表向きは老朽化と説明されましたが、隣の建物でも立ち退きの話が進んでおり、実際は再開発に伴う立ち退きの要請でした。相談者は、この店舗での事業が唯一の仕事であり、立ち退くと仕事を失うことになってしまう状況でした。
また、仮に別の場所で同じく飲食店を始めるとしても常連客を失ってしまうため、そのことにも不安を感じていました。そのような中で、立ち退きに応じたら一定額を支払うと提案されているが、それを受け入れなければならないのか、提案されている金額は妥当な額なのか教えてほしいと、咲くやこの花法律事務所にご相談いただいた事案です。
2,問題の解決結果
弁護士と相談者で協議し、立ち退きに応じる方針で交渉することになりました。そして、相談者の意向を踏まえて弁護士が適切な補償金額を算定し、その支払いを求めて事業者(新しい家主)と交渉しました。交渉の結果、当初提示額の2倍を超える金額の立退料を獲得できました。
3,問題解決における争点
本件の争点は、以下の通りです。
(1)正当な理由の有無
立ち退きを求められた場合、要求を受け入れて立ち退かなければならないのか、それともこれを拒むことができるのか。この点を判断する重要な基準が、貸主側に立ち退きを求める「正当な理由」があるといえるかどうかです。
例えば、貸主の経済状況が厳しくその建物以外には住む場所も用意ができない状況である一方、借主には余裕がありその建物を利用できなくなっても影響がないような場合もあります。そのような場合は、貸主に立ち退きを求める正当な理由があり、これを断ることは難しいといえます。逆に言えば、このような正当な理由がなければ立ち退きの要求に応じる必要はありません。
正当な理由が有るかどうかはとても重要です。それによって、その後の貸主側との交渉の仕方が大きく変わってくるからです。立ち退きを拒否したい場合はもちろん、立ち退きを受け入れるとしても、正当な理由がない場合は立ち退く側の要望を主張しやすくなり、より有利な立場で交渉できます。ただ、正当な理由があるかどうかの判断は、様々な事情を総合考慮する必要があるため、一部事案をのぞいて簡単には判断はできません。
本件でも、弁護士が賃貸借契約書や相談者の飲食店経営の実情などをお聞きして、正当な理由の有無を検討しました。結論としては、正当な理由があるとは言えないと判断しましたが、相談者が立ち退く前提での交渉を希望されたため、主に立退料、その他立ち退きの条件について交渉を行いました。
(2)立ち退き条件の検討
1,金銭補償
立ち退きを受け入れる場合、多くの事案では、金銭的な補償を求めることができます。いわゆる立退料というものです。賃貸借契約は、居住目的であっても商業目的であっても借主の生活または営業の基盤となっていることが多く、立ち退くとなると借主に大きな影響があることが通常です。そのため、立ち退きを求める貸主側は、借主側に対し、その影響に見合うだけの金銭補償をおこなう必要があります。そして、この補償金額の算定では事案に応じて様々な項目が考慮されます。
本件のような飲食店舗の場合は、例えば以下のような項目が考慮されます。本件でも、下記項目ごとに金額を算定し、その合計額を補償額として貸主側と交渉をしました。
- ●移転先物件で開業するための内装費用
- ●現店舗と移転先の家賃に差額がある場合、一定期間の差額分の補填
- ●移転先への引越し費用
- ●移転に伴う休業補償
- ●移転を顧客に案内する際の費用
- ●営業補償(移転先での事業が軌道にのるまでの補償)等
2,立ち退き時期
立ち退きを求められた場合、貸主側が一方的に期限を設定して要求してくることがあります。本件でも年内での立ち退きを求められました。このような一方的に設定された期限は、基本的に気にする必要はありません。
既にご説明のとおり、賃貸借契約は借主の生活または営業の基盤になっていることが多く、移転には大きな負担を伴います。貸主側の一方的な期限は気にせず、立ち退くとしても自身の都合にあわせて、無理のないスケジュールで実施することで問題ありません。
本件でも、立ち退き条件を交渉する方針が決まった際、立ち退き時期については未定として貸主側に通知しました。結果的に、貸主が希望した期間内に退去が完了しましたが、十分な補償を得たうえで相談者にとって無理のないスケジュールで退去しました。
3,その他の条件
立ち退きの場面では、立退料や立ち退き時期のほかにも、交渉事項があります。本件では、現在の店舗の家賃や退去の際に必要となる原状回復費用について、立ち退きに応じる代わりに、一定程度免除してもらうことができました。さらに、立ち退きの際、不要な荷物は置いたままでよいという条件も受け入れてもらいました。
事案ごとに異なりますが、債務の免除については、個人的には金銭補償のように貸主側が別途支払うものに比べて、応じてもらいやすいと考えられます。また、立ち退き事案では、その後に建物の取り壊しが予定されている場合も多く、その場合は上記のような原状回復不要、不要物を置いたままでよいという点は、受け入れてもらいやすいと考えられます。
4,担当弁護士の見解
担当した弁護士の見解は、以下のとおりです。
(1)交渉条件の協議
交渉方針を決定するため、弁護士が相談者から必要事項の聞き取りをしました。上記で説明のとおり、正当な理由の有無や、立ち退く際に求める条件をつめていくためには、詳しい事情を確認する必要があるためです。
相談者から賃貸借契約書、現店舗の開業準備に関する資料、立ち退きを求められた際の通知書面等、関連資料を提供してもらい、弁護士がその内容を確認しました。
そして、相談者からは、現在の店舗の収支状況や、現在の収入はこの店舗売上だけなのか他にも収入があるのかなど、必要な事項を聞き取りました。
これら聞き取った内容から、この店舗での営業が相談者の生活にとってどれだけ重要であるか、現在の場所に根差した事業のため移転したとしても現在の営業状態を再現することは容易でないことなど、弁護士が今後の交渉に必要となる事項をまとめました。
この時、相談者からは、現在の店舗にたくさん思い出があること、収入は多くないが長年続けてきた仕事で自身の生活の基本になっていることなどを伺いました。
そして、交渉をどう進めていくかの方針について意見を確認すると、できれば立ち退かず、今のまま営業を続けたいとのことでしたが、隣接するビルの立ち退きも進んでおり、自身だけが残っても仕方がないとして立ち退きは受け入れるつもりだと話をしてくれました。相談者との協議の結果、立退くことを前提に、金銭補償を含め適切な条件を合意する方向で交渉することになりました。
(2)協力事業者との協議
立ち退きをする場合の金銭補償に、移転先への引っ越し費用、移転先で開業する際の内装工事費用、移転先との差額家賃の補償など、移転先を踏まえて算定される費用があることは上記に記載した通りです。そのため、実際に移転するかどうかは別として、適切な補償内容を算定するためには、移転先候補となる物件を探す必要があります。
本件では、相談者が懇意にしている事業者がいるとのことで、その事業者に協力してもらい移転先を探すことになりました。この事業者は、内装工事費用の見積もり作成などにも協力してくれるとのことでした。
ただ、協力事業者としては、立ち退きの交渉のためにどのような資料を用意すればよいかわからないとのことでした。そこで、弁護士が協力事業者と協議し、店舗面積や移転先地域など移転先候補として望ましい条件や、内装工事の見積りに記載してほしい内容などを説明しました。移転先候補物件と現店舗の条件があまりに異なると算定資料としては利用しにくく、また内装費用の見積りも内容が抽象的過ぎると同じく算定資料としては利用しにくいものとなってしまいます。そのような点を、弁護士から協力事業者に伝え、交渉に使いやすい資料を準備してもらいました。
(3)貸主側との交渉
以上の準備をしたうえで、弁護士が代理人となって貸主側との交渉に臨みました。
交渉の基本ではありますが、できるだけ有利な立場にたって交渉することが大切です。そのため、大前提として本件では「正当な理由」があるとは思われず、立ち退きに応じる必要がないと判断していることを伝えました。そして、貸主に対し、立ち退くのであれば十分な補償をしてもらう必要があると説明しました。実際、相談者にとってこの店舗の売り上げが唯一の収入であり、生活の基盤となっていました。立ち退くことは収入が途絶え、生活の基盤を失うことであり、簡単に応じられるものではありませんでした。その点を貸主側にも十分に認識してもらうことが重要でした。この点について共通の認識を持てていないと、金額交渉をしてもうまくいきません。共通認識を欠いたままだと、当方が求める補償額を適切だと思ってもらえず、法外な金額だと受け取られてしまうためです。
弁護士が粘り強く交渉した結果、貸主側から金額の譲歩を引き出し、当初提示額の2倍を超える金額で合意をすることができました。あわせて、退去前3か月間の家賃免除、原状回復義務の免除、不要物を置いて退去すればよいことなどの条件も加えることが出来ました。
(4)最後の条件交渉
立ち退きについての条件は概ねまとまりました。しかし、立退料(補償金)の支払いについて貸主側から合意時と明渡時の2回に分けて支払いたいと要望がだされました。貸主側の立場からは、実際に明渡しがされるまでは安心ができないため、明渡前に全額支払うことは避けたいとするこの提案は理解ができるところです。
しかし、相談者にとっては移転作業に費用がかかるため、先にまとまった金額の支払いを受けられないと移転作業を進めることが出来ないという事情もありました。また、相談者としては現店舗の明渡しから移転先の開業までの事業がストップする期間をできるだけ短くしたいところです。
貸主に対して弁護士から事情を説明し、支払いが2回に分かれるとしても合意時の支払額を増額してもらえるように交渉しました。結果、相談者も受け入れられる金額を合意時に支払ってもらえることになり、合意書の取り交わしに進むことが出来ました。
このように最終的に合意に至りましたが、相談者としては愛着のある店舗を立ち退くことはやはり辛いとのことでした。そして、望んで立ち退くわけではないこと、相談者にとっては大切なものを奪われたような気持でいることをわかってほしいという趣旨のお話がありました。
5,解決結果におけるまとめ
(1)立ち退き事案ではこまかな事情を整理して主張する必要があること
以上で説明の通り、そもそも立ち退かなければならないのか、立ち退く場合でも十分な補償を受けられるのかは、正当な理由が有るかどうかがとても重要です。
しかし、正当な理由が有るかどうかの判断は考慮しなければならない事情も広い範囲にわたり、その判断は簡単ではありません。また、十分な補償を求めて貸主側に主張する際には、こまかな事情をよく整理したうえで主張する必要もあります。さらに、適切な補償費用の算定についても、何が補償対象となるのか、補償対象になるとしてどのように算定をするのか等が問題になります。
(2)迷ったときは弁護士に相談
立ち退きを求められる事案では、何の補償もせずに立ち退きを要求してくることはあまりなく、貸主側から一定の立退料が提案されることが多いと思われます。適切な条件かどうかの判断がつかないまま、貸主側の提案に応じてしまうこともあるのではと思っております。しかし、貸主側から提示される立退料は、本件のように事情をよく考慮すれば、適切な補償とは言えないことも多いです。適切な補償を得るためにも、専門家である弁護士にぜひご相談ください。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。
6,咲くやこの花法律事務所の立ち退きに関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の立ち退き事案に関する弁護士への相談サービスへの問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回の解決事例は、「飲食店立ち退きで当初提示額の2倍獲得!弁護士の交渉による増額成功事例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した不動産トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・貸店舗所有者からテナントの立ち退き交渉について依頼を受け、賃借人請求額約1300万円に対し、半額以下で解決できた事例
・賃料滞納を続けた飲食店のテナントを強制執行により明け渡しを実現した解決事例
・オフィスビルの家賃滞納トラブルが発生!賃料滞納したテナントを退去させて全額約200万円の回収に成功した事例
・不動産業者が競落した土地を建物の居住者が明け渡さなかったため、裁判・強制執行により不動産の明け渡しを実現した解決事例
・社宅として賃借しているマンションの階下への漏水事故について弁護士が対応し管理会社からの要請を諦めさせた事案
 06-6539-8587
06-6539-8587






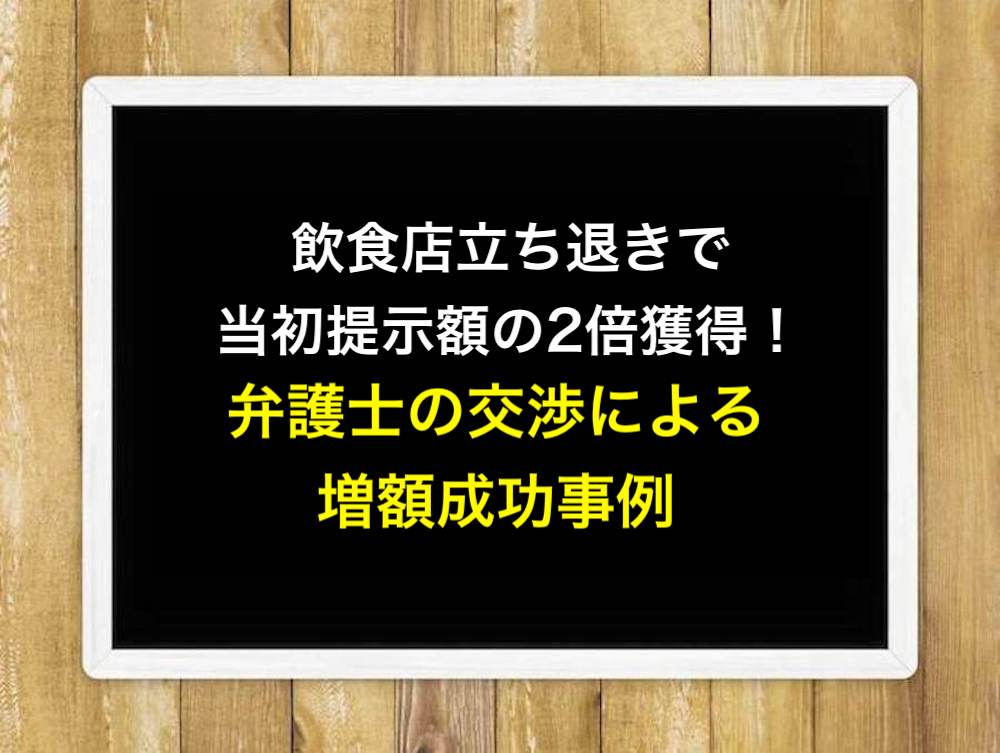

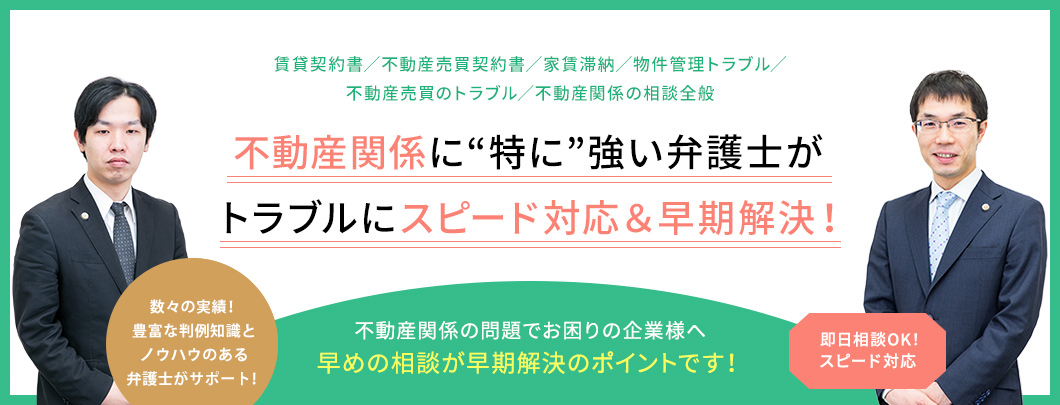
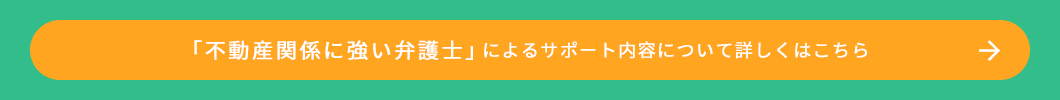
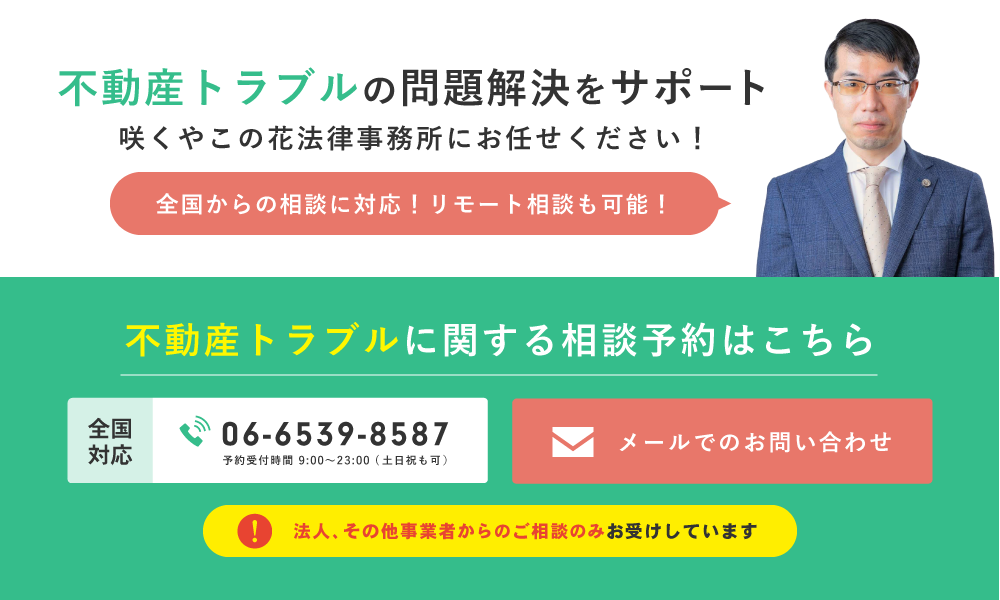
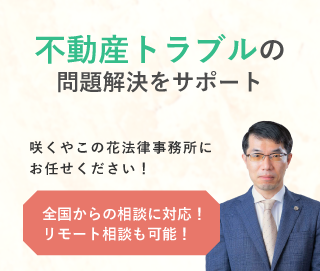





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る
















