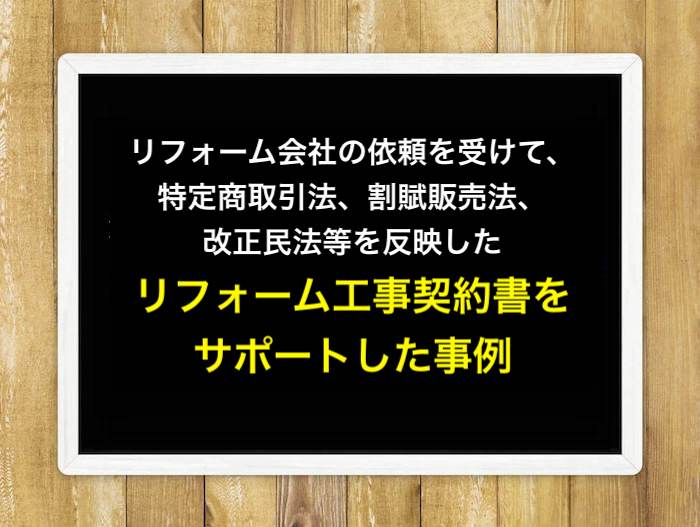
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 堀野 健一
出身地:大阪府岸和田市。出身大学:大阪大学。主な取扱い分野は、「労務・労働紛争の解決(従業員の解雇トラブルや従業員に対する退職勧奨、従業員からの残業代や未払賃金の請求)、不動産紛争の解決(不法占拠者に対する明渡の交渉・裁判・強制執行、賃料の回収、土地の境界の特定など)、システム開発紛争の解決、クレームの解決、就業規則・雇用契約書のチェック、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「リフォーム業者」の事例です。
2,事案の概要
ご相談者は、リフォーム事業をされている法人です。2020年4月に施行される民法改正にあたって、以前から使用されているリフォーム工事契約書の書式を見直しされたいとのことで、咲くやこの花法律事務所にご相談がありました。
3,ご相談内容の解決結果
本件のご相談者は、相談に来られるまでは、特定商取引法や割賦販売法に関する意識はほとんどなく、民法改正への対応を希望しておられるのみでした。
しかし、弁護士が相談者が現在使っている契約書を確認したところ、民法改正への対応だけでなく、特定商取引法や割賦販売法への対応もできておらず、非常にリスクが高い状態でした。
弁護士から特定商取引法や割賦販売法の適用に関しても対応が必要であることを指摘し、それも踏まえて、請負人側の立場に立った、新たなリフォーム工事契約書を作成していきました。
その結果、民法改正、特定商取引法、割賦販売法に対応した適正なリフォーム工事契約書が出来上がりました。
4,問題の解決におけるポイント
本件で弁護士が取り組んだ対応内容について、以下で詳しく解説いたします。
(1)建設業法への対応
まず、リフォーム工事を行うにあたっては、建設業法上、契約書を作成することが法律上義務付けられています。また、契約書に記載しなければならない事項も法律で決められています。(建設業法第19条)。そのため、建設業法上の記載事項を網羅することが必要でした。
(2)民法改正への対応
民法改正によって、「瑕疵担保責任」に関する規定が改正されました。まず、用語として、「瑕疵担保責任」という名称から、「契約不適合責任」という名称となりました。
また、工事に不具合があった場合、施主からの代金減額請求が新たに認められるようになりました(改正民法636条)。さらに、改正後の民法では、工事に不具合があった場合に業者が責任を負う期間が、施主が不具合に気づいた時から1年間とされました(改正民法637条1項)。
改正前の民法では、引渡日から1年間でした。改正後の民法に従えば、例えば、施主が引渡しから5年後に不具合に気づけば、その後も1年間は業者は責任を負うことになってしまいます。
この点は、リフォーム業者にとっては不利益な方向での改正であり、契約書での対応を要する重要なものです。これらの民法改正の内容を踏まえた契約書の作成が必要でした。
(3)特定商取引法への対応
リフォームの営業では、顧客宅など事業所以外の場所で契約を結ぶ場合も多く、その場合には、「訪問販売」として、特定商取引法が適用される可能性が高いです。そのため、特定商取引法の適用も踏まえて、契約書を作成することが必要になります。
特定商取引法でも、建設業法とは別に、契約書に記載すべき事項が決められています(特定商取引法4条、5条)。そのため、この記載すべき事項が漏れないように意識をして作成する必要がありました。
特定商取引法で定められた記載事項が漏れている場合には、法律上、施主側はいつまででも契約をクーリングオフできることになっています。
そのため、特定商取引法への対応は非常に重要です。
(4)割賦販売法への対応
さらに、リフォームでは工事代金を分割で支払ってもらうことが多く、その場合には、割賦販売法の適用があります。具体的には工事代金を、2か月を超える期間にわたり、3回以上の分割払いとする場合には、割賦販売法の適用があります。
そのため、割賦販売法の適用も踏まえて、契約書を作成することが必要でした。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の方針について解説していきます。
(1)建設業法への対応
建設業法19条によって、例えば、以下の事項を定めることが必要とされています。
まずはこれらの項目を確実に網羅することが必要です。
- ●工事内容
- ●請負代金の額
- ●工事着手の時期、工事完成の時期
- ●設計変更、工事着手の延期、工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- ●工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- ●注文者が工事に使用する資材を提供し又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- ●注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法、引渡しの時期
- ●工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- ●工事の目的物の契約不適合責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
1,追加工事代金のトラブルを契約書で予防することも重要
リフォーム工事でよくあるトラブルとして、追加工事費用の支払いをめぐるトラブルがあります。
追加工事が必要になった場合、本来的には、あくまで元の工事契約とは別になるので、別途工事代金が発生します。追加工事の代金について、追加工事について契約書を作った場合はもちろん、仮に契約書を作っていない場合でも、工事の内容に見合う報酬を請求することは可能です(商法第512条)。
しかし、追加工事代金の支払でトラブルになるケースでは、施主から、追加工事がもともとの工事(本工事)の契約の範囲内に入っていたという主張がされることがあります。
このような主張を施主にさせないために、本工事の内容を契約書で明確にすることにより、それ以外の工事が追加工事であることが明確になるようにすることが重要です。
この観点から、リフォーム工事契約書の「工事内容」欄には、以下の条項を定めました(下線部参照)。
「工事内容 添付見積書及び計画図面・仕様書に定めるとおり
※添付見積書及び計画図面・仕様書に記載無き事項はすべて別途工事とする。」
本工事の範囲については、単に見積書だけだと、どこに工事をするかが不明確であるため、図面を契約書に添付することが重要です。
図面で視覚的に認識できるようにし、できる限り工事の内容を特定するようにしました。その上で、「記載無き事項はすべて別途工事とする」と明記をすることで、図面等で特定した工事のみが契約の内容で、それ以外は全て契約外の別の工事であることを明確にしました。
(2)民法改正への対応
まず、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への用語の変更について契約書にも反映することが必要です。また、業者が施主に対して契約不適合責任を負う期間については、改正民法では、施主が「不適合を知った時から1年以内に通知する」ことが民法上定められています(改正民法637条1項)。
これは前述の通り、業者側に非常に不利な内容ですが、契約書で改正民法の期間を修正することが可能です。
そこで、契約書で改正民法の規定を修正して、契約不適合責任の期間を「引き渡した日から1年間」に限定しました。
具体的には、契約不適合責任の期間については、以下の条項を設けました(下線部参照)。
「発注者は、請負人に対して、本契約の目的物を引き渡した日から1年以内に、本契約の目的物に契約不適合がある旨を連絡しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、修補の請求、請負代金減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできない。ただし、請負人が、引渡し(引渡しを要しないときには、工事完成)の時点で、その契約不適合を知り又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。」
(3)特定商取引法への対応
リフォームの営業方法が「訪問販売」に該当する場合は、特定商取引法への対応も必要です。
特定商取引法にいう「訪問販売」とは、典型的に想定される「顧客宅に販売員が訪問する場合」だけでなく、広く「業者の事業所等以外の場所で契約を行う場合」を指します。
弁護士から本件のご相談者に確認したところ、事業所以外で契約書を作成することが多いということでした。そのため、この特定商取引法の適用があるものとして、契約書を作成することが必要でした。
1,特定商取引法で定められている記載事項とは?
特定商取引法上、契約書に記載すべき事項として、以下の事項があります(特定商取引法4条、5条、特定商取引法施行規則3条、4条)。
- ●役務の種類
- ●役務の対価
- ●役務の対価の支払の時期及び方法
- ●役務の提供時期
- ●クーリングオフに関する定め
- ●役務提供事業者(請負人)の名称、住所、電話番号、代表者の氏名
- ●契約の締結を担当した者の氏名
- ●契約締結の年月日
なお、「(1)建設業法への対応」で述べた記載すべき事項と重複する事項もありますので、それは、重複して記載することは不要です。
2,クーリングオフについての記載の注意点
上記の記載事項のうち「クーリングオフに関する定め」については、さらに、法律で、記載すべき具体的な内容が決められています(特定商取引法施行規則6条1項)。
この点を踏まえて、契約書にクーリングオフに関する条項を追加しました。なお、このクーリングオフに関する定めは、すべての文字を赤字とし、条項全体を赤枠で囲むことが必要とされています(特定商取引法施行規則6条6項)。
3,特定商取引法の記載事項の漏れについてのペナルティは重大
特定商取引法上記載すべき事項に漏れや不備がある場合、法律上大きく分けて2つのペナルティがあります。
●本来であれば契約後8日間に限定される施主からのクーリングオフが、いつでもできることになってしまいます。
例えば、契約から1年後でもクーリングオフをされてしまうことがあります。その場合には、業者側は、施主から受け取った代金を全額返還しなければなりません。
●記載事項の不備については6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(特定商取引法71条)。
このような重大なペナルティがあるため、特定商取引法の記載事項について、漏れがないように特に慎重に作成する必要があります。
4,記載の不備の典型例
特定商取引法の記載事項に不備があるケースの典型例としては、以下のケースがあげられます。
- ●クーリングオフの条項が赤字ではなく黒字で書かれている
- ●クーリングオフの条項が赤字で書かれているが、赤枠で囲まれていない
- ●「役務提供事業者(請負人)の電話番号」や「代表者の氏名」が記載されていない
- ●記載事項として「契約の締結を担当した者の氏名」が必要だが、「氏」だけしか記載されていない
- ●「よくお読みください」という文字を、赤字で表示した上で、赤枠で囲むことが必要だが正しく記載されていない
また、契約書の文字は、8ポイント以上の大きさの文字であることが必要です(特定商取引法施行規則5条3項)。このように細かな記載のルールがありますので、それに従って作成をしていきました。
(4)割賦販売法への対応
前述の通り、割賦販売法への対応が必要になりました。
ただし、「(1)建設業法への対応」、「(3)特定商取引法への対応」で述べた記載すべき事項と重複する事項もありますので、それは、重複して記載することは不要です。
一方、例えば、以下の事項については、割賦販売法に特有の記載事項ですので、漏れないように明記をすることが必要です。
- ●役務の現金提供価格(現金一括払いとした場合の価格)
- ●賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分)の額、支払期間、回数
- ●購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
なお、「購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号」については、請負人自身にすることでも構いません。
そのため、以下の条項としました。
「第〇〇条 お問い合せ窓口
本契約に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
記
株式会社〇〇 お問合せ窓口
TEL 〇〇‐〇〇‐〇〇(平日午前〇時~午後〇時)
※問い合わせ数の状況や問い合わせ内容等によって、対応に時間を要することがあります。」
この割賦販売法上の記載すべき事項が漏れている場合には、罰則が定められており、50万円以下の罰金とされています(割賦販売法53条)。
6,まとめ
以上の通り、リフォーム事業を行うためには、民法や建設業法はもちろんですが、特定商取引法や割賦販売法の適用も順守することが必要です。
そして、これらの法律の要件を満たした契約書を用いることが非常に重要です。
たとえば、前述のように、特定商取引法で定められた記載すべき事項に漏れがあれば、いつでもクーリングオフされてしまううえ、刑事罰まで科される可能性があるという、非常に危険な状態に陥ってしまいます。
このように弁護士に相談することで、相談者にとって思いもよらなかった法律の適用があることが判明し、それに適切に対応することが可能になることがあります。
今回は、民法の改正ということでご相談にお越し頂きましたが、それをきっかけに、特定商取引法や割賦販売法への対応もすることができました。法律の改正への対応はもちろん、使用している契約書の内容に不安のある方については、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の契約書に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「契約書に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】契約書テーマに関連した解決実績
今回は、「特定商取引法、割賦販売法、改正民法等を反映したリフォーム工事契約書のサポート事例」についてご紹介しましたが、この事例と関連する解決実績も以下でご紹介しておきますので、参考にご覧下さい。
・リゾート会員権販売事業の契約書を特定商取引法の要件を満たす内容でサポートした事例
・ECサイト運営会社の依頼を受けて、食料品の継続的売買契約についてリーガルチェックを行った事例
・職人への業務委託を準委任の形態で行う際の契約書をサポートした事例
・葬儀会社からの依頼で葬儀に関する契約書をサポートした事例
・中国企業との化粧品販売に関し、売買基本契約書をサポートした事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






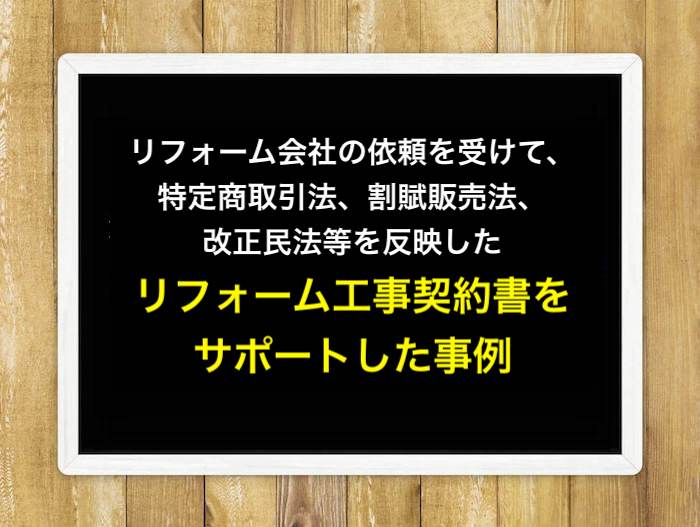

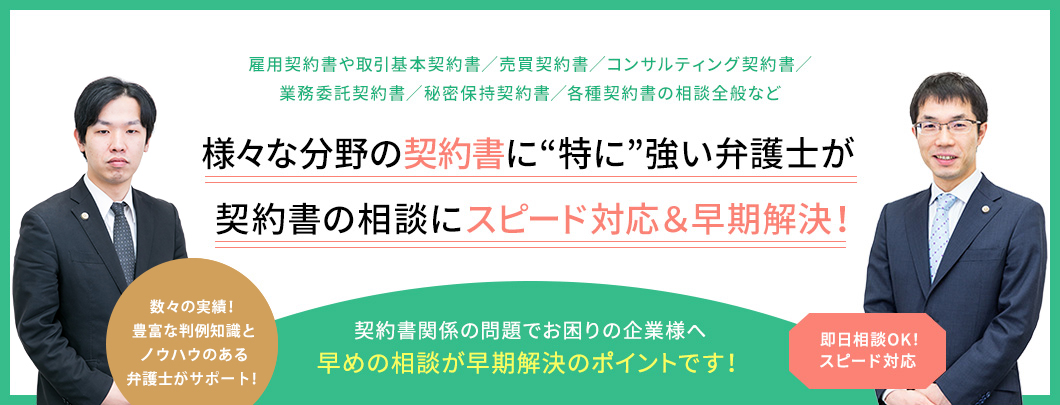
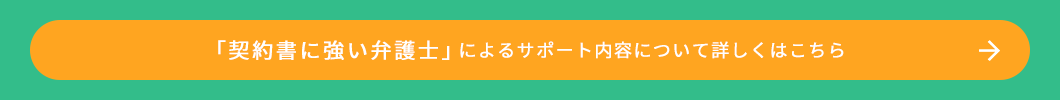
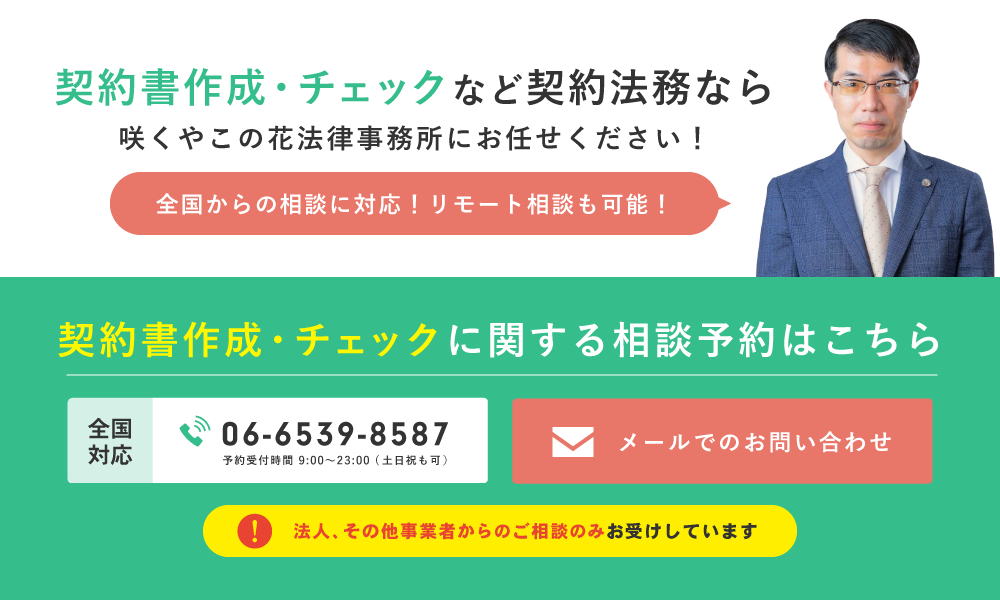
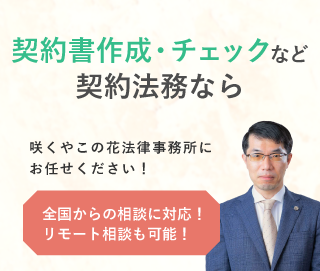





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















