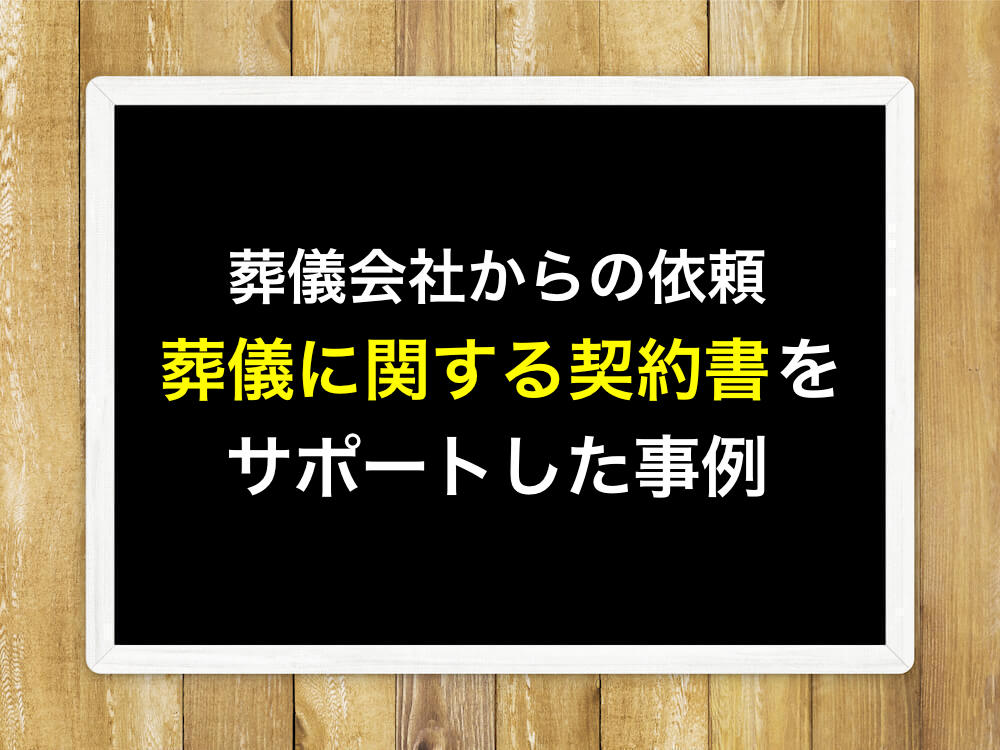
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕
出身地:兵庫県姫路市。出身大学:大阪府立大学総合科学部。主な取扱い分野は、「労務・労働事件(会社側)、保険業法関連、廃棄物処理法関連、契約書作成・レビュー、新商品の開発・新規ビジネスの立ち上げに関する法的助言、許認可手続における行政対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「葬儀会社」の事例です。
2,事案の概要
本件は、葬儀に関する契約書の作成を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただいた案件です。
葬儀に関する契約(葬祭契約)は口頭でされることも多いのですが、この場合、法的に見て、葬儀の依頼者が遺族の中の誰であるかすら不明確になりがちです。
もちろん、契約自体は口頭でも成立するのですが、書面に記載していなければ具体的に合意した内容が分からなくなり、「葬儀後に誰がいくらの費用を支払うのか」という契約内容について証拠が残りません。
口頭での契約の場合、中には口約束を反故にして、守らない葬儀の依頼者もでてきます。裁判をしなければ、費用を回収できないという事態は避ける必要があります。
3,ご相談内容の解決結果
葬儀会社の依頼により弁護士が葬儀に関する契約書を作成しました。
本件では、主に債権回収の観点から、葬儀費用の回収に支障をきたさない契約書を作成したいというのが、依頼者の要望でした。
要望を反映した契約書を作成することができ、満足していただくことができました。
4,弁護士が取り組んだ課題
葬祭契約について契約書を作成していない場合、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- (1)見積書に記載した内容について説明を受けていないと主張されて支払を拒否される
- (2)見積書に記載した費用とは別に追加料金が発生したのに説明を受けていないとして支払を拒否される
- (3)費用の説明をしていた相手方と喪主が別である場合に、どちらに費用を請求したらよいか分からなくなる
- (4)契約者が葬儀費用を支払うことができず、費用を回収することができなくなる
- (5)支払期限を明確に決めていなかったために、支払を先延ばしにされる
5,担当弁護士の見解
ここからは、前述の課題についての担当弁護士の見解をご説明していきます。
(1)契約の当事者を明確にする
契約をするためには、相手方が必要です。葬祭契約の場合、何も合意していなくても、喪主が契約の当事者になるという理解の仕方もあるでしょう。
しかし、そのような理解が常に正しいとは限りません。
葬祭契約の当事者とは、葬儀会社に葬儀を依頼し、その費用を負担することを葬儀会社との間で合意をした人のことです。一方、喪主は葬儀の主催者として参列者に対して遺族の代表としてふるまう立場の人をいいます。
喪主が葬儀会社に対して葬儀を依頼し、葬祭契約の当事者になることが多いと思いますが、喪主と葬祭契約の当事者が異なることもあります。
例えば、葬儀会社が、葬儀の内容や費用について喪主とは何も打ち合わせをしていないような場合、法的に見れば、喪主が葬祭契約の当事者とはいえない可能性があります。
このようなケースで、契約書を作成していなければ、葬祭契約の当事者があいまいになり、誰が葬儀費用を負担するのかについて親族間でトラブルが発生したときに、葬儀会社がこれに巻き込まれてしまい、葬儀費用の回収に困難を生じるおそれがあります。
そのため葬儀の契約書においても、喪主の欄だけでなく、契約の当事者を記載する欄を設けて、契約当事者を確定させることが非常に重要になります。
(2)どこまでのサービスが見積料金に含まれるのかを明確にする
葬儀を行う場合、写真、ドライアイス、お棺など費用ごとに見積書を作成することが多いと思います。そこで、契約書の別紙として見積書を添付したうえで、契約書に見積書記載の費用を負担しなければならないことを明確にします。
ただし、見積書の記載が抽象的なものだと、どのような場合に追加費用が発生するかが不明確になり、トラブルの原因となります。
例えば、葬儀費用一式100万円、商品代10万円、料理代20万円というような見積書ですと、どのような場合に追加料金が発生するか分からないので、適切ではありません。
見積書は、具体的なサービス名や商品名を記載し、項目ごとに費用を明記する必要があります。そうすることで、見積書の記載内容を超えるサービスの提供については追加料金が発生することを明確にすることができます。
なお、2021年4月以降、商品やサービスの値段である「価格」を、消費税分を加えた税込み価格で表示する「総額表示」が義務付けられていることにも注意してください。
契約書の具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が葬儀の契約者、乙が葬儀会社)。
▶参考例:契約書の条項例
第●条
甲は、乙に対し、本契約の各条項に従い、本契約添付の御見積書に記載された葬儀を依頼し、乙はこれを受託する。甲は、乙に対して、御見積書に記載されていないサービスを依頼する場合、御見積書とは別に追加料金を支払う。
(3)宗派についての合意も明確にする
葬儀契約については、どの宗派で行うかということが重要であることにも注意が必要です。
例えば、東京地方裁判所判決平成26年11月14日は、葬儀の依頼者が、自分の家族が信仰する宗派以外の僧侶により葬儀を行った葬儀会社に対して、葬儀費用の支払いを拒んだ事件です。裁判所は、「一般に,葬儀を主催する僧侶の属性は,葬儀において極めて重要な事柄であるから,原告と被告との間で,本件葬儀をa宗の僧侶に主催させる旨の合意が成立した以上,この合意は,本件葬儀契約の内容となっていると認めるのが相当であり,他にこの認定を左右する証拠はない。したがって,原告がa宗の僧侶でないDに本件葬儀を主催させたことは,本件契約の債務不履行を構成するというべきである。」と判断して、葬儀会社の契約違反を認めました。
その結果、葬儀会社は葬儀の依頼者に対し、50万円の慰謝料の支払を命じられています。
この事案で原告の葬儀会社は、葬儀の依頼者である被告が葬儀を安い価格で済ませることを重要視していたので、他の僧侶よりも布施を安く設定している別の宗派の僧侶に依頼したと主張しました。
しかし、裁判で、葬儀会社のこの主張は認められていません。
この裁判例からもわかるようにどの宗派で葬儀を行うかということは葬儀契約の重要事項の1つであり、この点を誤ると、葬儀の依頼者から慰謝料の請求をされることにもなりかねません。
葬儀契約書においても、どの宗派で行うのかという点についての合意の内容を記載する必要があります。
(4)連帯保証人を立てる場合、極度額を記載する
葬儀の依頼者の支払能力に不安がある場合は、連帯保証人を立ててもらうことも検討すべきです。
注意しなければならないのは、葬祭契約については将来的に費用が変動するので、民法の「根保証契約」に該当する可能性があるという点です。
「根保証契約」とは、事前に負担額が決まっていない契約について、保証するケースをいいます。
このような「根保証契約」については、民法により、連帯保証人の責任限度額(極度額)を定めなければ、連帯保証条項が無効になることが定められています。
▶参考情報:民法第465条の2
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
葬祭契約も根保証契約に当たる可能性があることを踏まえて、この民法の条文に従い、例えば、見積書記載の金額を連帯保証人の責任限度額(極度額)として記載しておくべきでしょう。
契約書の具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が葬儀の契約者、乙が葬儀会社、丙が連帯保証人)。
▶参考例:契約書の条項例
第●条
丙は、甲の乙に対する本契約上の一切の債務について、見積書記載の金○○円を上限として連帯保証し、甲と連帯して本契約上の債務の履行の責任を負う。
なお、連帯保証人制度については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
(5)請求方法と支払期限を明確にする
葬儀費用の請求については、弔問客の人数により飲食代や返礼品費が変動するので、後払いのケースが多いと思います。
契約書上は、請求の方法と支払期限、支払方法を必ず記載することが重要です。また、葬儀の依頼者の支払能力に不安がある場合、一定の金額を前払いで支払ってもらうという選択肢も検討すべきです。
契約書の具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が葬儀の契約者、乙が葬儀会社)。
▶参考例:契約書の条項例
第●条
1 乙は、●条に基づき葬儀費用を算出し、請求書を甲に送付するものとする。
2 甲は、葬儀の日から○○日以内に、葬儀費用を乙の指定する銀行口座に支払うものとする。振込手数料は、甲の負担とする。
6,解決結果におけるまとめ
これまで、葬儀に関する契約は、見積書で済ませてしまっている葬儀会社も多くありました。
確かに、葬儀については、実際に葬儀が終わってみなければ費用が確定しない側面もあり、確定した金額を記載した契約書を作成しにくいという特殊性があります。
しかし、だからといって、契約書を作成していなければ、誰が契約の当事者かを確定できなくなり、費用の回収に支障をきたすケースが考えられます。
最近では遺族間のつながりが薄いケースも少なくなく、葬儀費用を誰が負担するかで、葬儀後にトラブルになるケースも存在します。
このような状況を踏まえると、葬儀についても、書面での契約書作成が必要になってきています。
そのほか、本稿では触れませんでしたが、遺族が出棺時刻までにあらわれない、収骨に来ないなどのトラブルも存在します。
また、感染症拡大の影響で、喪主が突然、発熱し、葬儀を延期した結果、用意した料理や生花が無駄になり、遺体の保管や火葬場のキャンセルに費用がかかるなどといったケースも出てきています。
このようなケースでの対応をどうするかについても、契約書に盛り込み、いざというときに困らないようにしておく必要があります。
契約書関係については以下の記事もご参照ください。
7,咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「契約書に強い弁護士への相談サービス」への今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回は、「葬儀会社からの依頼で葬儀に関する契約書をサポートした事例」について、ご紹介しました。
他にも、今回の事例に関連した契約書関係の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・スポーツ用品店の依頼を受け、プロスポーツ選手とのスポンサー契約書をサポートした事例
・職人への業務委託を準委任の形態で行う際の契約書をサポートした事例
・ECサイト運営会社の依頼を受けて、食料品の継続的売買契約についてリーガルチェックを行った事例
・リフォーム会社の依頼を受けて、特定商取引法、割賦販売法、改正民法等を反映したリフォーム工事契約書を作成した事例
・リゾート会員権販売事業に関して、特定商取引法の要件を満たす契約書を作成した事案
・派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックの依頼を受けた事例
・中国企業との化粧品販売に関し、売買基本契約書をサポートした事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






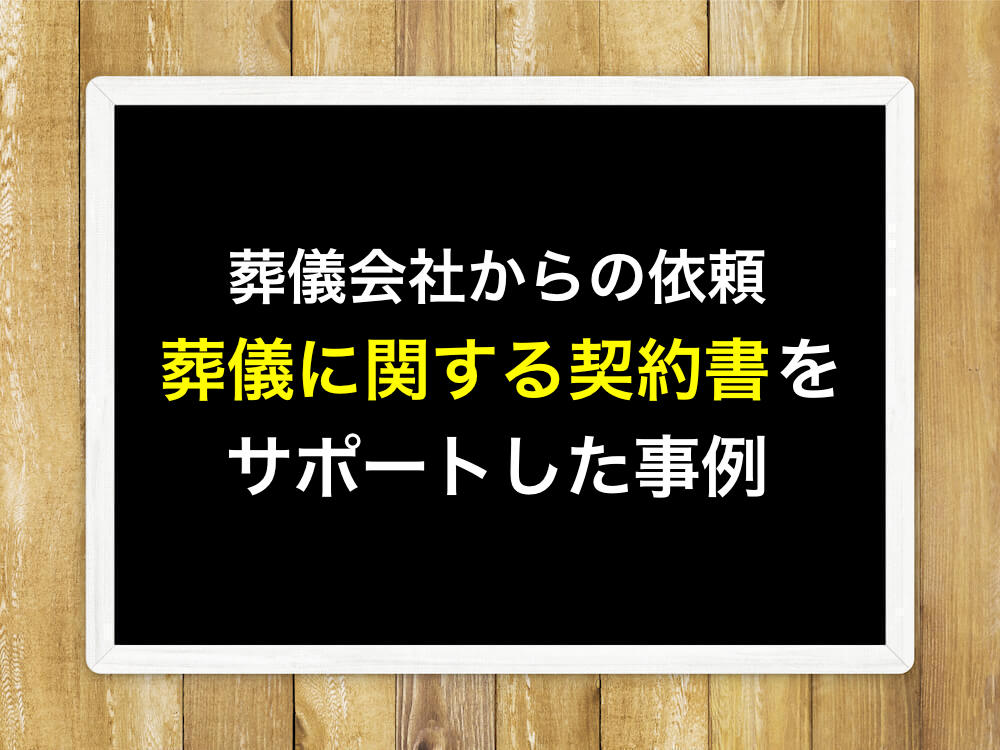

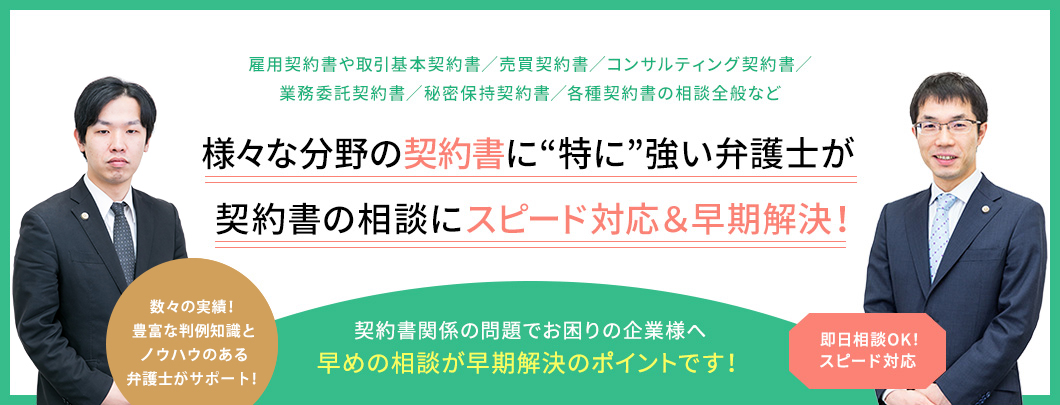
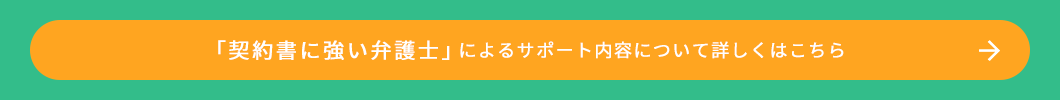
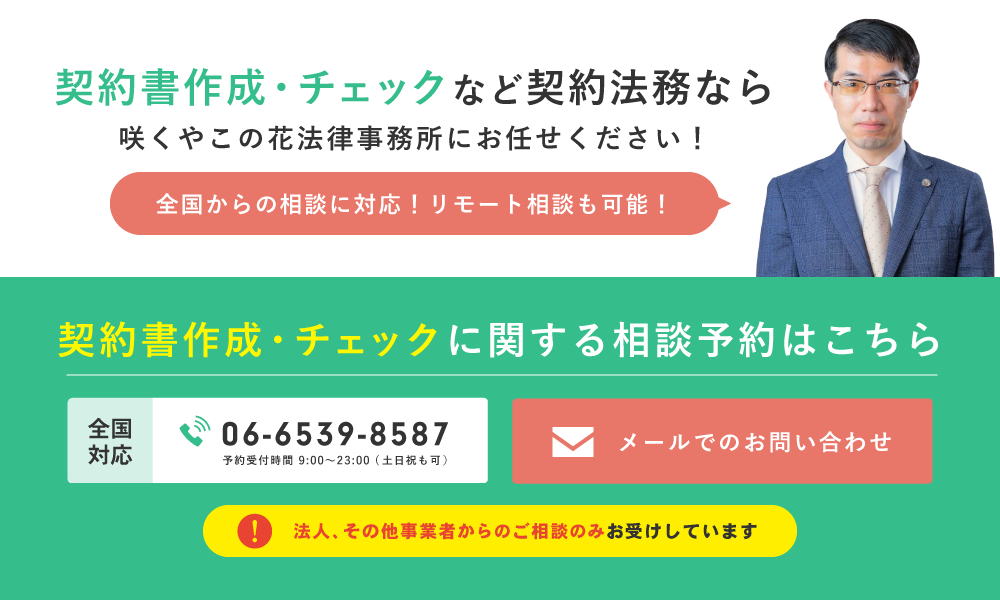
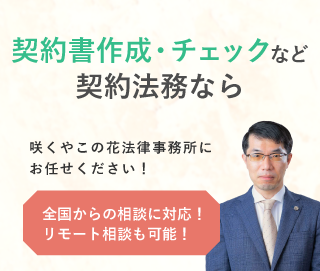





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















