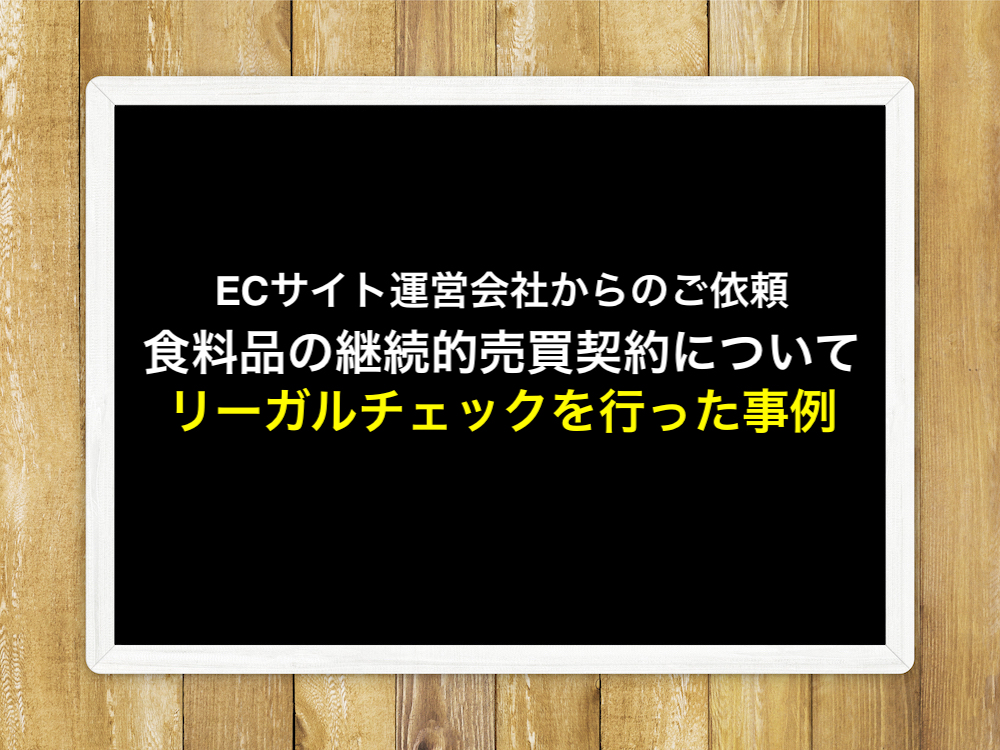
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕
出身地:兵庫県姫路市。出身大学:大阪府立大学総合科学部。主な取扱い分野は、「労務・労働事件(会社側)、保険業法関連、廃棄物処理法関連、契約書作成・レビュー、新商品の開発・新規ビジネスの立ち上げに関する法的助言、許認可手続における行政対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「ECサイト・ECモール運営会社」の事例です。
2,事案の概要
本件は、ECサイト運営会社から食料品の購入契約書のリーガルチェックを咲くやこの花法律事務所にご依頼いただいた案件です。
背景事情として、ご相談時、新型コロナウイルス感染拡大で食料品をオンラインで購入して宅配してもらう人が増えていました。来店での利用者が減少したので、従来オンラインでの宅配サービスを行っていなかった飲食店や生産者も導入を進めていました。
そして、オンラインで食料品を宅配してもらうという形態は、コロナウイルス感染終息後も続く可能性がありました。ECサイト・ECモールを運営する場合、飲食店や生産者との契約、利用者との利用規約の作成が必要です。
本件の相談者のビジネススキームは、以下のようなものでした。
- ●1,ECサイト運営会社が、飲食店・生産者から食料品を購入し、購入した食料品を利用者に販売する
- ●2,ECサイト運営会社が購入した食料品は飲食店・生産者が保管して、その発送は飲食店・生産者が宅配業者に依頼して行う
この場合、ECサイト運営会社は、生産者との関係で、食料品の購入に関する契約を締結する必要があります。
3,問題の解決結果
ご相談時、ECサイト運営会社が、飲食店・生産者との間の食料品の購入と発送に関する契約書の原案を作成していました。
そこで弁護士が依頼を受け、そのリーガルチェックをしました。
4,弁護士が取り組んだ課題
以下では、本件に関する弁護士が取り組んだ課題について解説いたします。
(1)食料品をオンライン宅配する場合の2つの方法
まず、食料品をオンライン販売して宅配するサービスを提供する場合、以下の2つの方法が考えられます。
1,サイト運営会社が生産者や飲食店から購入して自社の商品として販売する方法
今回の相談は、この方法でした。
この方法の場合、生産者や飲食店との間で食料品の継続的売買契約の締結が必要です。
2,生産者や飲食店がサイトを通して消費者に自社の商品として販売する方法
出前館、Uber Eatsは、この方法です。
この方法の場合、サイト運営会社は生産者や飲食店との間で、ウェブサイトへの出店に関するウェブサイト利用料その他の利用条件についての契約を締結する必要があります。
(2)今回の契約のリーガルチェックのポイント
今回の契約のリーガルチェックのポイントは、以下の通りでした。
- a:契約の当事者を明確にする
- b:売買契約の成立時期に注意する
- c:代金の支払時期・手続を明確にする
- d:表明保証条項では食料品であることの特殊性に配慮する
- e:商品の写真を加工する許可をもらう
5,担当弁護士の見解
ここからは、担当弁護士の見解についてご説明していきます。
ここでは、上記「a~e」のポイントごとに、弁護士の見解を説明していきます。
a:契約の当事者を明確にする
飲食店との契約で、契約書の当事者として店舗名が記載されていることがあります。
しかし、店舗名だけ記載しても、店長と契約したことになるのか、店長とは別にオーナーがいる場合、オーナーと契約したことになるか、店長やオーナーが交代した場合に契約がどうなるのかといったことがわからず、あいまいになります。
そして、契約の当事者があいまいであれば、契約違反があった場合にも、誰にも責任の負担を求めることができなくなるおそれがあります。そのため契約書の当事者は、店舗名ではなく、個人の場合は氏名、法人の場合は●●株式会社というような商号を記載するのが鉄則です。
ただし個人の場合、店舗名と個人をセットで記載しても構いません。例えば「店舗名」こと「氏名」というような記載です。
b:売買契約の成立時期に注意する
今回の契約は、ECサイト運営会社が飲食店や生産者から購入した食料品を消費者に販売するというビジネスモデルです。
生鮮食料品の場合、消費者との間で注文される前にサイト運営会社が生産者から食料品を購入してしまうと、賞味期限切れ等でロスが生じます。
そのため、サイト運営会社において在庫をかかえない運用にする必要があります。
具体的な運用の流れと留意点は以下のとおりです。
- ●1.まず消費者からECサイト運営会社にオンライン上で商品の注文がされます。この注文の段階では、消費者とECサイト運営会社との契約は成立していません。
- ●2.次にECサイト運営会社は、消費者から注文された商品について生産者や飲食店に購入の申込をします。購入の申込の際には、商品の発送時期についても明記します。
- ●3.生産者や飲食店から購入の申込を承諾するという連絡があった時点で、生産者や飲食店とECサイト運営会社との契約が成立します。生産者や飲食店から承諾の連絡がされた後、ECサイト運営会社は、消費者に対して注文の確定を連絡します。
- ●4,仮に、商品の在庫がない等の理由で生産者や飲食店から、食品の販売を断られた場合、ECサイト運営会社は消費者に対し注文に応じることができない旨の連絡をします。
販売ができるかどうかについての生産者や飲食店から連絡が遅れることも考えられますが、いつまでも消費者を待たせることはできません。
そこで契約書には、一定期間が経過しても、生産者や飲食店から回答がない場合、契約が成立しない旨の記載もあった方がいいです。
ECサイト運営会社と飲食店・生産者との間の契約書における具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が飲食店・生産者、乙がECサイト運営会社)。
第●条(売買の成立)
1 甲乙間の売買は、乙が甲に対し発送時期、価格等を指定して個別に注文を行い、甲がこれを承諾することにより成立します。
2 甲が前項の注文を受けてから1営業日以内に諾否の回答をしないときは、乙の注文はその効力を失います。
3 第1項により成立した売買契約(以下「個別契約」といいます。)については、特に定めのあるときを除き本契約の各条項を適用します。
c:代金の支払時期・手続を明確にする
代金の支払時期・手続がはっきりしない契約書も多いですが、代金の支払は契約書の最重要事項なので明確にしましょう。
当たり前のことのように思えますが、締め日や請求の期限等が明記されていない契約書が多いです。
具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が飲食店・生産者、乙がECサイト運営会社)。
第●条(代金の支払)
甲は、納品した本件商品の代金を毎月末日に締切り、当月分の代金支払総額を翌月15日までに乙に対して請求書を送付する方法で一括して乙に請求するものとします。当該甲の請求があった場合、乙は、当月分の代金支払総額を甲の締切日の翌月末日(乙の休業日の場合、翌営業日)までに甲の指定する銀行口座に振込送金する方法で支払うものとします。なお、振込手数料は乙が負担します。
d:表明保証条項では、食料品であることの特殊性に配慮する
表明保証条項とは、取引の対象となる商品について一定の性能や品質を保証するものです。
例えば、動産の売買では、第三者の知的財産権を侵害していないことや検査機関で一定の検査に合格したことなどについて売主が買主に対し保証する内容の契約条項を設け、保証に違反した場合、買主が被った損害を賠償するという内容となることが多いです。
食料品の場合、「腐ってしまう」、「不良があった場合に人の健康に影響する」という特徴があります。また、食料品の産地に偽装等があった場合には運営会社は消費者からの信用を失う危険があります。
表明保証条項を作成する場合もこのような食品の特殊性を考慮すべきです。
ECサイト運営会社と飲食店・生産者との間の契約書における具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が飲食店・生産者、乙がECサイト運営会社)。
第●条(品質保証)
甲は乙に対し、本件商品が鮮度良好であり、異物、異品種、夾雑物、虫等の付着又は混入がないこと、食品に対する法律及び諸規定が遵守していることを保証します。万一、当該保証に反し、第三者より乙に対して、何らの権利の主張または異議の申立て、損害賠償その他の請求がなされた場合、甲は自己の責任と負担をもってこれを解決し、その第三者または乙が被った一切の損害(乙が第三者に支払った慰謝料を含む賠償額、乙が本件商品を市場から回収するために要した費用、弁護士費用を含むがこれに限られない)を賠償するものとします。
e:商品の写真を加工する許可をもらう
インターネットで食品を販売するためには、美味しそうにみえる食品の写真をウェブサイトに掲載することが不可欠です。
写真を運営会社が撮影することも考えられますが、生産者や飲食店が撮影した食品の写真を提供してもらって、これをウェブサイトに掲載することが多いです。
生産者や飲食店が撮影した写真については、生産者や飲食店の著作物です。
そのため、契約書には、運営会社による写真の利用が無料で、また、運営会社において必要な加工をすることが許されることを、契約書に記載する必要があります。
具体的な条項例は、以下のとおりです(甲が飲食店・生産者、乙がECサイト運営会社)。
第●条(販売促進)
甲は、乙が要請した場合、乙が本件商品を販売促進のために必要な資料及び情報(本件商品の写真、カタログ、説明文章等の著作物、但し甲が権利者である情報に限る)を乙に提供しなければなりません。乙は当該資料及び情報を本件商品の販売促進のために無償で使用(乙または乙の指定する者のウェブサイトや文書に掲載することも含みますがこれに限られません)することができ、また掲載するための必要な改変を無償で行うことができます。
6,解決結果におけるまとめ
今回の契約は、法的には動産の継続的売買契約に分類することができますが、食料品であることの特殊性を考慮したリーガルチェックが必要です。
リーガルチェックのメリットは、「法的に問題のない契約書の作成」にとどまりません。第三者の視点を導入して、契約書を見直す過程で自社が提供するサービスが明確になるというメリットもあります。
リーガルチェックの過程で「サービス内容そのものが現実的か」、「契約相手方にとってわかりにくくないか」などを弁護士のサポートを受けながら、再検証することができるのです。
7,咲くやこの花法律事務所の契約書に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「契約書に強い弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】契約書テーマの関連した解決実績
今回は、「ECサイト運営会社の依頼を受けて、食料品の継続的売買契約についてリーガルチェックを行った事例」について、ご紹介しました。他にも、各種契約書や利用規約など、今回の事例に関連した解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・職人への業務委託を準委任の形態で行う際の契約書をサポートした事例
・勤怠管理ソフトウェアの利用規約の制定をサポートした事例
・リフォーム会社の依頼を受けて、特定商取引法、割賦販売法、改正民法等を反映したリフォーム工事契約書を作成した事例
・リゾート会員権販売事業に関して、特定商取引法の要件を満たす契約書を作成した事案
・業界新聞より依頼を受け、インターネット上で新聞記事を閲覧できるサービスの利用規約を作成した事例
・派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックの依頼を受けた事例
・モデルの動画への出演契約書をサポートした事例
・中国企業との化粧品販売に関し、売買基本契約書を作成した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






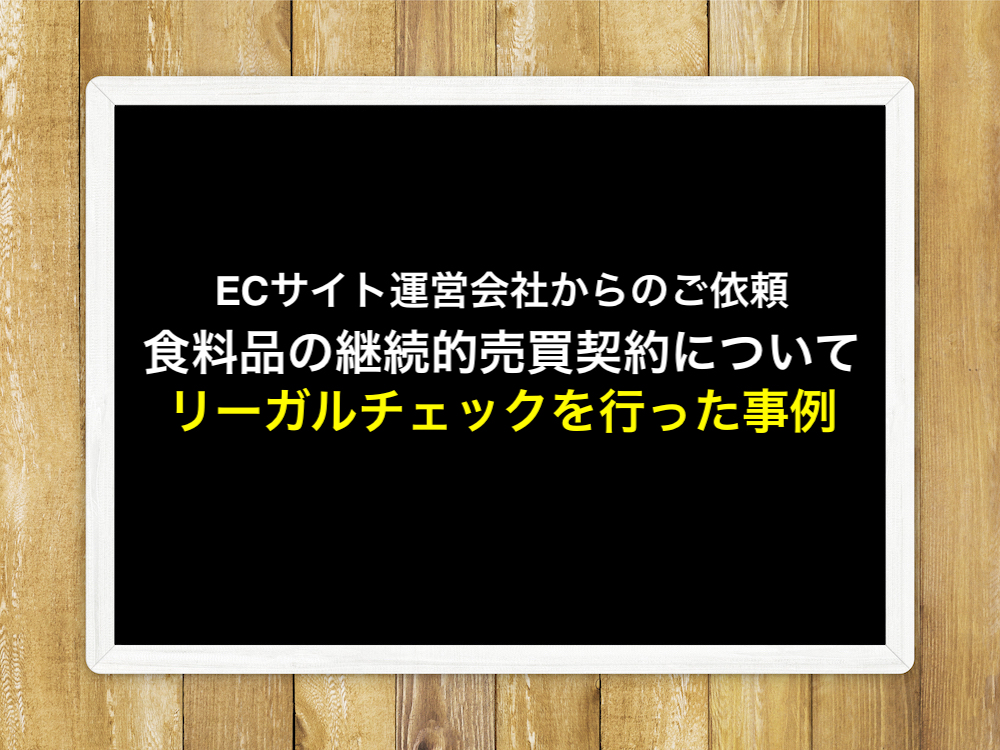

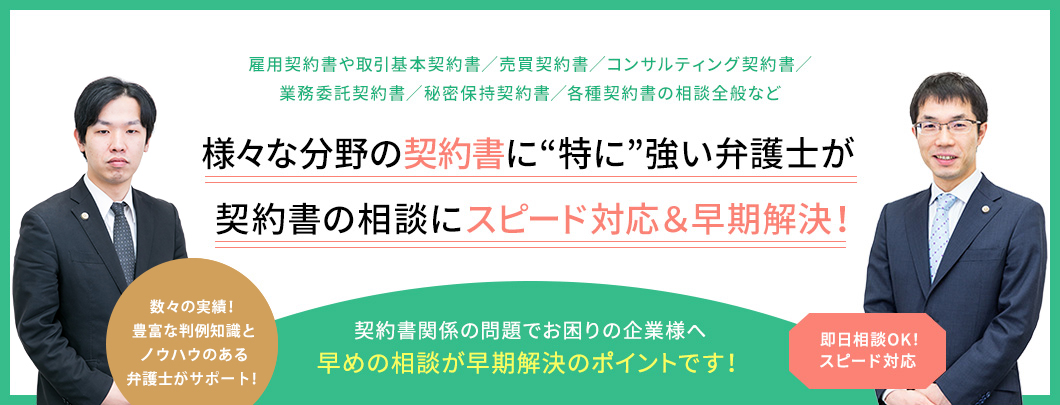
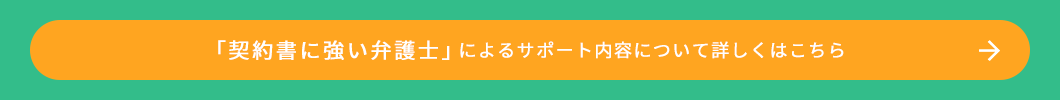
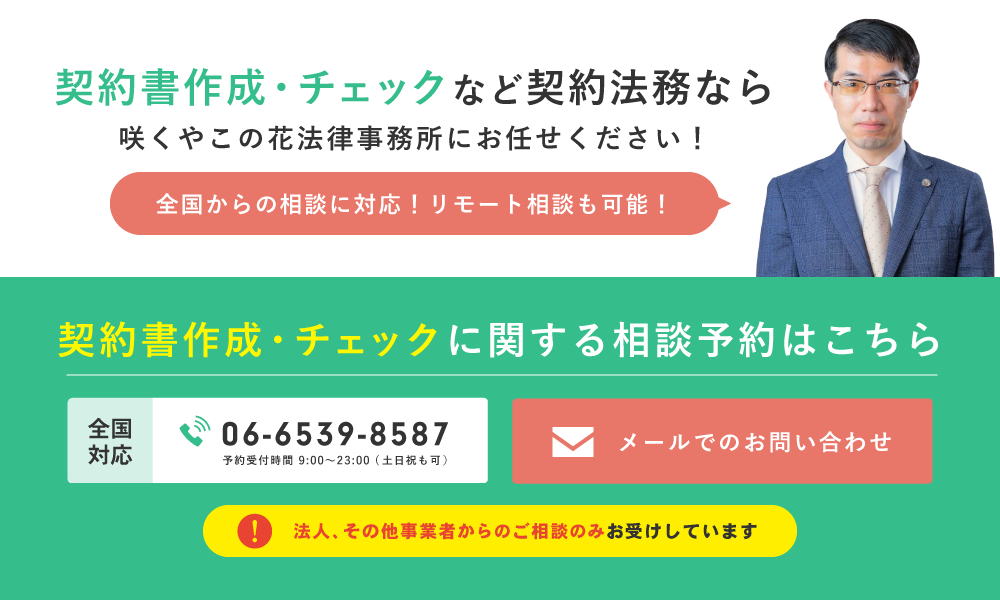
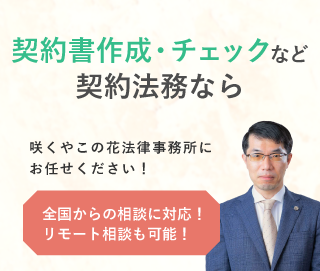





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















