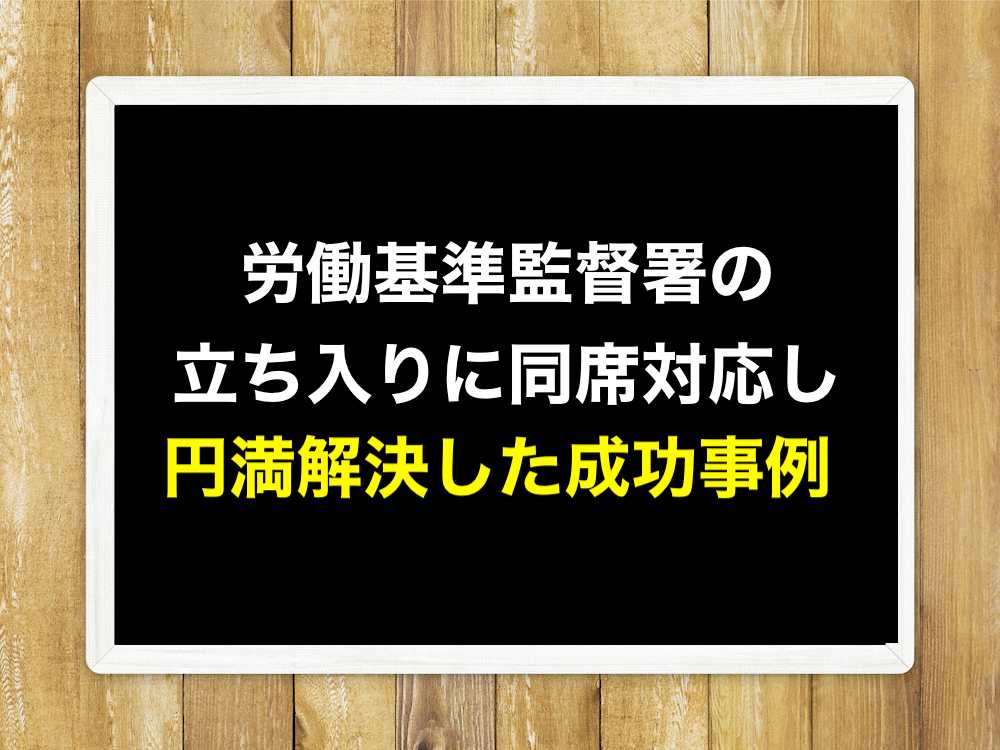
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 小田 学洋
出身地:広島県。出身大学:広島大学工学部工学研究科。主な取扱い分野は、「労務・労働関連(企業側)、債権回収、システム開発トラブル、運送業関連、フランチャイズ契約トラブル、顧客クレーム対応、インターネット上の誹謗中傷対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「菓子製造業」の事例です。
2,事案の概要
本件は、労働基準監督官の立ち入り調査に対して、弁護士が同席して対応した事案です。
労働基準監督官は、会社に対し、「労働基準法」その他労働関係の法律が遵守されているかどうかについて立ち入り調査を行う権限を有しています。
立ち入り調査の結果、違反していることが判明すれば行政指導を受けることになります。また、労働基準法の違反には、刑罰も規定されているため、違反が悪質とされれば刑事処分がされる可能性もあります。
本件では、労働基準監督官が抜き打ちで相談者の会社を訪問し、資料の提出や従業員へのインビューをなどの調査をすることを要求してきました。
会社は、訪問を受けた日がちょうど繁忙期で対応する時間がとれないことから、翌月に調査を延期してもらうことにしました。
その後、労働基準監督官の調査について全く知識がなかったため、その対応方法について咲くやこの花法律事務所に相談にこられ、調査への対応を弁護士に依頼されました。
3,問題の解決結果
ご相談後、弁護士が、労働基準監督署に電話して、立ち入り調査の日程の調整を行い、また、調査の日に準備しておくべき資料を労働基準監督官に確認しました。
そのうえで、弁護士が相談者にヒアリングをして、労働基準監督官から指摘されそうな会社の労務管理の問題点を調査し、かつ、問題点に対する改善策を決めました。
そして、立ち入り調査の当日は、弁護士が顧問弁護士として同席し、会社経営者と一緒に、労働基準監督官に対し、会社が認識している問題点と今後の改善方法を説明しました。その結果、労働基準監督官からは是正勧告と改善指導がされましたが、会社から説明した改善策を了解してもらうことができました。
また、会社が事前に弁護士に相談して改善策を自主的に検討していたことが評価され、当初予定されていた従業員へのインタビューも省略となり、1時間程度で調査はおわりました。
会社は厳しい処分を受けることなく、無事に調査に対する対応を終えることができました。
4,担当弁護士による対応
ここでは、担当弁護士が実際に行った対応について解説いたします。
(1)まず弁護士から労働基準監督署に問い合わせをして調査内容を把握する
労働基準監督官の調査は、「定期監督」と「申告監督」があります。
- ●「定期監督」=労働基準監督官が担当地域内の会社から調査対象を抽出して行う調査
- ●「申告監督」=従業員からのタレコミなどにより労働法違反の情報を入手したことをきっかけとして行う調査
本件では、相談にこられたときは、会社は労働基準監督官の調査が、どちらによるものか把握していませんでした。
そこで、まずは、弁護士から労働基準監督署に連絡して、弁護士が調査に同席することを伝え、調査日程を調整するとともに、調査の目的と、準備する資料や調査の内容について確認しました。
その結果、今回の調査は、労働基準監督官が調査対象会社を抽出して行う定期監督であり、労働法違反の情報を入手したことに基づく調査ではありませんでした。
このような定期監督の目的は、会社の労働法の遵守状況を調査する点にあります。
定期監督では、労働基準監督官が、タイムカードと賃金台帳、健康診断の記録、労働基準監督署にこれまでに提出済みの労使協定、就業規則等を確認し、あわせて、従業員数名へのインタビューも行って、会社の法令順守状況を調査することが通常です。
本件でも、従業員へのインタビュー調査を予定しており、インタビューする従業員は当日資料を見て、労働基準監督官が指定するということでした。
そこで、弁護士から、会社に、まずは、当日労働基準監督官が確認するであろうタイムカードや賃金台帳の資料などを準備しておくように依頼しました。
(2)弁護士が事前に会社の労働法順守状況を調査して対策を立てる
労働基準監督署の調査をスムーズに終わらせるために、調査に先回りして、自主的に労働関係法令に違反していないかどうかの検討をしておき、違反している点については解消するための対策も決めておくことが重要です。
このような事前準備を行うことで、立ち入りの時に会社側に自主的な改善意思があることを監督官に説明して、信頼を得ることができます。
本件では、会社の労働関係法令の遵守状況を弁護士が確認すると、以下の問題点が判明しました。
- 1,従業員を残業させるために必要な「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36協定」)を締結していなかった
- 2,10名以上の従業員がいるのに就業規則を作成していなかった
- 3,残業時間の計算方法に不適切な取り扱いがあった
- 4,一部の職種に関し労働時間の把握が不十分で、未払い残業代が発生していた。
- 5,一部の職種において月100時間を超える長時間の残業が生じていた。
これらの点については、労働基準監督官から指摘を受けることは確実でした。
また、36協定を締結せずに残業をさせることや、残業代の不払いについては、法律上刑事罰が科されることもありうる違反でした。そこで、これらの点について、弁護士が会社と相談して、改善策を事前に決め、労働基準監督官に当日説明することにしました。
1,36協定が締結されていなかった点について
会社ではほとんどの従業員が残業を行っている現状がありました。
会社が従業員に残業をさせる場合、従業員の過半数代表(または労働組合)との間で、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
しかし、本件では、会社は36協定の締結と届出をしたことがありませんでした。その原因は、会社に労働法に関する知識が不足していたことにありました。
違反状態の解消には36協定を締結したうえで労働基準監督署に届け出ることが必要でした。
しかし、36協定の締結のためには過半数代表の選出の手続きなどが必要であり、立ち入り調査の日までに36協定を締結して届出を済ませることは困難でした。
そのため、立ち入り調査日には、労働基準監督官に対して、会社として36協定の不備を率直に認め、すでに違反状態を解消するために36協定の締結の準備を進めていることを、弁護士から説明することで理解を得る方針をとりました。
2,就業規則の不備について
従業員10名以上の会社には就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
しかし、相談者の会社はこの点も対応できておらず、法律違反となっていました。
この点についても就業規則を作成して届け出ること以外に違反状態を解消する方法はありません。そこで、労働基準監督官には、会社として就業規則の作成・届出の義務があることは認識しており、手続きを進めていることを説明することにしました。
3,残業代の支払い方法の問題について
パートタイマーの残業代の支払いについて、タイムカードから計算される労働時間のうち、30分未満はすべて切り捨てで計算していました。
この点について、立ち入り調査で、計算方法が不適切であるとの指摘を受けることが明らかでした。厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)によれば、1か月の時間外労働の合計時間数に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、30分以上の場合は切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく事務簡便を目的としたもの認められるとされています。
本件では、賃金を30分単位で計算していたことから、今後は、15分を下回る端数は切り下げ、15分を上回る部分は切り上げて計算することとしました。
4,労働時間の把握が不十分である点について
会社には従業員の労働時間をタイムカードなどで把握する義務があります。
相談者の会社はタイムカードを準備していましたが、製造職の従業員は、タイムカードを打刻していないか、あるいは出社した時だけ打刻して、退社の時には打刻していない者が大半でした。
そのため正確な労働時間が把握できていませんでした。
タイムカードが打刻されていなかったのは、会社が製造職の社員に対し、基本給に残業代が含まれているため残業代はつかないという説明をしていたためでした。正確な労働時間はわかりませんが、定時後も働いている社員がほとんどであり、残業が発生していることは確実でした。
残業のルールは労働基準法の中でも重要なルールの1つであり、労働時間の把握不備について、労働基準監督官から指摘されることは確実でした。
そこで、今後はタイムカードの打刻をきちんと行うよう社員に徹底すること、過去の残業については、一定の一時金をだすことで清算することを社員に説明し、全員の同意書を作成することにしました。
そのうえで、立入り調査の当日は、タイムカードを示して労働時間把握ができていなかった状況を説明し、労働時間把握状況は現在は改善されていること、過去分の未払い残業代についても全員に説明して精算することを予定していることの説明を行いました。
その結果、労働基準監督官からは、労働時間把握については改善済みであると判断してもらい、また、未払いの残業代については正確な金額が計算できないので精算方法については会社に任せるということになりました。
5,長時間労働になっていた点について
製造職の社員は、繁忙期には遅くまで働いている者も多く、月100時間近い長時間残業をしている可能性がありました。
そこで、立ち入り調査の当日は、過重労働対策として、今後、タイムカードの打刻の徹底により、労働時間に注意し、実際の労働時間を把握していくことを監督官に説明しました。
また、ちょうど製造現場への機械の導入を進めていたため、これにより、従来に比べ労働時間の短縮がなされる見込みであることを、労働基準監督官に対して説明しました。
労働基準監督官からは、長時間労働に対しては「労働安全衛生法」に定められた医師による面接指導をうけさせるようにとの指導がされました。
6,固定残業手当の制度を利用して残業代の不払いを是正
また、会社が行っていた残業代を基本給に含めて支払う扱いは、判例上、残業代の適法な支払方法とは認められていません。
このような支払い方法を続けていると、将来、未払い残業代があるとして紛争になる可能性があるので、弁護士の提案により、基本給とは別に固定残業手当を支給する扱いに変更しました。
この点については調査終了後に、会社が個別に従業員と面談し、給与の支払費目を変更することについて同意書を取得しました。
7,弁護士が労働基準監督官に会社の対応を説明した
調査日には、弁護士が、顧問弁護士として、労働基準監督官による調査に、会社側の立場で同席しました。
そして、弁護士から、前記のとおり会社について労働関連法規の違反があるものの、その対策は順次とっているところであることを説明しました。
その結果、労働基準監督官は会社が法令遵守のために努力していることを認めて、予定されていた従業員へのインタビュー調査を省略しました。
労働基準監督署は、会社から提示した対策をとるように是正命令および指導をすることで、調査を終了しました。その後、会社としても、実際に対策を完了し、労働基準監督官に報告し、円満に対応を完了させることができました。
5,解決結果におけるまとめ
労働基準監督署の調査は、対応を誤ると、未払い残業代について多額の支払いを求められるなど、会社として大きな負担を強いられるケースもあります。
事前に弁護士に相談し労働基準監督官から指摘される前に会社から先回りして改善案を提示していくことや、調査に弁護士が同席し弁護士から改善案を提示することで監督官の信頼を得ることが、調査への対応を円滑に終了させるポイントです。
労働基準監督署からの調査への対応については、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。
6,咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「労働問題に関する弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 06-6539-8587
06-6539-8587






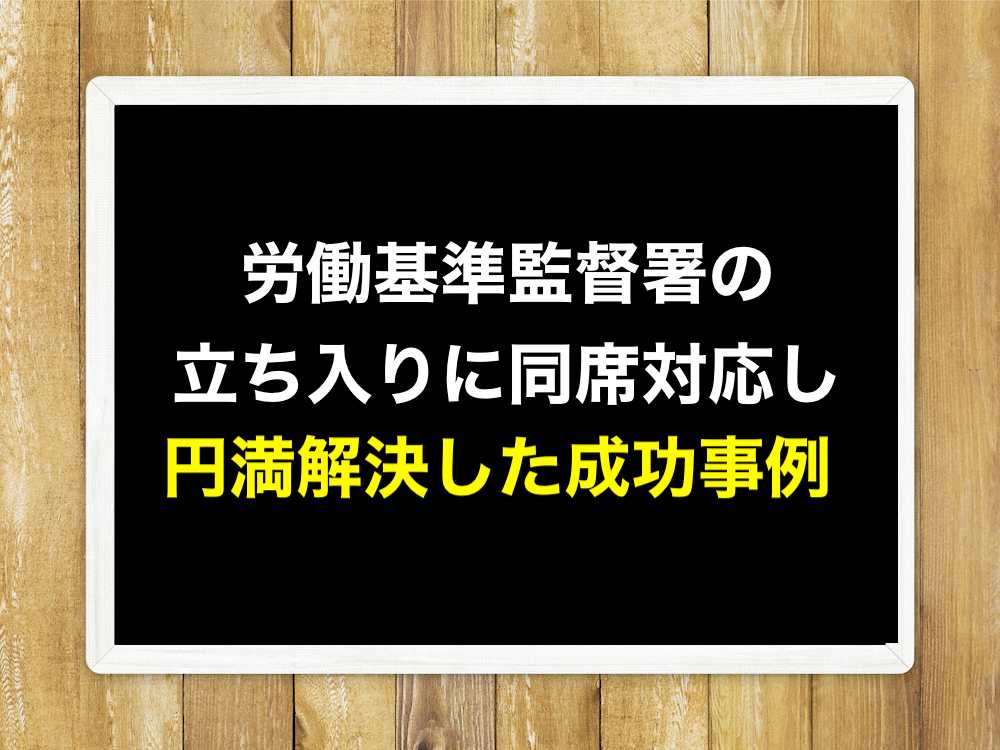

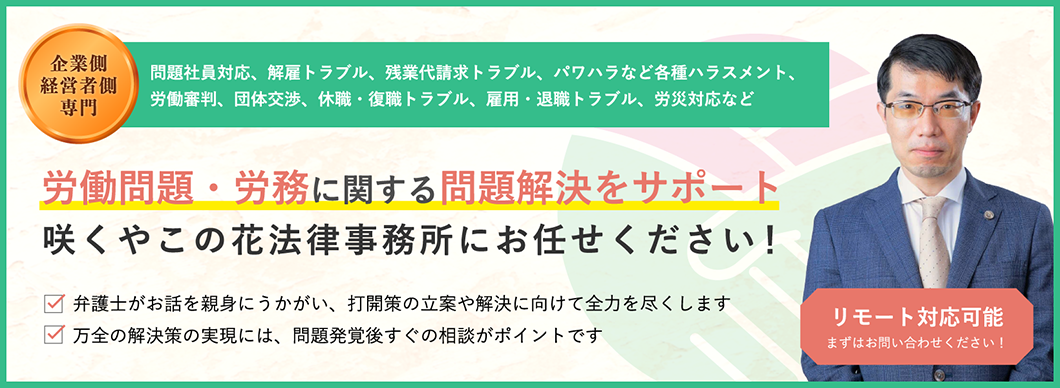
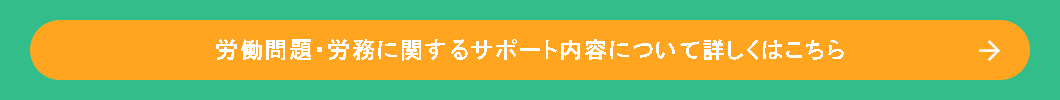
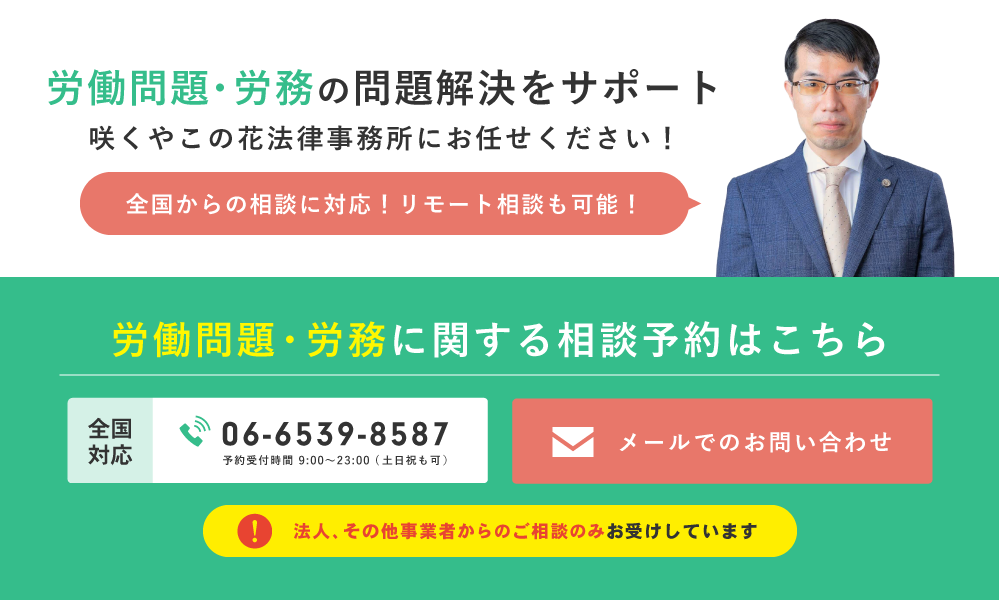
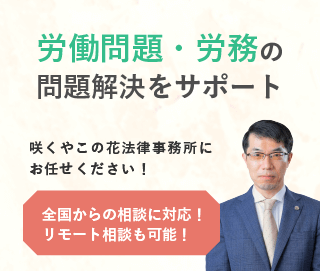





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















