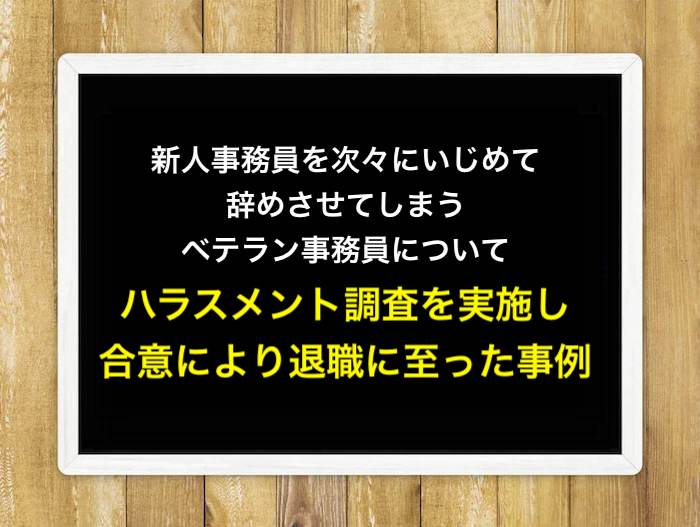
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 木澤 愛子
出身地:神奈川県横浜市。出身大学:慶應義塾大学法学部法律学科。主な取扱分野は、人事・労務に関する相談、紛争一般(使用者側)のほか、賃貸借等不動産関連、クレーム対応、債権回収、その他企業法務一般です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種の紹介
「クリニック」の事例です。
2,事件の概要
この事案は関東地方にあるクリニックから、新人事務員をいじめて辞めさせてしまうベテラン事務員への対応についてご相談いただいた事案です。
このクリニックでは、クリニックの開業から約1年後に入職し、以後10年以上勤務しているベテランの受付事務員がいました。このベテラン事務員が、新人事務員に対して、指導の際にきつい言い方をしたり、明らかに他の事務員に対するのとは異なる冷たい態度で接したりするなど、辛くあたることを繰り返すため、新人事務員が2年連続で退職してしまいました。
クリニックは新人事務員が2年連続で退職した後、事務員が足りなくなったため、派遣会社に事務員を派遣してもらい、その後、直接雇用することにしました。しかし、今度はこの新人事務員がターゲットにされてしまい、新人事務員から、ベテランの事務員が怖く、一緒に働くことが辛いという申出がありました。
また、ベテランの事務員が新人事務員にひどい態度で接する場面を見て、その場にいた別の事務員が体調不良を訴えて勤務を休んだり、他の事務員たちが次は自分がターゲットにされるのではないかと恐れ、職場全体の雰囲気が悪化しているという問題もありました。
クリニックとしてこのベテランの事務員の問題に適切に対処できなければ、真面目に頑張ってくれている他の事務員や職員からの信頼を失ってしまうおそれもありました。これらの経緯から、クリニックとしては、このベテランの事務員を何とかして円満に退職させたいと考え、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
3,問題の解決結果
咲くやこの花法律事務所でご相談をお受けし、弁護士が院長に問題のベテラン事務員に対する対応をサポートしました。その結果、最初のご相談から約3週間後に対象の問題のベテラン事務員から退職届が提出され、問題を解決することができました。
以下では、解決のポイントと弁護士が行ったサポート内容について紹介します。
4,問題解決におけるポイント
以下では、本件で問題となったベテランの事務員を「ベテラン事務員」と呼んでご説明します。また、ベテラン事務員のハラスメントのターゲットとされて、最初に退職してしまった新人の事務員を「新人事務員A」、新人の事務員Aの退職後に、ベテラン事務員のターゲットとなり、新人の事務員Aに続いて退職してしまった新人の事務員を「新人事務員B」と呼んでご説明します。また、新人事務員Bの退職により、補充のために派遣会社から派遣され、その後直接雇用となった在職中の新人事務員を「新人事務員C」と呼んでご説明します。
(1)解雇ではなく退職勧奨による解決を目指す
弁護士がクリニックからの相談をお聞きしたところ、院長のおっしゃるとおり、ベテラン事務員は、新人事務員AとBを立て続けに退職に追い込んだ可能性がありました。しかし、一般に、暴力を伴わないハラスメントについて解雇により対応しようとすると、解雇が訴訟トラブルになれば、十分な指導や懲戒による警告をせずに解雇したとして、不当解雇と判断されてしまう例も多いです。
本件では、ベテラン事務員に対して、指導や懲戒がされていたとは言い難い状況でした。そのため、解雇ではなく、退職勧奨によって合意による解決をする必要がありました。
(2)ハラスメント調査を行い、退職勧奨が受け入れられる土壌を作る
院長によると、新人事務員Aが退職してしまったときに、院長がベテラン事務員と話をし、その際にベテラン事務員は「自分のせいで周りに迷惑をかけてしまったので、退職した方が良いと思っている」と話していたという経緯がありました。
院長は、このとき、ベテラン事務員に「退職の方向で進めていきましょう」と回答しました。
しかし、ベテラン事務員は、院長から引き留めてもらえることを期待していたのか、院長が退職に同意すると、一転して、「もう一度チャンスが欲しい」と言い、退職を拒否しました。また、院長が、「頭を冷やすために一週間くらい休むのはどうですか」と提案すると、ベテラン事務員は、「なぜ私が休むのかわかりません」と答え、勤務を休むことも拒否しました。さらに、別の機会に、院長が、ベテラン事務員に対して「新人事務員Aさんの退職について、自分にも問題があったと思うところはないですか」と質問したこともありました。しかし、ベテラン事務員は、これに対し、「何もありません」と答えました。
また、その後の新人事務員Bの退職についても、ベテラン事務員は、自分の問題点を全く認めていませんでした。むしろ、ベテラン事務員は、新人事務員AとBについて、「私は親切に指導してあげたのに」と主張していました。つまり、ベテラン事務員は、自分の言動に問題があり、そのために新人事務員2名が退職してしまったということを認識できていませんでした。
退職勧奨は、使用者が労働者に対して退職に向けた提案や説得を行い、合意により雇用契約を終了することを目指します。労働者との合意が必要になるため、労働者自身が退職に向けた説得を受けるに至った経緯を理解できていなければ、なかなか退職勧奨による解決はできません。
本件のベテラン事務員のような「自分は新人事務員らに親切に指導をしてあげた」、「新人事務員の退職について自分に問題はない」という心の状態のままで退職勧奨を行っても、退職合意が成立する可能性はとても低いものになります。ベテラン事務員は、なぜ自分がクリニックから退職して欲しいと言われなければいけないのか、なぜ自分がクリニックを辞めなければいけないのかが理解できていないからです。
合意による解決を実現するためには、まず、ハラスメント調査を実施し、ベテラン事務員に、自分の新人事務員らに対する言動に問題があったことをはっきりと理解させたうえで、退職勧奨をする必要がありました。
(3)ヒアリング対象者の不安に対応し、充実した調査を実現する
ベテラン事務員に、自分の言動に問題があったことを理解してもらうためには、ベテラン事務員が、新人事務員らに対して、具体的に、いつ、どのような場面で、どのような言動を行い、それが新人事務員らの就労環境にどのような支障を生じさせたのかを明らかにしなければいけません。
そのためには、直接の被害者である新人事務員らから当時の詳しい事情を聞く必要がありました。しかし、新人事務員AやBは、既にクリニックを退職していました。そして、退職後もベテラン事務員に対する恐怖心が強く、ハラスメント調査に協力してもらうことは困難なことが予想されました。
そうすると、現在の直接の被害者である新人事務員Cからの聞き取りに加えて、新人事務員A、Bが被害を受けていた当時からクリニックに在籍し、ベテラン事務員の新人事務員らに対する言動を見ていた他の事務員たちからの詳細な聞き取りが必要不可欠でした。
そして、これらの事務員の中には、新人事務員A、Bがクリニックに在籍していた当時、新人事務員A、Bから「ベテラン事務員の自分に対する態度がひどく、ベテラン事務員と一緒に働くことが辛い」という相談を受けて、院長に報告していた事務員もいました。
しかし、報告を受けて院長が事務員たちに聞き取りを行った際、ベテラン事務員は、聞き取りに協力した事務員を個別に呼び出して、何を話したのかを問い詰めたり、何十通もの長文のLINEを送信して、クリニックから何を聞かれて何を話したのかを聞き出そうとしたりする行動をとっていました。
このため、他の事務員たちは、ハラスメント調査に協力することで、ベテラン事務員から報復を受けるのではないか、また、自分がベテラン事務員のターゲットにされるのではないかということをとても恐れていました。
これらの事情から、クリニックは、新人事務員C、そして、他の事務員たちを心理的にフォローし、事務員たちの信頼を得て、調査への協力を取り付け、充実したハラスメント調査を実現する必要がありました。そのうえで、ベテラン事務員に自分の言動の問題を理解させ、クリニックから、ベテラン事務員のこれまでの貢献なども考慮した退職条件を提案し、退職に合意してもらうことを目指す方針をとりました。
5,担当弁護士の見解
担当した弁護士の見解は、以下のとおりです。
(1)ハラスメント調査の支援
ハラスメント調査の実施にあたり、退職した新人事務員AとBに連絡を取り、調査に協力して欲しいと依頼しました。しかし、新人事務員Aはベテランの事務員の名前を聞くことも嫌な様子でベテラン事務員のことがトラウマになっており、関わりたくないとして協力を断られてしまいました。また、新人事務員Bからもやはり協力を断られてしまいました。
そこで、クリニックは、現在、ベテラン事務員の被害を受けている新人事務員Cと他の事務員たち3名の全員に聞き取りを行い、関連する証拠を提出してもらい、その内容を精査する必要がありました。前述のとおり、新人事務員Cと他の事務員たちは、調査に協力することで報復を受けることを恐れていました。
例えば、エピソードの内容から、その場にいたのが被害を受けている新人事務員の他には自分だけであるため、自分が伝えたことがわかってしまうような情報の提供を躊躇していました。そこで、弁護士が、新人事務員Cや他の事務員たちから信頼を得て、調査に協力してもらうための対応方法をアドバイスしました。
本件の被害者は、現在、直接の被害を受けている新人事務員Cだけではありませんでした。他の事務員たちも、ベテラン事務員が新人事務員に対して他の事務員や患者さんのいる前で高圧的な指導や叱責を行うために、辛い思いをしたり、ベテラン事務員の言動について院長に相談や報告をすれば執拗に問いただされたりするなど、皆が精神的に疲弊してしまうような環境で働くことを余儀なくされている被害者でした。
そのため、クリニックとして皆が安心して働くことができる職場環境を提供するために、ベテラン事務員の問題について真剣に取り組むこと、皆が調査に協力してくれることがベテランの事務員の退職に繋がること、ベテラン事務員から報復があった場合にはそれも全て報告して欲しいことを丁寧に説明し、信頼してもらいました。
その結果、他の事務員たちの全員が調査に協力し、ベテラン事務員の言動に関する具体的なエピソードを提供してくれました。他の事務員たちや一部の看護師への聞き取り調査により、例えば、以下のような問題が明らかになりました。
- ●ベテラン事務員が新人事務員に対して処方箋を渡すときに投げるように渡していたこと
- ●受付で新人事務員が一人だけの勤務になってしまう日にパートの他の事務員が出勤を申し出たにもかかわらず、ベテラン事務員が「出勤しなくていい」と伝え、故意に新人事務員を一人だけで勤務させたこと
- ●別の日にも新人事務員に一人だけで勤務をさせるためにベテラン事務員が体調不良を装って欠勤したこと
- ●ベテラン事務員が、他の事務員に対し、新人事務員について「何度言ってもわからない、だってバカなんだもん」、「あのバカいつ辞めるの?」と言っていたこと
- ●ベテラン事務員が、新人事務員から「何かお手伝いすることありますか」と声をかけられても何も返事をせず無視していたこと
- ●ベテラン事務員が、実際には自分のミスであったにもかかわらず、新人事務員のミスであると決めつけ、多数の患者さんがいる前で、新人事務員に厳しく叱責したこと
また、新人事務員は、ベテラン事務員から理由もなく強い口調で怒られるため萎縮していること、ベテラン事務員に話しかけても無視されたり、患者さんがいる前で自分のミスではないことについて叱責されることで精神的に苦痛を感じていること、新人事務員がベテラン事務員に患者さんの診察券を渡す際、ベテラン事務員が汚いものを受け取るかのように人差し指と親指で診察券の端を摘まんで受け取るなどしたため深く傷ついたことなども明らかになりました。
(2)ベテラン事務員に対する対応の支援
本件ではベテラン事務員に対する退職勧奨に先行して、ハラスメント調査を行うことにしましたが、調査には一定の時間がかかります。院長は、調査期間中に新人事務員Cが耐えきれずに辞めてしまうことも心配しておられました。そこで、弁護士はそれまでのベテラン事務員に対する対応についてもクリニックに助言しました。
ハラスメント調査は、事実関係を正確に確認したうえで、被害者に対する配慮、行為者に対する適正な措置を行い、再発防止に向けた措置をとることを目的に行うものです。加えて本件では、前述したとおり、ハラスメント調査を通じて、ベテラン事務員に自分がなぜクリニックから退職勧奨の提案を受けなければいけないのかを理解させ、退職勧奨を受け入れるような心の状態をつくることも必要でした。
これらの観点から、院長にはベテラン事務員と面談してもらい、以下のことを伝えてもらいました。
- ●新人事務員Cは、ベテラン事務員と一緒に働くことが怖いと感じていること
- ●複数の職員からベテラン事務員の勤務態度に問題がある旨の報告を受けていること
- 新人事務員A、Bに続いて、新人事務員とのトラブルが今回で3回目であり、クリニックとしてこの問題を重く受け止めていること
- ●そのため、これまでの新人事務員A、Bの件を含めてハラスメント調査を実施すること
- ●当面の間、新人事務員Cとベテラン事務員との勤務を分離すること
ベテラン事務員は、クリニックが開業して約1年が経った頃から継続して勤務しており、仕事熱心で真面目に仕事をし、事務員の人数が少なく大変だったときもクリニックを支えてくれた経緯がありました。そのため、クリニックは、これまでこのベテラン事務員を優遇してきた側面がありました。そのようなこともあって、ベテラン事務員が新人事務員らとトラブルを起こしたときも、ベテラン事務員に責任があることを明確に指摘したり、ベテラン事務員に遠慮のない指導をすることができていませんでした。
このようなこともあってか、ベテラン事務員は、院長は自分の味方でいてくれていると思っていたようでした。しかし、今回、院長が、ベテラン事務員に対して明確な態度をとり、ハラスメント調査を実施すること、新人事務員Cと一緒に勤務をさせないことを宣言したことで、ベテラン事務員は、これまでとは状況が違うということを理解したようでした。
(3)ベテラン事務員からの退職届提出に対する対応の支援
事業者から問題社員の退職勧奨のご相談を受けて弁護士が支援を始めると、相手はこれまでとは状況が違うことを察知して、弁護士が退職勧奨を行う前に、突然退職届を出してくることがあります。退職届は、通常は合意退職の申込と評価され、使用者が退職を承諾することにより、退職の合意が成立し、その後は労働者は退職を撤回できなくなります。
本件でも院長が弁護士の支援を受けて、ハラスメント調査の実施を決定し、ベテラン事務員と面談してその旨を伝えるとともに、新人事務員と勤務を分離してベテラン事務員の勤務を制限することとしたため、ベテラン事務員は、クリニックからこれまでとは違う対応をされている状況でした。
院長は新人事務員とベテラン事務員の勤務を午前と午後にわけて、2人を分離しました。このような経緯から、弁護士は、ベテラン事務員から突然退職届が提出される可能性があると考え、その場合に備えて、あらかじめ退職承諾書を作成し、クリニックからいつでも交付できるように準備しておきました。
本件では、最初のご相談から約3週間が経過し、直接の被害者である新人事務員C、他の事務員たち、さらに一部の看護師たちへの聞き取り調査などが一通り終わった頃、ベテラン事務員は退職届を提出してきました。ベテラン事務員は、残っている有休を消化し、夏の賞与を受け取った後に退職したい旨話し、約2か月後を退職日とする退職届を提出しました。
また、ベテラン事務員は、退職金の有無と金額について質問しました。クリニックは、まず、約2か月後を退職日とするベテラン事務員の退職を承諾し、あらかじめ準備していた退職承諾書を交付して、退職の合意を確定させました。これは後でベテラン事務員の気が変わって退職を撤回されるということがないようにするためです。そのうえで、ベテラン事務員のこれまでの貢献や、過去の事務員への退職金の支給実績を考慮して、退職金を提案しました。ベテラン事務員は退職金について了承し、その後、最終勤務日まで揉めることなく勤務し、賞与と退職金を受け取り、円満に退職しました。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、ハラスメント調査の結果を踏まえて、弁護士がクリニックを訪問して、ベテラン事務員に退職勧奨を行うことを予定していました。しかし、その前に退職届が提出され、早期解決が実現しました。
以前は退職を拒否していたベテラン事務員が退職届を自ら提出するに至ったのは、院長がベテラン事務員の問題について逃げずに本気で取り組むことを決意し、実践したことにあると考えられます。院長は、遠方にもかかわらず、咲くやこの花法律事務所の「YouTubeチャンネルの動画」の解説を見て、困難な状況だけれども、何とか力を貸して欲しいということでお問い合わせいただきました。そして、弁護士と打ち合わせの結果、退職勧奨に先行してハラスメント調査を実施することを決め、日々の業務に対応しながら、他の事務員たちに協力を求め、必死に証拠を収集し、協力してくれる職員全員に対して聞き取り調査を行いました。
ベテラン事務員からの反発や他の事務員たちへのフォローなど一人だけでは難しい対応も、弁護士のアドバイスを信じて、決めたことを全て実践してくださいました。そのようにして対応を進めるなかで、ベテラン事務員は、院長が過去のトラブルの件も含めて他の事務員たち全員に対して聞き取り調査を実施していること、自分の新人事務員に対する言動の詳細が確認され、他の事務員たちが自分の新人事務員に対する言動が問題であると認識していること、自分にはクリニックに居場所がなく、勤務を継続することは困難であることを理解しました。その結果、退職届の提出につながり、問題を円満解決することができました。
本件のような暴力を伴わないハラスメントについて解雇により対応しようとすると、十分な指導や懲戒による警告をせずに解雇したとして、不当解雇と判断されてしまう可能性が高いです。そのため、退職勧奨によって合意による解決をすることが必要ですが、加害者となっている従業員が自身の言動の問題点を理解していない段階で退職勧奨をしても、合意に至らない可能性が高いです。
合意による解決を実現するためには、弁護士のサポートを受けながらハラスメント調査を実施し、事業者として加害者の言動が受け入れられないことを加害者にはっきりと認識させたうえで退職勧奨を行うことが必要です。また、そのような過程で、被害者が萎縮して調査に協力してくれないといった問題や、調査期間中に加害者にどのように対応するかといった様々な問題が出てきます。
しかし、弁護士のサポートを受けて正しい方法で1つ1つ対応すれば、問題を解決することは可能です。咲くやこの花法律事務所では、ハラスメントの調査や、加害者の退職勧奨について、事業者側の立場でご相談をお受けしていますので、お困りの際は咲くやこの花法律事務所までお問い合わせください。
7,咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する弁護士への相談サービスへの問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回の解決事例は、「新人事務員を次々にいじめて辞めさせてしまうベテラン事務員について、ハラスメント調査を実施し、合意により退職に至った事例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した問題社員トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・歯科医院で勤務態度が著しく不良な問題職員の指導をサポートした事例
・やる気のないベテラン社員の指導を弁護士がサポートして解決に至った事例
・パワハラを繰り返す社員を解雇したところ、不当解雇であると主張されたが、弁護士が交渉して退職合意をし、訴訟回避した事例
・業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例
・社内で暴力をふるう社員について弁護士が調査して暴力行為を認定して退職させた解決事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






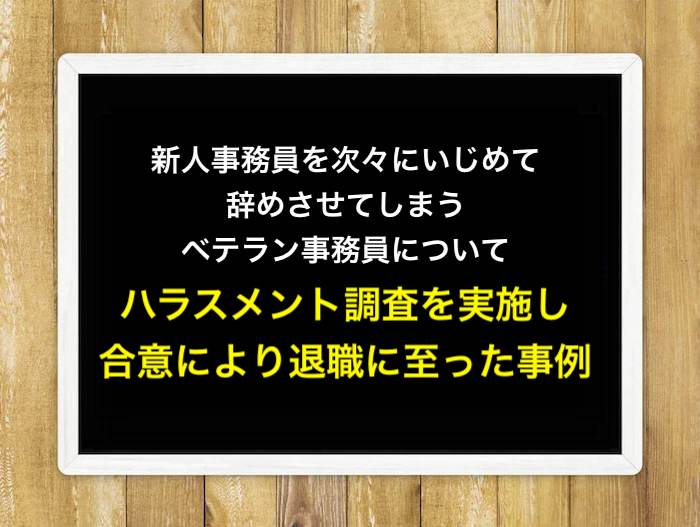

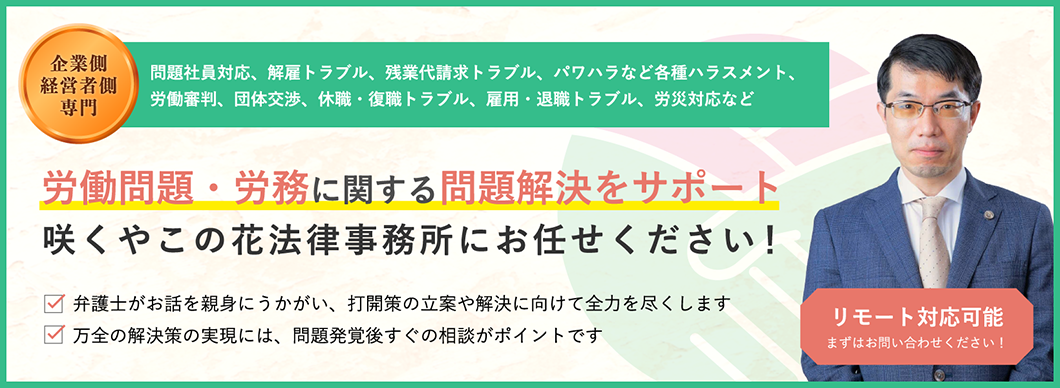
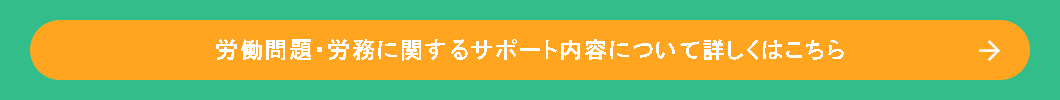
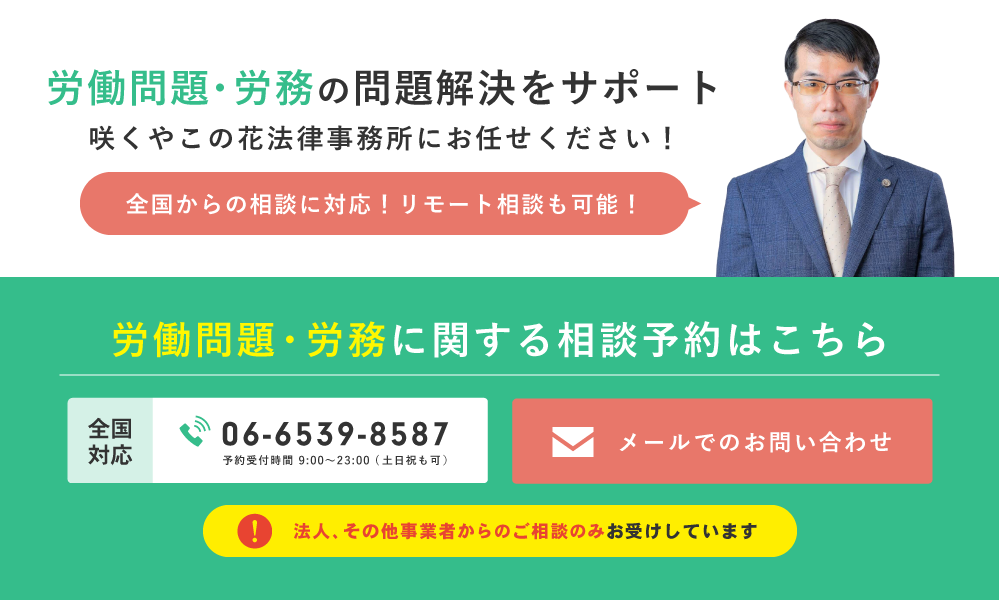
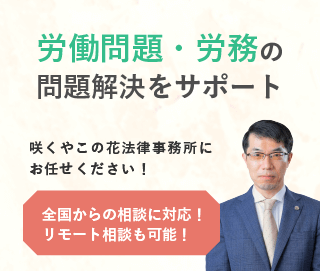





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る
















