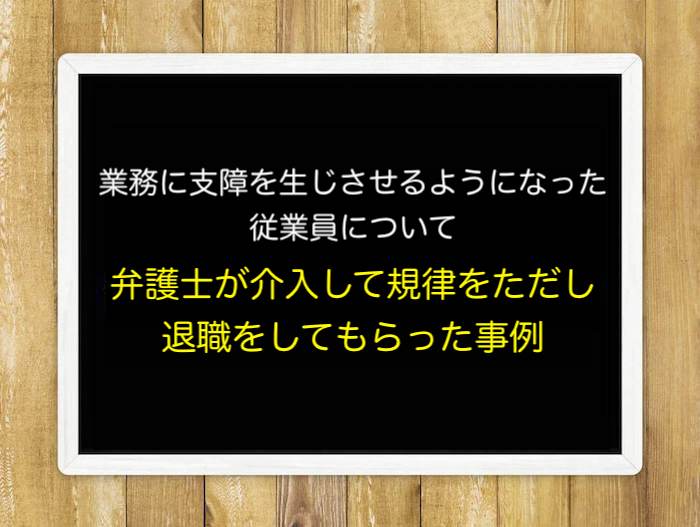
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 片山 琢也
出身地:大阪府。出身大学:京都大学法学部。主な取扱い分野は、「労働関連(組合との団体交渉、就業規則や契約書作成・チェック、残業代請求・解雇トラブルへの対応、従業員のメンタルヘルスから職場復帰へのアドバイス、従業員間のトラブルへの対応等)、債権回収、システム開発トラブル、建築業の顧客トラブル対応、インターネット上の悪質記事の削除請求など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
本件は、会社に古くから勤める従業員とのトラブルに関する解決実績です。
その古参社員は先代の頃から長年勤めているため、現社長である2代目よりも会社事業に詳しく、取引先との関係も深い立場にありました。
日々の業務もその古参社員を中心に行われており、その古参社員がいなければ業務がまわらない状況でした。そのため、会社もこの古参社員を特別扱いせざるを得ないような状態になってしまい、無断での遅刻・早退や多少の放言など、細かな問題については黙認してしまっていました。
その結果、古参社員の増長を招くことになり、最終的には待遇について不当な要求をする、要求が通らないと会社の指示に従わない等の問題行動をとるようになりました。そのために会社業務にも大きな支障が出る事態になっていました。
そこで、この古参社員にどのような対応をするかをご相談いただいたのが本件です。
2,問題の解決結果
問題の中心であった古参社員は話合いの末に合意退職となり、その後は社内ルールの運用を厳格にしたことで社内の規律がただされ、健全な職場環境を回復することができました。
3,問題解決における争点
不当な要求をしてくる古参社員への対応として、不当な要求をやめさせ、規律を守らせることができるかが、本件の課題となりました。
4,担当弁護士の見解
ここでは、本事案の担当弁護士による見解をご紹介します。
(1)顧問弁護士が会社の立場で介入したことが解決のきっかけ
この会社からはじめてご相談を受けたときには、長年、問題の古参社員を特別扱いしていた事で、もはや会社や社長がその古参社員に何か言っても真剣にとりあわず無視されるような状況になっていました。
会社もその古参社員に反抗されて業務に支障が出ることを恐れて強く言えない状態でした。そして、これが他の従業員にも波及し、会社が言うことに対しては他の従業員も真面目に対応しないような状況になっていました。
そこで、まずはこのような乱れた規律をただすために、第三者である顧問弁護士が会社の立場で介入し、問題行動の指摘、注意指導を行うようにして会社の意向を無視できない状況にしました。
(2)従業員への注意、指導を徹底した。
具体的には、会社が問題ありと判断した行為について、こまめにその日時、場所、内容を記録してもらうようにしました。
そして、その内容を弁護士にFAXで報告してもらい、弁護士が内容をチェックした上で対応が必要と判断したものについては、弁護士から会社に注意指導を実施してもらうよう指示をしました。注意指導の実施についても、今後に備えて日時、内容、相手方の反応を記録に残してもらうようにしました。
こうすることで、「その従業員は特別である」、「会社の言うことは真面目にとりあわなくていい」といった雰囲気を変えていき、会社の規律を取り戻していきました。
(3)業務の主導権を会社に取り戻す
その上で、次に、古参社員を業務の管理から外して管理権を会社に取り戻し、古参社員がいなくても会社の業務が行える体制を作ることを目指しました。
そのために、それまで古参社員が取引先との連絡窓口を担当していたところを、担当を別の社員に変えることを弁護士から提案し、これを実行してもらいました。これにより、それまで業務内容がその従業員を通してしかわからなかった点が改善されました。
(4)問題のある従業員の不正行為への対応
会社が業務を管理するようになると、会社備品の無断転売などそれまで把握できていなかったこの古参社員の過去の不正行為が明らかになりました。
それらの判明した事実については、弁護士が検証しました。その結果、中には重大な不正行為もあり、会社としてもはや、この古参社員と信頼関係を築くことはできないとの結論になりました。
そのため、この古参社員には「退職勧奨」を行うこととしました。
(5)問題のあった古参従業員への退職勧奨
退職勧奨にあたっては、弁護士が同席して古参社員に不正行為の事実関係の確認をし、また本人からの言い分を聴き取る作業をしました。話し合いの中で当人が不正行為を暗に認めたため、この古参従業員は合意のうえで退職することとなりました。
5,解決結果におけるまとめ
最後に本事案の解決結果から重要なポイントをまとめておきます。
(1)誰に対してもルールの運用は厳格に!
この事例のように、勤続年数の長い従業員がいる企業は珍しくないと思います。
そして、大企業と違い中小企業では、その従業員が事実上強い影響力をもち、社長や役員であっても強い態度がとれない等の事態になることもままあるのではないでしょうか。
もちろん、長く勤めてくれている社員は会社の財産ですから、そのような従業員を大切にすることは当然です。そのため、長年の功労に報いる意味で、ルールに則って給与を増額する等の待遇面をよくすることは問題ありません。
しかし、ルールを曖昧にして古参社員だけ例外のように扱うことは、今回の事例のように間違いの元になります。会社の財産であった従業員がむしろ会社にとって害を与える存在になってしまいます。
このような問題は、会社がルールをおろそかにしたことが発端になって生じます。長年勤めてくれている社員等、近しい関係となった者に対しても例外をつくらずルール通りに、厳格に運用することが重要です。
(2)ルールをあいまいにすることは厳禁!
会社が従業員の問題行為を把握していながら、ルールを疎かにしてこれを放置することには様々な危険性があります。
1つは、会社がルール違反を黙認することで、ルールを破ってもおとがめなしということで誰もルールを守らなくなってしまう事です。
今回のケースでも問題のなかった他の従業員も会社の指示に対して真面目に対応しなくなってしまいました。
また、いざルールを適用して取り締まろうとしても、例外を認めてしまっていると結局誰にも適用できなくなってしまう恐れがあります。つまり、例えば「遅刻厳禁」というルールがあったとしても、Aさんを特別扱いして遅刻しても何の注意もしていないと、「会社は遅刻をそれほど問題視しておらず、ルールは守る必要がない」と他の従業員からも思われてしまいます。
そうすると、Aさん以外の人が遅刻した時にも、会社はルールを適用して注意することができなくなってしまいます。
こうなると、せっかく就業規則等で社内ルールを規定していても、何の意味もないことになってしまいます。
(3)ルールをあいまいにした結果、会社が敗訴した裁判例もある。
ルールをあいまいにした結果、会社が敗訴した裁判例もあります。(北沢産業事件 東京地裁判決-平成19年9月18日)。
下記でこの裁判例を簡単に紹介します。
裁判例:
北沢産業事件(東京地裁判決-平成19年9月18日)
●事案:
会社が、会社データを無断で消去するなどしていた問題社員を解雇した事案です。
これに対して、従業員が不当解雇であると主張して解雇の撤回を求めて裁判を起こしました。
●裁判所の判断:
結論:
裁判所は、従業員の訴えを認めて、不当解雇であると判断し、会社に従業員を復職させることを命じました。
理由:
裁判所は、会社が主張した問題社員の問題点が軽視できないことがらであり、解雇事由にあたることは認めました。
しかし、裁判所は、これらの問題点は会社が1年以上前に把握していた事実であり、それにもかかわらず口頭注意すらしていなかったため、会社は重大な問題と思っていなかったとの判断を示しました。
そして結論として、いままで何の対応もしていなかった以上、1年以上前の解雇事由を持ち出して解雇を正当化することは許されないと判断しました。
この事案では、会社は問題行動について1年以上放置していました。そして1年以上たってから解雇をしたところ、裁判所はいまさら解雇することは認められないとして不当解雇と判断しました。
このように、問題行為を把握したときは、速やかに対応することが必要です。とりあえず後回しにしておこうとして放置していると、結局は対応ができなくなってしまいます。
(4)弁護士への依頼が問題解決の近道
現時点で、既に従業員の問題行為を黙認してしまっている等の事態が生じてしまっているなら、早急に対応をとる必要があります。放置すればするほどどんどん対応が難しくなってしまいます。
今回のケースのように、会社だけでは対応が難しくなってしまっているような場合は、第三者である弁護士の介入が有効な手段となります。似たような状況でお困りの場合は、ぜひご相談ください。
6,問題社員対応でお困りの際は「労働問題に強い弁護士」への相談がポイント!
今回ご紹介してきた事案のように「問題従業員の対応」でお困りの企業様は、本記事でご説明してきた通りスピード相談が重要です。そのため、まずは労働問題に強い弁護士がそろう「咲くやこの法律事務所」までお問い合わせ下さい。
7,咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回は、「業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した問題社員対応の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・やる気のないベテラン社員の指導を弁護士がサポートして解決に至った事例
・成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
・正当な指導をパワハラであると反抗する問題社員に対してメールで指導し退職させるに至った事例
・パワハラを繰り返す社員を解雇したところ、不当解雇であると主張されたが、弁護士が交渉して退職合意をし、訴訟回避した事例
・歯科医院で勤務態度が著しく不良な問題職員の指導をサポートした事例
・遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員を弁護士の退職勧奨により退職させた成功事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






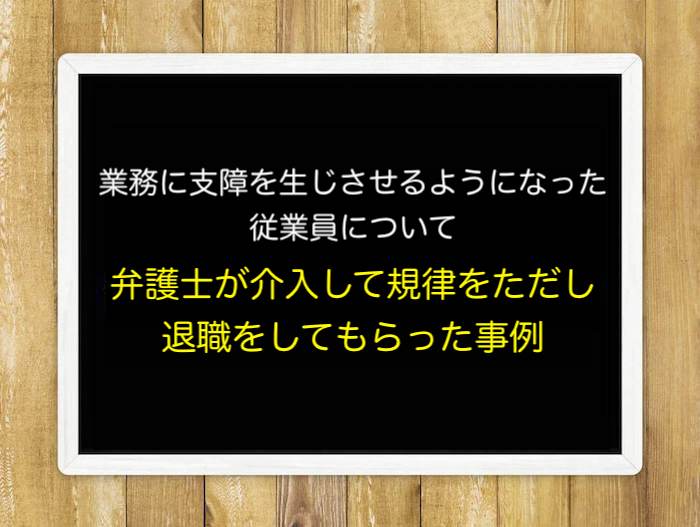

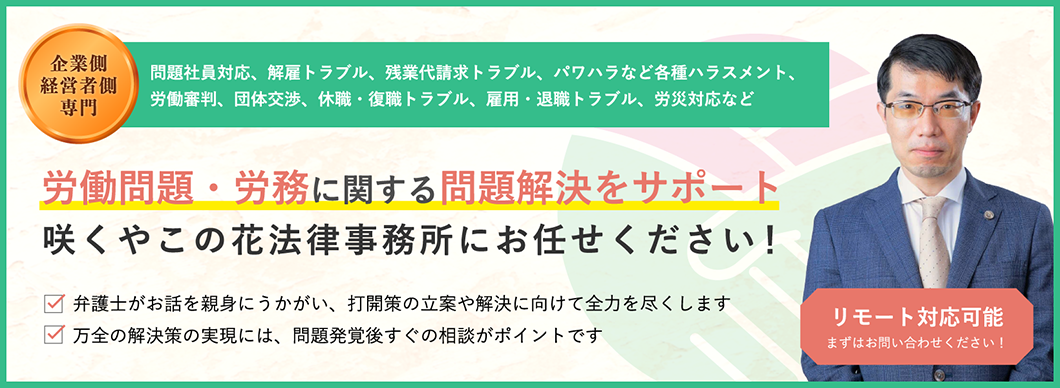
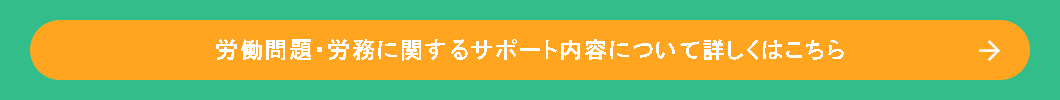
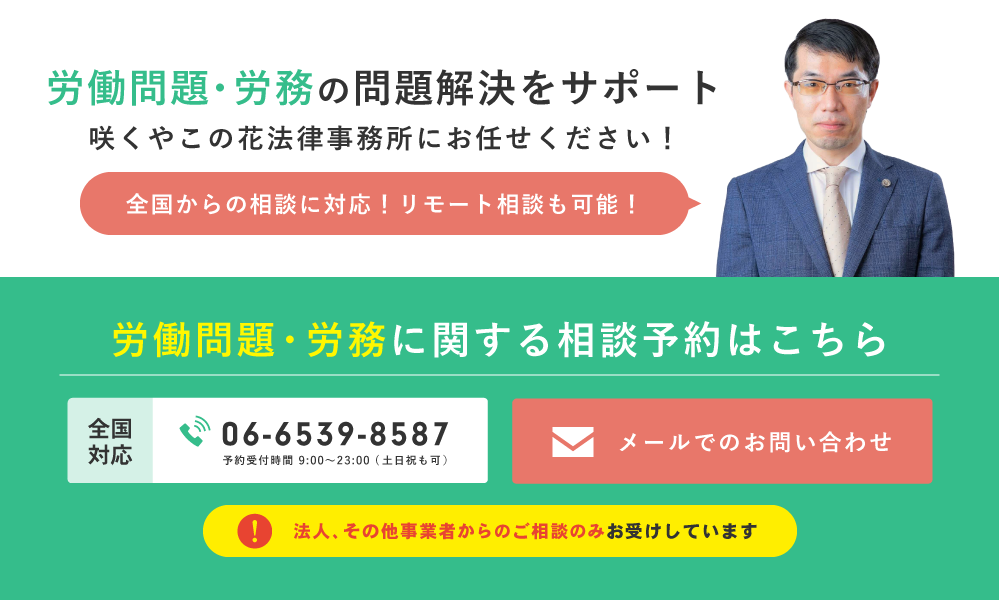
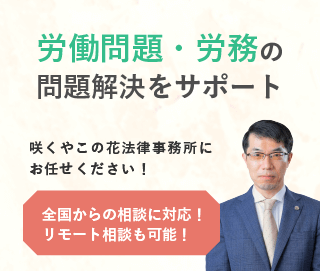





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















