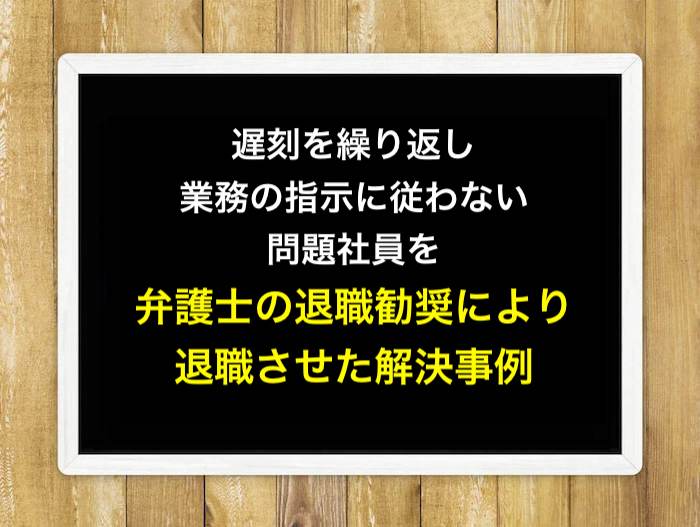
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「電気工事業」の事例です。
2,事件の概要
本件は、遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員の退職勧奨について、咲くやこの花法律事務所が依頼を受け、従業員Aに退職するよう説得することで、最終的に退職を承諾させたケースです。
相談に来られた会社は、協調性がなく、遅刻を繰り返し、また、上司の指示や同僚からの依頼に応じようとしない従業員Aに何とか退職してもらいたいと考えていました。
社長や上司も、従業員Aに対し、何度か態度をあらためるように説得しましたが、従業員Aが全く聞く耳を持たない様子で困っているとのことでした。
会社から従業員Aに退職を働きかけても、のらりくらりとかわされて、退職に向けた話合いが進みそうにないが、弁護士から従業員Aに話をすることによって、具体的な進展があるのではないかと思い、咲くやこの花法律事務所にご相談にお越しになりました。
3,問題の解決結果
弁護士による退職勧奨の結果、1ヶ月分の給与の支払いと残っている有給休暇を買い取るという条件で、退職に応じさせることに成功しました。
4,弁護士による対応内容
本件で弁護士が取り組んだ対応内容について、以下で詳しく解説いたします。
(1)相談時に弁護士が会社担当者から詳細な聞き取りを行う
ご相談を受けて、弁護士は、そもそも、なぜ会社が従業員Aに退職してもらいたいと考えているのかを聞き取りました。
会社の説明によると、従業員Aは、週に何度も、電車が遅れたとの理由で、5分から30分程度遅刻して出勤しており、業務に支障が出ているとことでした。
上司は従業員Aに対して、「電車が頻繁に遅れるのであれば、もう一本早い電車に乗るなどの対応があるのではないか」と指導しました。
しかし、従業員Aは「一本早く乗ると、会社に着く時間が早くなりすぎるから」との理由で、態度を改めず、そのまま、週に何度も遅刻を繰り返しているとのことでした。
その他にも、従業員Aは、上司の指示や同僚からの作業の依頼に応じようとせず、「それは私の仕事ですか」と尋ねるといった態度をとっているとのことでした。
以上のような従業員Aの態度から、会社は、このまま従業員Aが在籍していると社内の空気が悪くなり、他の従業員の意欲が低下するおそれがあると判断し、退職してもらうよう進めたいとの考えをお持ちでした。
(2)弁護士が問題社員に面談をして退職勧奨を行った
会社としては、社長が退職勧奨をしても、従業員Aはまともに取り合わないと考えていました。
そして、第三者である弁護士が退職すべきであると真摯に説得することで、従業員Aが現状をしっかりと受け止めるのではないかと考えているとのことでした。
そのため、会社の希望に従い、弁護士が会社の代理人として退職勧奨を行うことになりました。従業員Aは東京事務所に在籍していたため、弁護士が東京に行き、直接従業員Aと面談することにしました。
(3)退職を求める理由についての資料の準備をする
弁護士から退職勧奨を行う場合であっても、従業員Aに対して、退職を求める理由を説明しなければなりません。
今回、従業員Aに退職を求める理由は聞き取りにより明らかでしたが、態度が悪いという部分はどうしても会社の主観的評価が入ってしまいます。
そのため、態度が悪いことを指摘することは控えることにしました。
一方、従業員Aは遅刻する度に、上司の携帯電話にショートメッセージで連絡しており、その回数は2年で70回にも及びました。遅刻したことは客観的に証明可能でしたので、退職勧奨時に、その部分を指摘することにしました。
(4)退職についての金銭的条件をあらかじめ検討しておく
退職勧奨をした後、従業員が金銭的な条件次第では退職に応じると言う場合があります。
このような展開になった場合、「会社で金銭的条件を検討した上で、後日、通知します」といった対応をした場合、その間に従業員の気が変わって、「条件にかかわらず、退職しない」と主張される可能性があります。
そのため、確定的な内容でなくても構わないので、退職勧奨の前にどのような金銭的条件であれば会社から提示できるかを検討しておくべきです。
本件でも、会社からどの程度の金銭的条件であれば提示できるかについて、弁護士と会社担当者で事前に打合せを行いました。
その結果、条件交渉に至った場合、以下の条件を提案することにしました。
- ●1,賃金1ヶ月相当の退職金の支払い
- ●2,残っている有給休暇の買い取り
- ●3,離職理由を会社都合として処理する
このうち「1,賃金1ヶ月相当の退職金の支払い」の退職金の支払いについては、即日解雇する場合であっても、原則として1ヶ月分の解雇予告手当を支払わなければならないことを考え、盛り込むことにしました。
「2,残っている有給休暇の買い取り」については、従業員から「有給休暇の消化完了後に退職する」と主張された場合には、認めなければならないことの均衡上、盛り込むことにしました。
「3,離職理由を会社都合として処理する」の離職理由については、会社都合とすることで従業員にとって失業保険を受給するうえで有利になる一方で、会社は会社都合としても特段の不都合が生じないことから、従業員の退職を後押しするために盛り込むことにしました。
(5)あらかじめ退職合意書も準備してのぞむ
「1」から「3」の条件についてその内容を盛り込んだ退職合意書をあらかじめ準備して、退職勧奨に臨みました。なお、退職合意書には「清算条項」も入れておく必要があります。
清算条項とは、合意書に記載された内容以外には会社と従業員の間に債権も債務もなく、今後お互いに何も請求しません、ということを確認しておく条項です。
この条項は、例えば従業員が退職後に在職中にパワハラがあったなどといって会社を訴えてくることを防ぐためにも重要な条項ですので必ず入れておくことが必要です。
(6)退職勧奨当日の対応
弁護士が退職勧奨に立ち会う従業員Aの上司と合流し、東京事務所近くの喫茶店で簡単な確認の打合せを行いました。
その後、従業員Aを会社から喫茶店に呼び、退職勧奨を行いました。
弁護士の自己紹介を済ませた後、遅刻回数を一覧にまとめたものを示し、上司から注意・指導を行ったにもかかわらず、一向に改善されなかったと指摘しました。その上で、電車の乗り継ぎなどを考慮して、無理なく通勤できる範囲の会社に転職することを検討したほうがよいのではないかと提案しました。
従業員Aは、「退職するのは構わないが、急に収入がなくなるのは困る。有給はどうなるのか。」との質問が出ました。
弁護士は、従業員Aの上司に確認した上で、残りの有給休暇分は全て支払う、退職金として1ヶ月分の給与を支払うとの条件を伝えました。
従業員Aは、そうであれば退職に応じると答え、その場で退職合意書に署名しました。その後、会社から有給休暇分と退職金を支払い、従業員Aは退職しました。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の見解について詳しく解説していきます。
(1)本件では解雇した場合に解雇の正当性が認められるかは不明であった
会社と従業員との雇用契約を会社側から終了させる方法としては、大きく分けて、会社が従業員を解雇する方法と、退職勧奨をして従業員の意思で退職してもらう方法の2種類があります。
このうち、最初の方法の、解雇については、後で従業員から不当解雇だとして訴えられる可能性があります。
そのため、直ちに解雇すべき特別な事情(社内での犯罪行為があった場合など)がない限り、まずは退職勧奨を検討すべきです。
本件では、従業員Aがかなりの頻度で遅刻を繰り返しているという証拠はあり、これに対して上司も注意指導をしていましたが、上司が注意指導をしてきたことを裏付ける証拠がありませんでした。
裁判所では、解雇する前に十分な指導を行わなければならないという考え方が一般的です。
そのため、仮に会社が従業員Aを解雇して、後日不当解雇であるとして訴えられた場合、上司が注意指導を繰り返してきたことについての証拠がないと、裁判所では、遅刻に対する会社の指導が不十分であるとされ、不当解雇であると判断される危険もありました。
そのため、相談の際に弁護士からまずは解雇ではなく、退職勧奨をすべきであると会社担当者に説明しました。
(2)会社とのミスマッチであることを強調する
退職勧奨は対象となる従業員の性格をよく考えて行うことが必要です。
従業員の性格によっては、退職勧奨の場面で、従業員の問題点を追及すると感情的な反発を生み、うまくいかないことがあります。
退職勧奨は文字通り退職を勧めるものであって、従業員を論破するものではありません。
こういった場合には、従業員の問題点を追求するのではなく、会社と従業員とのミスマッチを強調して、退職を促すことが必要です。
本件でも、確かに従業員Aが遅刻を繰り返していたことは問題なのですが、そこを厳しく責めるのではなく、「無理なく通勤できる範囲の会社で働いたほうが、あなた自身の評価も上がるのではないか」と、現在の会社とのミスマッチを強調しました。
その結果、従業員Aは、こちらの提案を理解し、スムーズに退職に応じることになりました。
(3)退職合意書の作成
退職勧奨をする場合、その場で退職届や退職合意書の提出を求めないというのが原則です。ただし、従業員が退職条件を受諾しており、不満を述べていないような場合には、気が変わらないうちに退職届や退職合意書を取得してしまったほうがよいケースもあります。
この点は、臨機応変な対応が必要になります。
本件でも、退職届や退職合意書の回収を急がないということは会社とも事前に確認していましたが、退職勧奨の結果、従業員Aが退職条件を了解していたため、その場で署名してもらうことにしました。退職条件について、会社が金銭的な譲歩をして合意する場合、その後に紛争が蒸し返され、さらに請求を受けることがないよう退職合意書をしっかりと作成しておく必要があります。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、最終的に、従業員Aは、賃金1ヶ月分の退職金と残りの有給休暇の買い取りによって退職していきました。
会社が従業員に退職してもらいたいと考える場合、様々な理由があると思います。その理由や、従業員の個性によって、どのような手続、手順を選択すべきかについて、慎重に検討する必要があります。
また、雇用契約が終了する場面は、会社と従業員との関係において、最も紛争が生じやすい場面の1つです。退職勧奨の場面でも、退職強要だといって訴えられたり、パワハラだといって訴えられるケースが増えています。
そのため、後に紛争が生じないよう、十分に注意して準備を進めることが重要です。本件のように弁護士に同席してもらい、話を進めることが最も望ましいです。
7,咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「労働問題に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】問題社員対応テーマに関連した解決実績
今回は、「遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員を弁護士の退職勧奨により退職させた解決事例」についてご紹介いたしましたが、この事例と関連する解決実績も以下でご紹介しておきますので、参考にご覧下さい。
・やる気のないベテラン社員の指導を弁護士がサポートして解決に至った事例
・業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例
・歯科医院で勤務態度が著しく不良な問題職員の指導をサポートした事例
・歯科医院の依頼で能力不足が顕著な職員の指導をサポートして問題解決した事例
・成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






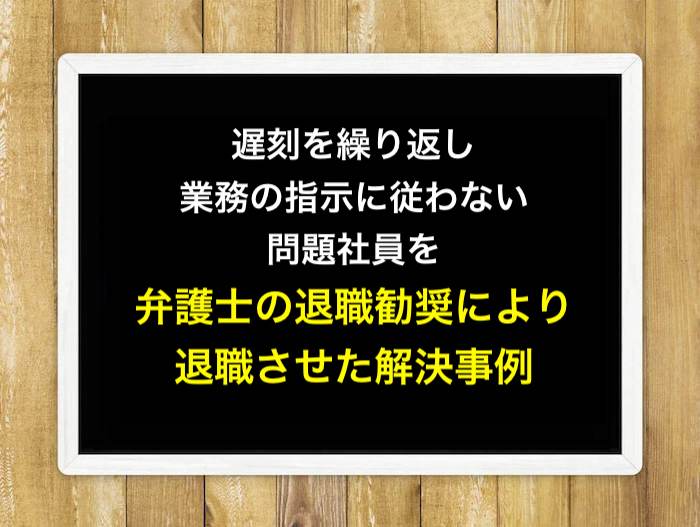

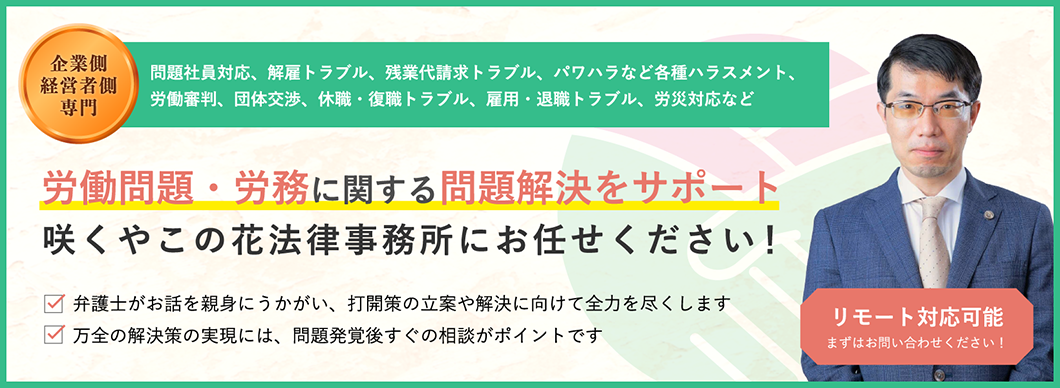
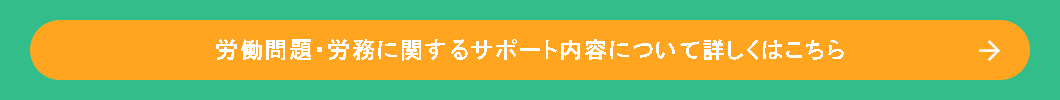
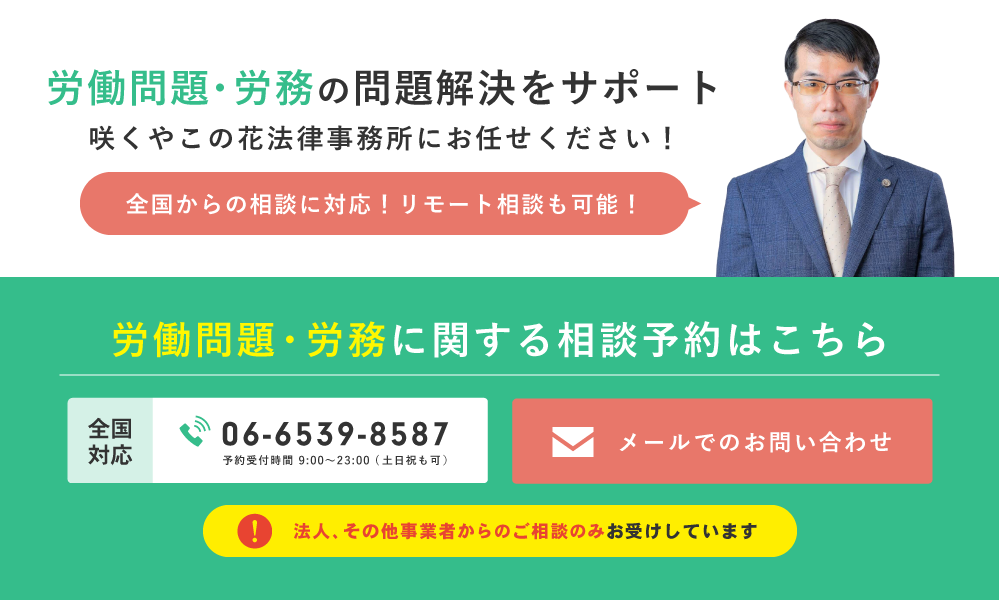
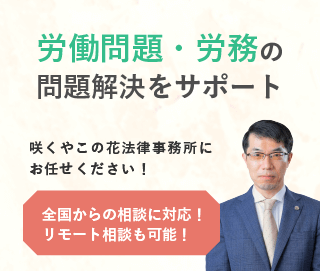





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















