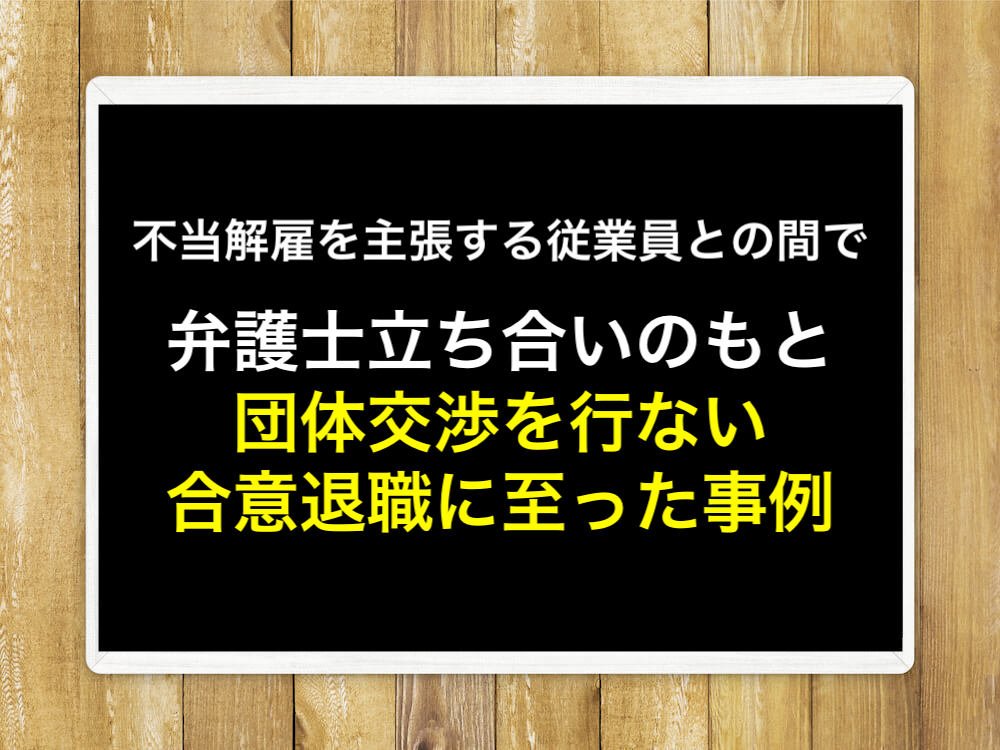
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 小田 学洋
出身地:広島県。出身大学:広島大学工学部工学研究科。主な取扱い分野は、「労務・労働関連(企業側)、債権回収、システム開発トラブル、運送業関連、フランチャイズ契約トラブル、顧客クレーム対応、インターネット上の誹謗中傷対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「コンサルタント業」の事例です。
2,事案の概要
本件は、会社が解雇した元従業員が不当解雇であるとの主張や未払い残業代がある等の主張をして外部の労働組合に加入し団体交渉を申し入れてきた事案です。
3,問題の解決結果
労働組合は解雇の撤回を求めていましたが、会社としては、本人に期待した能力がなかったので、解雇を撤回して再度雇用するという選択肢は避けたいと考えていました。一方、未払い残業代については、法令上支払いが必要な範囲で支払う意思がありました。
弁護士が、会社側から依頼を受け、団体交渉に会社の代表とともに出席し、一定の金銭補償をすることを条件として合意退職とすることができました。
4,問題の解決における争点
以下では、本件に関する問題解決における争点について解説いたします。
(1)能力不足を理由とする解雇の有効性について
解雇は会社側の判断のみで行う労働契約の解除です。ただし、正当な解雇理由がないのに解雇した場合は、不当解雇となり、解雇は無効になります(労働契約法16条)。
▶参考情報:労働契約法16条
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
・参照元:「労働契約法」の条文はこちら
本件で、会社が、元従業員を解雇した理由は能力不足でした。
この解雇した従業員は従事する業務についての経験者として中途採用された経緯がありましたが、会社が期待していた能力を備えていないと判断され、解雇に至りました。
判例上、能力不足の従業員の解雇は、会社が十分な指導を行っても能力不足が改善されない場合でなければ、正当な解雇とは認められていません。
しかし、特定の業務能力をもつことを前提に即戦力として従業員を中途採用したケースで、採用時に前提としていた能力を有していないことが判明した場合には、このような指導を行わなくても、比較的解雇が認められやすい傾向にあります。
そのため、本件では、会社が特定の業務能力をもつことを前提に採用した中途採用のケースといえるかどうかが、争点になりました。
また、能力不足を理由とする解雇では、実際に能力が不足していたことを裏付ける証拠の有無も重要です。
この点については、本件では具体的な能力不足の証拠として、書面等として残った記録はほとんどありませんでした。
そのため、交渉が決裂して、不当解雇であるとして訴訟を起こされた場合、裁判所で不当解雇と判断され、多額の支払を命じられる可能性も高いと予想される状況でした。
(2)残業代の未払いについて
残業代の未払いについては以下の点が問題になりました。
1,残業時間の端数処理
会社は残業時間をタイムカードで記録し、残業代を支払っていましたが、労働時間の端数の処理に関して、厚生労働省の通達とは違う計算をしている部分がありました。
具体的には、厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)「賃金計算の端数の取扱い」は、1か月の時間外労働を合計したうえで1時間未満の端数の処理について30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる処理をすることは賃金の全額払いの原則に違反しないとしています。
ところが、会社は、月の時間外労働の時間数を合計する前の、1日の労働時間について、10分未満の時間を切り捨てる処理をしていました。
このように日々の労働時間の端数を一律に切り捨てる処理は適法とはいえませんでした。
2,タイムカードに記録されていない労働時間
また、組合側からは、タイムカードに記録されていない以下の時間が労働時間に含まれるとする主張があり、この主張への対応が問題となりました。
- ●予定されていた業務が終了したあとに同僚と業務の進め方について話をしていた時間
- ●業務終了後に事業所内でおこなった懇親会へ出席した時間
さらに、会社では、残業した場合に定時後に休憩時間を設けていましたが、この休憩については就業規則や雇用契約書に記載がありませんでした。そのため、この定時後の休憩時間が、賃金支払いの対象にならない休憩時間と認められるかどうかも問題となりました。
5,担当弁護士の方針
ここからは、担当弁護士の方針についてご説明していきます。
(1)団体交渉は不当労働行為に注意
団体交渉は話し合いの場なので、組合側の要求についての会社側の見解を、組合に対し、十分に説明することが重要です。
組合の要求を単に断るような紋切り型の説明に終始することは、不当労働行為として違法行為になり、会社にとって余計に不利になる結果となりますので注意が必要です。
本件では、あらかじめ組合に対して書面で会社側の見解を説明したうえで、団体交渉の場で改めて口頭でも書面の内容を説明することで、十分な説明を行いました。
(2)解雇の理由については具体的に問題点をリスト化して主張する
解雇の理由については、解雇予告通知書で、解雇の根拠となる就業規則の条項を記載していましたが、能力不足と判断される具体的な理由までは示していませんでした。
そこで、団体交渉では、具体的な能力不足とされる点をリスト化して組合側に提示し、交渉に臨みました。
(3)タイムカードは早期に開示して支払うべき残業代は支払う
次に、組合からは残業代の計算の資料として、タイムカードや就業規則の開示を求められました。
この点については、いたずらに情報開示を拒絶しても解決に向けた話し合いができません。そのため、組合から秘密保持誓約書を提出させた上で、早期に必要な情報を開示することにしました。また、会社が通達に従って計算できていなかった部分については、通達に従って再計算し、差額を支払うことを会社側から提案しました。
(4)労働時間の争いがある部分は会社の考えを適切に主張する
残業代については、前述のとおり、労働時間自体にも争いがありました。
これについては、以下のように会社の考えを主張しました。
1,同僚と業務の進め方について話をしていた時間が労働時間にあたるか?
調査の結果、問題となった会話は、仕事の進め方について先輩社員が話をしたものであることがわかりました。
しかし、会社の指示した業務が終了した後に先輩社員とのおこなわれた会話であり、会社が指示した業務ではありませんでした。
また、そのようなことがあったのは1回だけでした。それに加え、本人がタイムカード上で労働時間として記載していないことから会社は労働時間とは把握していませんでした。
そこで、この時間については、会社の立場から、労働時間とは認められないと主張しました。
2,社内懇親会に参加した時間が労働時間にあたるか?
一般論として、宴会への参加が労働時間であると認められることはありますし、本件の懇親会は、定時後に職場でおこなわれたものでした。
しかし、参加は義務ではなく、実際に参加しなかった人もいました。
そのため、会社側の立場から、懇親会参加時間は労働時間とは認められないと主張しました。
3,定時後の休憩時間が休憩時間と認められるか?
定時後の休憩時間については、雇用契約書や就業規則には記載がありませんでした。
しかし、eメール等で、元従業員から定時後の休憩時間について質問を受け、会社側から回答して説明していた経緯もあり、また、実際に休憩もとれていました。
そこで、この休憩時間についても、会社側の立場から、労働時間とは認められないと主張しました。
(5)組合側の主張との対立
組合からは、解雇については、多くの点で会社側の主張が事実ではないとの反論がありました。また、会社が要求する技術水準が高すぎるのであって、能力不足ではないとの主張もありました。
これらの主張は能力不足の解雇では常に議論になる部分であり、当然予想される反論ともいえました。
一方、通達に基づく未払い賃金の再計算については組合も同意しました。
しかし、同僚と業務の進め方について話をしていた時間については、業務の進め方に関する話をしたものであるから、業務の一部であるというのが組合側の主張でした。
また、社内懇親会への参加時間についても、新人であった元従業員が参加を断ることは不可能であり、参加は業務命令と評価できると組合側は主張しました。
さらに、定時後の休憩時間については、元従業員が会社から説明を受けたことは認めたものの、実際には休憩はとれていなかったと主張しました。
(6)現実的な解決点に導く
上記のような会社と組合の主張の対立は団体交渉を継続しても解消できる見込みが立ちませんでした。
会社として、ここで交渉を打ち切り、争点の判断を裁判所にゆだねた場合、未払い賃金の点は許容できるリスクでしたが、解雇が無効とされるリスクがあることは問題でした。裁判所で解雇が無効と判断されると、多額の金銭の支払いに加えて、従業員を復職させることも命じられることになり、それは避けたいというのが会社の意向でした。
一方、組合としても、仮に裁判所で、不当解雇であるとして解雇無効が認められて元従業員が復職できたとしても、会社と信頼関係を築いて働くことは難しいと考えていました。また、裁判等で争うことにより、元従業員の地位を長期間不安定な状況のままにするのは望ましくないとの考えでした。
そこで、弁護士が会社の代理人として、会社から一定の金銭補償をすることで合意退職とすることを提案しました。組合は、本件で他には妥当な解決はない、として金銭補償をうけいれて合意退職することを了解しました。交渉の結果、金銭補償額は給与の約2か月分とし、退職を合意できました。
6,解決結果におけるまとめ
(1)団体交渉で解決できる紛争は解決する
本件では、解雇撤回の要求があったものの、組合との団体交渉の結果、合意退職とすることで解決でき、労働審判や裁判になることを回避することができました。
外部の労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、拒否反応を示して、単に断るだけの紋切り型の対応をしてしまいがちです。
しかし、正しく交渉を行い、交渉で解決できる問題は交渉で解決することが会社にとってもメリットになります。交渉で問題を解決できれば、裁判で会社として大きなリスクを抱えることを回避することができるからです。
(2)解雇は事前に弁護士への相談が必要
また、そもそもトラブルに発展しないように、解雇前に必ず弁護士に相談し、正しい手続を踏んだうえで解雇をすることも非常に重要です。
解雇の前に、万が一紛争になったときにそなえて十分な証拠を準備しておくことも必要です。
本件では会社が解雇前に弁護士に相談せずに自己流で対応して解雇していましたが、その際の会社からの説明が不十分であったことも原因となって、紛争に発展しました。
(3)採用時の説明を充実させる
さらに、本件のようなトラブルを避けるためには、採用時に必要とするスキルについて詳細かつ具体的な説明を行い、雇用側と雇用される側で、求められるスキルの水準について理解を合わせ、記録として残すことも必要です。
また、適切な試用期間を設け、どのような基準で正社員への本採用をするかを明確に定めておくことにより、試用期間後、正社員への本採用を拒否する場合も、従業員側の一応の納得が得られるように工夫しておくことも必要です。
本件のような団体交渉になってしまった場合はもちろん、団体交渉に発展することを避けるためにも、従業員の解雇や残業代のトラブルについては、早期に咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。
7,咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「労働問題に強い弁護士への相談サービス」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回は、「不当解雇を主張する従業員との間で弁護士立ち合いのもと団体交渉を行ない合意退職に至った事例」について、ご紹介しました。
他にも、解雇トラブルや残業代トラブルなど、今回の事例に関連した解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
●解雇トラブル
・成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
・解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例
・パワハラを繰り返す社員を解雇したところ、不当解雇であると主張されたが、弁護士が交渉して退職合意をし、訴訟回避した事例
●残業代トラブル
・退職者から残業代請求された企業から相談を受け、約480万円の請求を3分の1以下に減額できた成功事例
・元従業員からの解雇予告手当、残業代の請求訴訟について全面勝訴した事案
・配達ドライバーの残業代トラブルで748万円の請求を弁護士が230万円に減額した成功事例
・手待ち時間が労働時間でないことを認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額して解決した事例
・退職した従業員による残業代未払い請求のケースで、支払金額を請求額の半額程度に減額に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






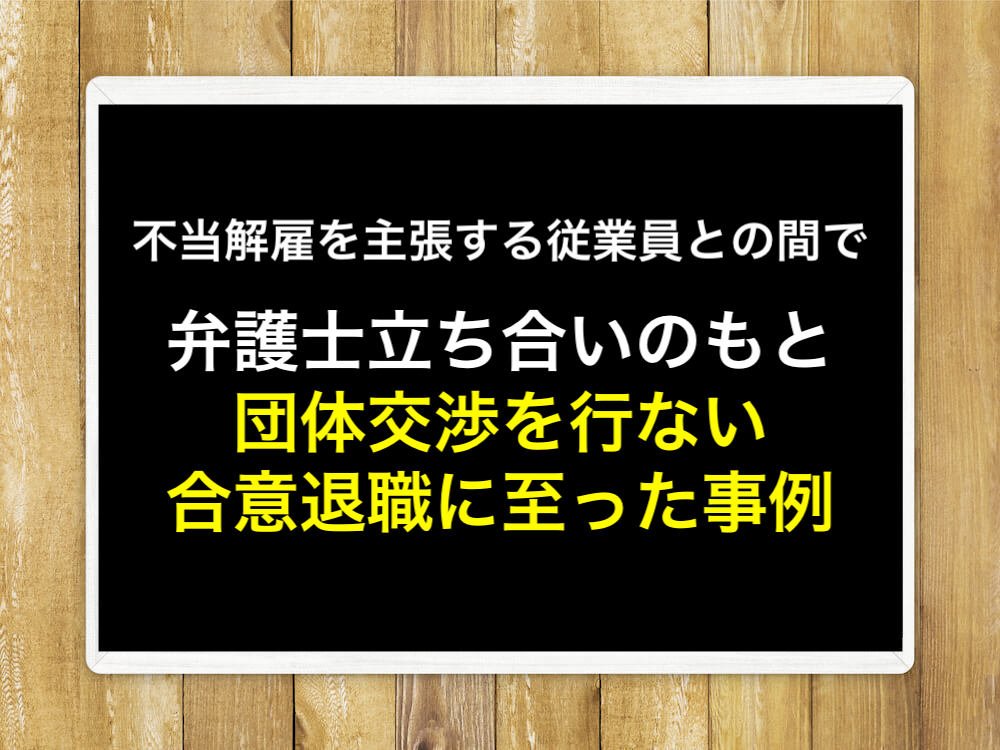

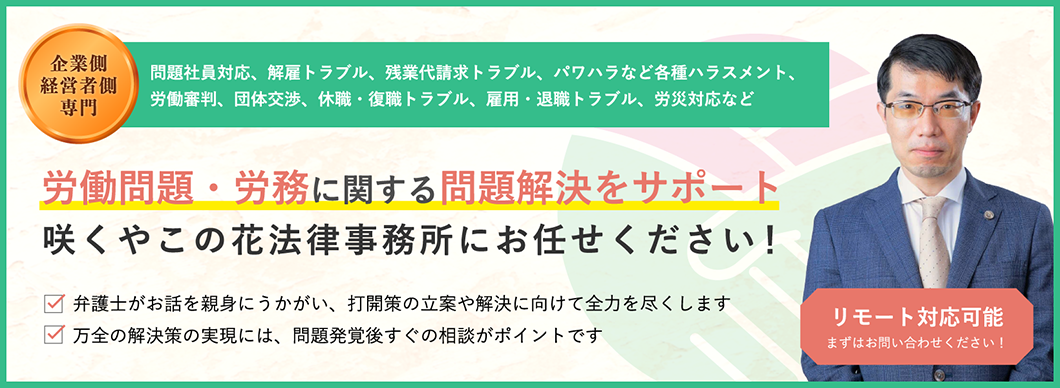
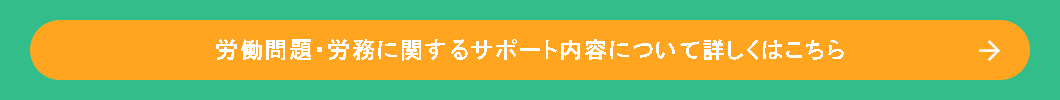
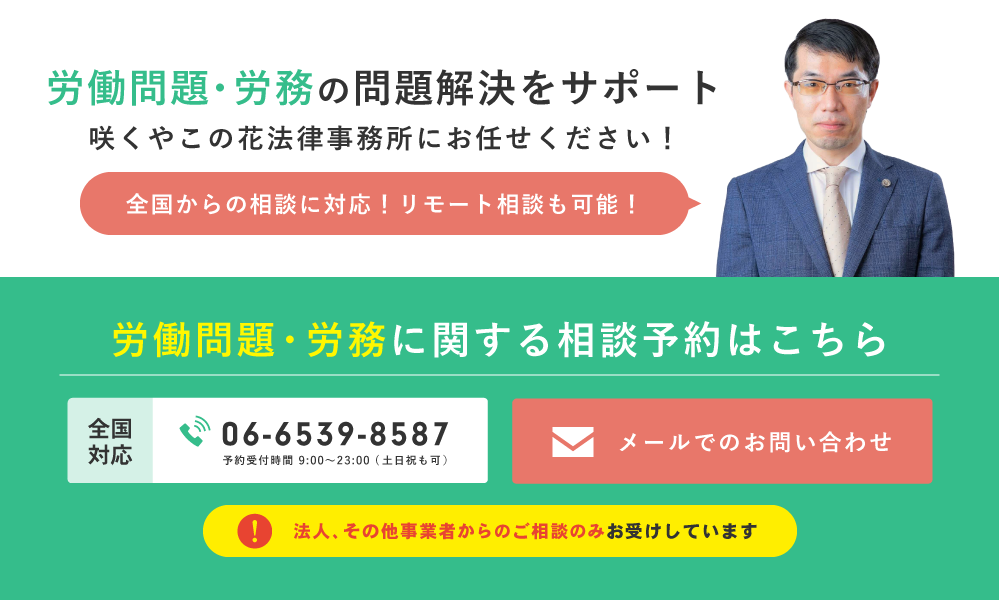
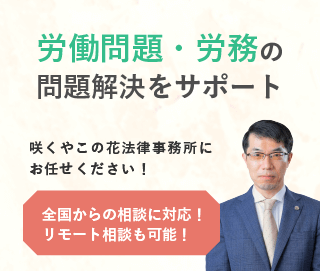





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















