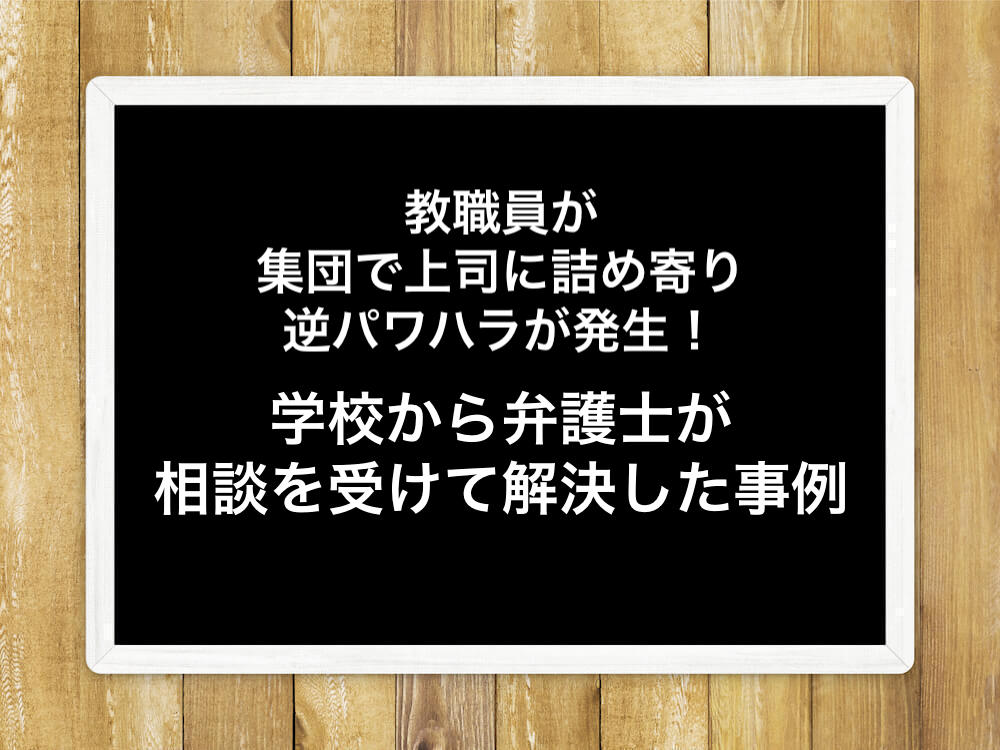
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 片山 琢也
出身地:大阪府。出身大学:京都大学法学部。主な取扱い分野は、「労働関連(組合との団体交渉、就業規則や契約書作成・チェック、残業代請求・解雇トラブルへの対応、従業員のメンタルヘルスから職場復帰へのアドバイス、従業員間のトラブルへの対応等)、債権回収、システム開発トラブル、建築業の顧客トラブル対応、インターネット上の悪質記事の削除請求など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「学校法人」の事例です。
2,事案の概要
相談のあった学校法人では経験豊富な指導担当者を新しく迎えて、現場の教職員の指導や相談を任せていました。
当然、教職員に問題があれば、指導担当者がそれについて意見をしたり指導することがありました。しかし、教職員の一部がこれらの指導に不満を持つようになり、指導方法に問題があるなどとして、指導担当者ひいては学校側と対立することが次第に増えていきました。
この対立がだんだんと深くなっていたところ、1人の教職員が行き過ぎた指導はパワハラであり、それにより体調不良になったと主張し始めたことがきっかけで、学校側と教職員側が決定的に対立する事態になってしまいました。
一部の教職員が学校に不満を持つ他の教職員をまとめ、指導担当者の指導に問題があったことを認めるよう学校側にせまりました。
このような経緯の中で、教職員らが大勢で学校側責任者に詰め寄るなど、学校の業務運営にも支障をきたす状況にいたり、その解決について、咲くやこの花法律事務所にご相談いただいた事例です。
3,問題の解決結果
弁護士がパワハラの有無について事実関係を調査したうえで、パワハラの事実はないと確認し、それを教職員全員の前で説明したことで、まずは発端となったパワハラの主張によるトラブルを収束させました。
そして、それまで教職員側からの集団の圧力におされて適切な指示・指導ができていなかったため、弁護士もサポートして、学校から教職員らに対して適切な指示・指導を行うようにしていきました。
その結果、学校に反発していた教職員らの言動が次第におさまり、学校の正常な運営を取り戻すことができました。
4,問題の解決における課題
以下では、本件に関する問題解決における課題について解説いたします。
(1)現状の把握
ご相談時、学校は、教職員側と学校側に二分され、双方が全面的に対立している状況でした。
しかし、このような場合、教職員側の全員が等しく学校側に不満を持っているかと言えばそうではありません。多くの場合、主導する人間がおり、それ以外の人達は表面上それに従っているだけです。
そのため、事態を収拾するには、誰が学校に反発する教職員らを主導しているのかを正しく把握することが重要です。
そこを確認せずに、主導者以外の者を相手にして話し合いをしても、また別の問題で対立が再燃するだけで、解決に至りません。学校の指導に反発するグループの中心人物に対して、働きかけることで、はじめて事態の改善が可能になります。
そのためには、まずは、現状の正しい把握が課題となりました。
(2)パワハラに当たるかどうかの判断
本件で学校を二分するような大きな対立が生まれたきっかけは、1人の教職員が、自分に対する指導がパワハラであり、それにより体調不良になったとして、学校側の安全配慮義務違反を主張し始めたことでした。
そのため、本件の問題解決のためには、このパワハラの主張を解決することが必要になりました。
5,担当弁護士の見解
ここからは、担当弁護士の見解についてご説明していきます。
(1)関係者からの聞き取り
1,対立するに至った経緯の確認
ご相談を受けて、弁護士が、学校関係者からの詳細なヒアリングを行い、現在の対立関係に至った経緯や、教職員側で学校に反発する言動を主導しているのは誰か等の事実関係の確認を行いました。
学校の指導に反発していた教職員らは、学校が迎えた指導担当者全員について、その指導方法に問題があると主張していました。
そして、このままでは教職員は仕事ができず、指導担当を教職員側が希望する人物に変更することや、現在の指導担当者から教職員に対して謝罪をすることなどの要求をしていました。
そのため、弁護士が、当事者である指導担当者全員と、現場の状況をよく知っている現場責任者の方々から聞き取りを行いました。
弁護士が対面又は電話で、1人1人から聞き取りを行いました。その結果、教職員グループを主導している中心人物が誰であるかを確認することができました。
また、聞き取りを行った結果、指導担当者たちの言動にパワハラなどの問題はなかったことが確認できました。ただ、指導担当者らは学校に来てからまだ日が浅いこともあって、従来からの学校の慣例等を十分に把握できず、それから外れるような指導をしてしまったということはあったようです。
そういった些細なことをきっかけに、教職員側に指導担当者に対して不満を持つ者があらわれ、その者達が周囲を巻き込んで対立をあおり、最終的に教職員全体が学校側と対立するような構図になってしまったようでした。
(2)パワハラ問題に関する聞き取り
行き過ぎた指導であり、パワハラに当たると教職員から指摘を受けた場面については、学校の防犯カメラに映像が残っていました。
映像を見ると、指導担当者は終始穏やかに話しかけているだけで、パワハラと言えるような言動は一切ありませんでした。
ただ、指導が保護者からのクレームをきっかけとするものであったこともあり、指導を受けた教職員がストレスを感じ、体調を崩したことは事実でした。
映像の内容を踏まえて、弁護士から、パワハラに該当する事実はなく、指導担当者に対する懲戒処分等は不要であると学校側に報告をしました。
(3)教職員側への説明
1,弁護士が学校を訪問してパワハラに該当する事実はないことを説明
学校側から、調査の結果、パワハラはなく、指導担当者への処分や指導担当者の変更は行わないとの決定を、パワハラを受けたと主張している教職員に通知しました。
このようなパワハラ調査では、本来は、パワハラ被害を訴えている本人に結果を伝えればよく、教職員全員に報告する必要はありません。
しかし、一部の教職員がこの問題を大きくし、教職員全体と学校側の対立に発展していたため、パワハラ調査の結果、パワハラに該当する事実はなかったということを、教職員全員が参加する場でも説明をすることにしました。
当時、対立があおられていたこともあって教職員側は感情的になっており、学校側の説明を冷静に聞くことができる状態ではありませんでした。
パワハラに該当する事実はなかったという教職員側の意向に沿わない結論を伝えると、たちまち激しい抗議が起こり収拾のつかない状況になってしまうことが予想されました。
そのため、第三者である弁護士から説明をした方がよいと考え、弁護士が学校を訪問して説明を行うことに決めました。
2,説明会の前にルールを確認させる
説明の場に大勢が参加する場合、誰もが好き勝手に発言をするとまったく話ができません。
そこで、教職員らが集まった場で、弁護士から最初に説明会のルールを伝えました。すなわち、まずは学校側の説明をするのでそれを最後まで聞いてもらうこと、その後に質問等がある人は挙手して1人ずつ話をしてもらうように伝えました。
その上で、弁護士から、パワハラ被害が訴えられた問題について、客観的なカメラ映像があること、映像からは反省を強制したり、体調不良であるのに学校側が配慮せずに放置したなどといった、教職員側が主張するような事実が確認できなかったことを説明しました。
そして、映像では、指導する側は終始丁寧な言葉使いで話をし、体調が悪いと感じたときには気遣う言葉をかけており、パワハラはなかったと結論付けたと伝えました。
その後、説明会の中で、教職員側から反論や質問が相次ぎましたが、人づてに聞いた不正確な内容を基にした発言がほとんどでした。
そのため、そもそも話の前提である事実関係が間違っていることを伝えて、パワハラはなかったと判断した学校側の結論は変わりませんと重ねて伝えました。
3,パワハラ問題を今後全体では扱わない旨を伝える
そして、本件のパワハラ問題については、被害を訴えた教職員本人とは引き続き話をしていくが、今後は教職員全体に対しての説明はしませんということを弁護士から伝えました。
これによって、パワハラ被害の訴えについて、訴えた本人とだけ話し合いをするという通常の状態に戻し、学校がこれ以上この問題について教職員全体に説明するなどして時間をかけることをしないで済むようにしました。
(4)今後の協議ルールの確認と適切な指導
本件では、学校と教職員の対立関係から、本来は個々人と話しあえばよいはずの、パワハラ被害の訴えや指導方法に対する不満への対応といった問題についてまで、学校側が教職員全体に説明し、協議せざるを得ないようになっていました。
このことが、本件の対立を深刻化させ、対応を難しくさせていた原因の1つになっていました。
このように、本来は個別で話をするべきことも、逐一、全体への説明をせざるを得なかったため、直接の事実関係を知らない部外者が、伝聞で誇張された不正確な内容をもとに意見をすることになり、混乱を生じさせていました。
学校側は、部外者からの間違った意見に対して、毎回前提が間違っていることを説明し、さらにその説明に納得してもらうよう説得する作業をしなければなりませんでした。
このように、中身の議論をする前の段階で時間がかかり、建設的な話し合いがなかなかできない状況になっていました。そこで、弁護士が学校に助言し、個々人の問題については、今後は当事者とのみ話をしていくことにしてもらいました。
また、教職員が指導担当者を無視している状況を改めるため、業務命令として、指導担当者の指示に従うことを命じることにしました。
教職員らには、正当な理由なく、単に好き嫌いで上司の命令に従わないことは雇用契約違反になることを学校側から説明しました。
このように、教職員らに今後の協議ルールを確認し、学校側の指示を守る義務があると伝えたことで、次第に現場の混乱もおさまり、業務がスムーズに回るようになりました。
すると、それまでなかなか本音を言うことができなかった教職員が、学校側に本音を言ってくれるようになりました。
彼らによると、本来最も優先すべき子供達が後回しになっていたそれまでの状況に、心を痛めていたとのことでした。このような声が表に出るようになったことで、学校への反発を主導していた教職員の影響力も弱まっていきました。
6,解決結果におけるまとめ
今回のケースでは、教職員の一部の者が学校側との対立をあおり、教職員側と学校側で二分されて対立する構図になってしまっていました。
ご相談があった時には両者の間で冷静な話し合いが難しい状態になってしまっていたので、弁護士等の第三者が介入しなければ、解決は難しかったといえます。
しかし、そのような事態にいたるまでには予兆ともいえる小さなトラブルが起こっていました。小さなトラブルの段階で学校側が適切な対応をしていれば今回の事態に至ることは防げたと言えます。
日々の運営の中で従業員に対してどのような指導をすべきか悩ましいことは多いと思います。日ごろから気軽に相談できる顧問弁護士がいると、トラブルが小さい段階で相談でき、サポートを受けることで、早期の解決が可能になります。
従業員への指導にお悩みの場合、できる限り早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
問題社員の指導方法については以下の記事でも解説していますのであわせてご参照ください。
また、学校法人における顧問弁護士の役割については、以下をご参照下さい。
7,咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「労働問題に強い弁護士への相談サービス」への今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績&お役立ち情報
今回は、「教職員が集団で上司に詰め寄り、逆パワハラが生じていた学校から弁護士が相談を受けて解決した事例」について、ご紹介しました。
他にも、パワハラなど、今回の事例に関連した解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例
・パワハラ被害を受けたとして従業員から会社に対し300万円の慰謝料が請求されたが、6分の1の慰謝料額で解決した成功事例
また、パワハラについては、以下で詳しい解説記事を公開していますので参考にご覧ください。
・パワハラやハラスメントの調査方法について。重要な注意点を解説!
・逆パワハラとは?正しい対策方法3つを解説します。
・部下からパワハラで訴えられた時、パワハラと言われた時の必要な対応
・パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点
・パワハラ発生時の加害者の懲戒処分について
 06-6539-8587
06-6539-8587






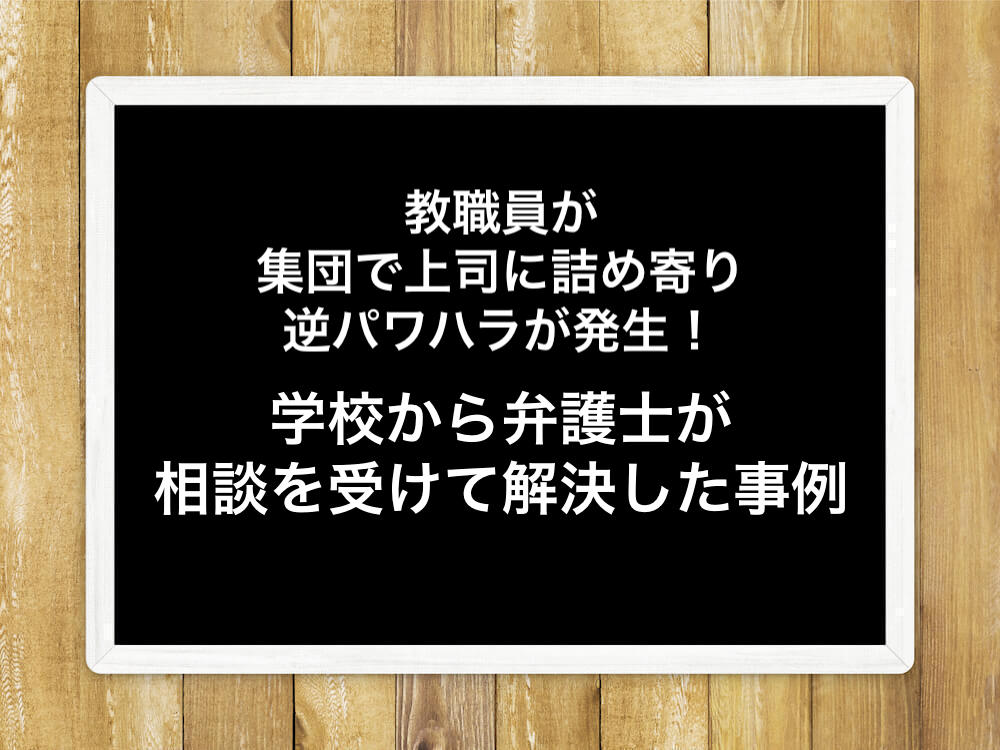

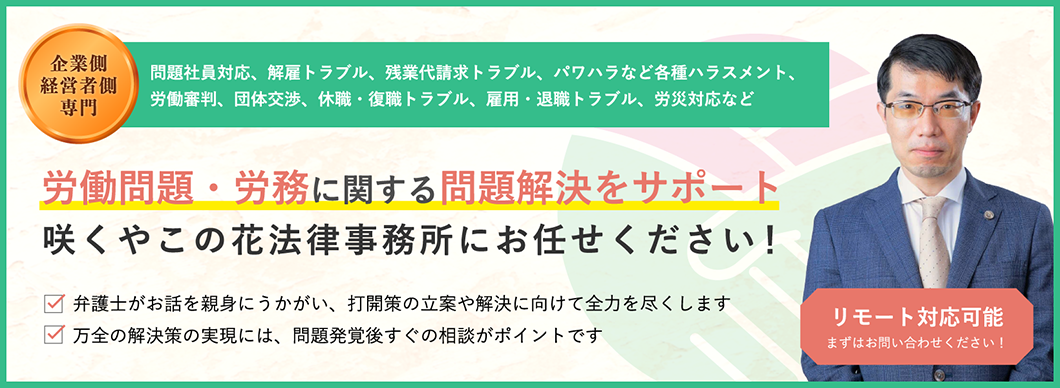
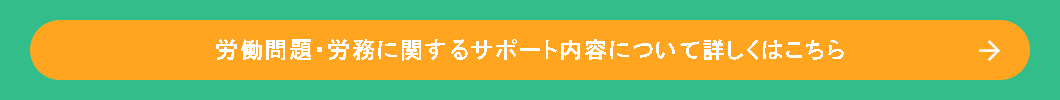
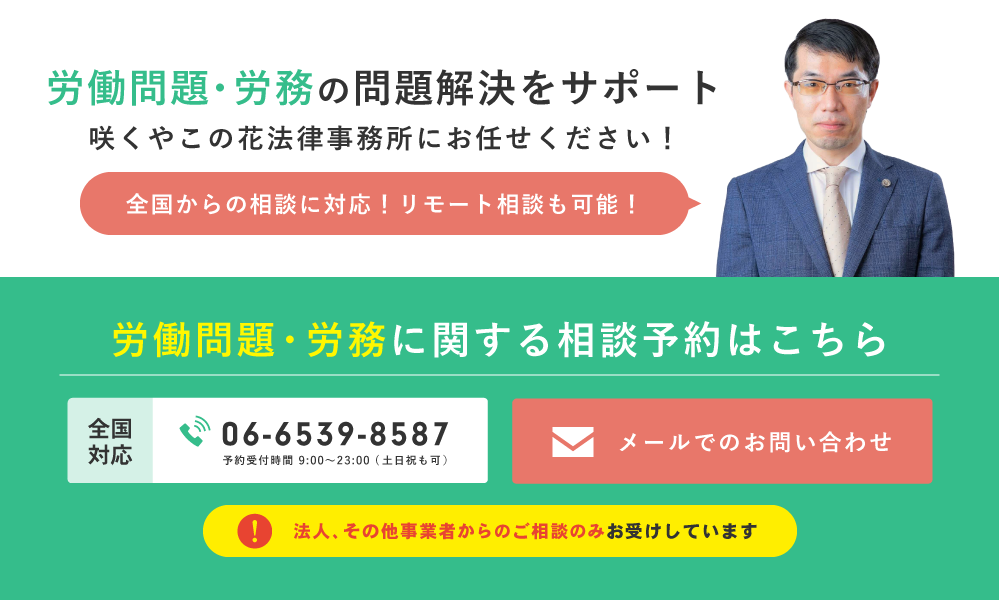
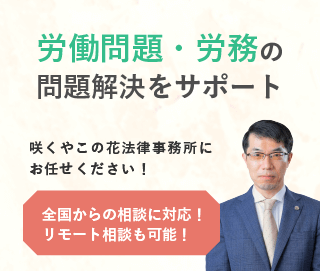





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















