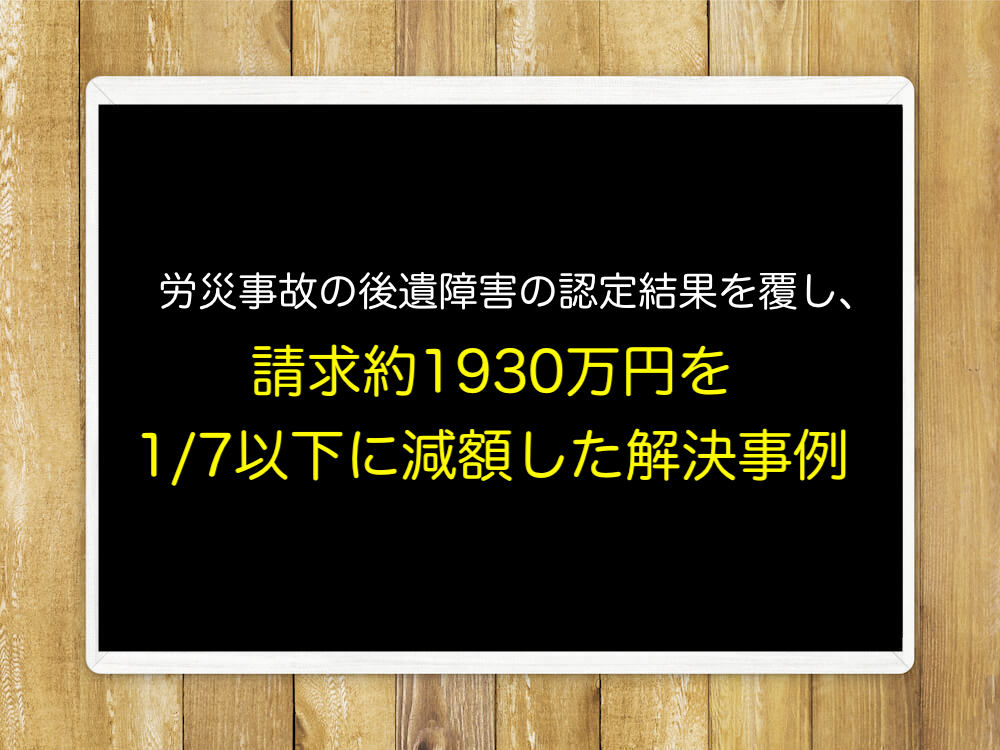
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 堀野 健一
出身地:大阪府岸和田市。出身大学:大阪大学。主な取扱い分野は、「労務・労働紛争の解決(従業員の解雇トラブルや従業員に対する退職勧奨、従業員からの残業代や未払賃金の請求)、不動産紛争の解決(不法占拠者に対する明渡の交渉・裁判・強制執行、賃料の回収、土地の境界の特定など)、システム開発紛争の解決、クレームの解決、就業規則・雇用契約書のチェック、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「鋼鉄加工業」の事例です。
2,事案の概要
本件は、玉掛け(クレーンで物を吊り上げること)資格の有資格者であった元従業員が、業務中、クレーンで吊り上げていた鋼材を足の上に落として怪我をした労災事故の事案です。
元従業員はこの事故により後遺障害等級11級という重い後遺症が残ったとして、会社側の安全配慮義務違反を理由に約1930万円の損害賠償を求め、会社に対して訴訟を起こしました。
元従業員側の弁護士は事故が起こったのは会社の安全教育や注意指導に問題があったためであると主張していました。
しかし、元従業員は会社の指導に背いた方法で作業しており、自らが大変危険な行為をした結果、事故が起きてしまった、というのが事実でした。
ただ、裁判所は労災事故が起こった以上、従業員の落ち度が非常に大きい場合でも、会社に対して賠償を命じることが通常です。そのため、事故後、会社は裁判に発展した場合のリスクも踏まえて一定の譲歩を示しつつ、交渉で解決するよう努めました。
しかし、結局、元従業員側が自分の主張を曲げず、交渉での解決には至りませんでした。そして、元従業員が訴訟を提起してきました。
(1)労災事故の概要
元従業員が、長さ10m、重さ930㎏の鋼材を1本のワイヤーで吊り上げ、かつ、鋼材の下に入ってリモコン操作をして鋼材を運んでいたところ、鋼材を置く予定のコンベヤ上のローラーに鋼材の端が当たりました。それによって、鋼材のバランスが崩れ、元従業員の左足の甲の辺りに落ちた、という事故でした。
それにより、元従業員は左中足骨骨折の怪我を負いました。
長尺の鋼材を1本のワイヤーで吊り上げることや吊り上げた鋼材の下に入ることは、危険であるため、禁止されています。玉掛け作業をする者であれば常識であるし、玉掛け資格を持っている元従業員であればなおさらのことで、当然知っているはずでした。
元従業員は、労災の認定を受けて、治療を継続し、約1年間の治療ののち、後遺障害申請を行い、後遺障害等級11級に認定されました。
3,問題の解決結果
裁判では、元従業員の認識や主張が誤っていることを指摘し、会社が安全配慮義務を果たすために行っていた安全対策を具体的に説明しました。
また、元従業員が通院していた病院のカルテと労災の調査復命書を取り寄せることにより、約1年もの治療が必要になる怪我ではないことを主張して、従業員の主張に反論しました。さらに、後遺障害の程度は、従業員が主張する内容よりも軽いことを裏付ける医療鑑定を証拠として提出しました。
これにより、裁判所から当方の主張を踏まえた和解内容を提案され、結果、約1930万円の請求から大幅に減額した270万円を支払うことで和解を成立させることができました。
4,問題の解決における争点(弁護士が取り組んだ課題)
本件の争点は、以下の3点でした。
- ●争点1:会社の安全教育や注意指導に問題があったのか
- ●争点2:治療期間は本当に1年も必要だったのか
- ●争点3:後遺障害等級11級の認定は妥当なのか
以下で詳細を解説します。
(1)会社の安全配慮義務違反の有無と元従業員の過失
▶元従業員の主張:
会社から、鋼材をワイヤー1本で吊り上げる方法(1本吊り)で吊るようにするように言われていた。安全に関する会社からの指導は一切なく、会社側は従業員の危険行為を放置していた。
▶会社の主張:
1本吊りで吊るように指示したことはない。
これは、会社に安全配慮義務違反があったかどうかにかかわる争点です。
労働安全衛生法により、会社にはさまざまな安全対策が義務付けられています。会社が従業員に対してきちんと指導・安全管理を行っていたのかということが問題になるので、当時の会社の安全対策を確認して、事実に基づく反論をすることが大変重要です。
本件では、元従業員による会社の安全配慮義務違反の主張を全面的に争いました。
(2)治療期間
▶元従業員の主張:
約1年の治療期間は必要だった。実際に治療に約1年間かかった。
▶会社の主張:
治療期間は5か月が妥当である。
治療期間は休業補償の額や慰謝料の額に影響する争点です。
治療期間が長ければ、休業補償をしなければならない日数が増えますし、慰謝料も高くなります。治療期間について適切な反論をするためには、カルテなどの治療記録から、主治医がどのように考えて治療を行っていたのかを読み取ることが重要です。
会社は、1年もの通院期間は必要ないと考えて争いました。
(3)後遺障害等級の認定
▶元従業員の主張:
労災認定の結果に基づき後遺障害等級11級と主張。後遺障害により、足指と足首の関節の動く範囲(可動域)が通常より制限されている。
▶会社の主張:
労災の認定した後遺障害等級に誤りがあり、14級程度である。
労災事故による後遺障害は、その程度に応じて1級から14級という等級が認定されます。
この等級は数字が小さいほど障害が重く、本件の元従業員は労災において11級という比較的重い等級が認定されていました。この後遺障害等級は労災の損害賠償額(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)に大きく影響します。
損害賠償額のうち大きな部分を占める後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は、認定された後遺障害等級が重くなればなるほど高くなります。11級であれば1900万円を超える元従業員の請求もおおむね妥当とされる余地がありました。そのため、国(労災)が認定した後遺障害等級をくつがえすことが賠償額減額のための大きなポイントでした。
そして、後遺障害等級についての反論は、元従業員が通院していた病院の「カルテ」と、「調査復命書」という労働基準監督署が作成する調査内容を記した書面の両方を精査して行うことが重要です。
担当弁護士としては、国の労災認定は誤りであり、本件では最も軽い後遺障害等級である14級程度が妥当と考え、全面的に争いました。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の見解について解説していきます。
(1)労災認定と安全配慮義務違反
国の労災認定は、会社側の安全配慮義務違反の有無に関係なく行われます。つまり、「労災認定された=会社側が従業員に対し賠償責任を負う事が認められた」、というわけではありません。
本件では、会社の安全配慮義務違反について全面的に争う方針でしたので、会社の主張を裏付けるため、会社側が安全配慮義務を尽くしていたこと、元従業員の落ち度が相当大きい事を、具体的かつ丁寧に説明していく必要がありました。
ア:安全配慮義務を尽くしていたかどうか
工場や建設現場など、従業員が危険な機械を操作する業務を行っている会社では、安全配慮義務を果たすため、以下の点を遵守しなければなりません。
- ●安全な機械操作の説明、安全研修の実施
- ●会社から従業員への十分な指導
- ●安全な労働環境を整える
- ●従業員の安全について定められた法令等の遵守
当然ですが、会社は法令を遵守しています。
また、会社からは危険な方法で鋼材を吊り上げるような指示は行っていませんでした。また、工場内の整理整頓を心がけるよう日頃から指導を行っていました。
加えて、身体の安全が第一であることを従業員に伝え、危険な行為をしている従業員に気付いたときは、会社がその都度注意し、正しい機械操作を行うよう指導もしていました。
さらに、労働環境面で言えば、従業員が吊り荷の下に入ることなくクレーン操作が出来るように、無線のリモコンを導入していました。
裁判所に対しこれらを具体的に説明し、会社側は十分な指導、教育、設備の導入を行っていたのだから、今回の事故は会社の安全配慮義務違反というよりは元従業員の落ち度によるものであることを主張しました。
安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
イ:元従業員の落ち度
元従業員が玉掛け資格の有資格者でした。しかも、前職で同じメーカーの切断機の操作経験もありました。
有資格者というのは、クレーンの基本的な操作方法や禁止事項、注意点等を熟知しているはずです。つまり、前提として、会社からのこと細かな指導が無くても、危険行為を行うことはないはずですし、会社も危険行為を行うという想定をそもそもしていません。
今回、元従業員は、長尺の鋼材を1本吊りしました。しかも、吊り上げた鋼材の下に立ち入っています。長尺の鋼材を1本吊りすることや吊り上げた鋼材の下に立ち入ることは、危険であるため禁止されていますが、玉掛け資格の技能有資格者である元従業員であれば、当然知っているはずのことでした。
また、元従業員が会社に入社した際、会社が切断機操作方法を説明しようとしたところ「知っています」と説明不要であることを自ら申し出ていました。これも、機械の操作経験が豊富であることを裏付ける言動です。
本件では、有資格者で、かつ、機械の操作経験が豊富なことを前提として採用された元従業員の今回の行為(長尺の鋼材を一本吊りし、かつ、積み荷の下に立ち入った行為)は、会社が使用者として危険を回避するために必要な予測の範囲を超えるものであり、会社に安全配慮義務違反はない、と主張しました。
(2)労災の認定を争う
労災認定において長い治療期間や、重い後遺障害等級が認定されたからといって、必ずしもその認定結果を前提に賠償に応じなければならないというわけではありません。
本件で、担当弁護士は、労災が認めた治療期間・後遺障害等級について誤りであるという反論を行う余地があると判断しました。
会社側で行う反論の裏付けとなる点がないかを検討するのに重要なのは主治医の「カルテ」です。カルテを丁寧に精査すると、主治医がどのように治療経過を見ていたのかを読み取ることができ、反論の糸口をつかむことができます。
ア:治療期間について
労災事故で受傷したとしても、治療を希望すれば延々と治療を受けることができるというのは本来適切ではありません。治療を受けても症状の改善が見られない、いわゆる「日にち薬」となった段階で、それ以上治療しても意味がありませんから、治療は終了とすべきです。
このように治療をしても症状の改善が見られなくなった状態を「症状固定」といいます。
弁護士が、会社側の反論を構成するにあたって着目したのは、カルテの中で主治医が症状固定について触れている点が無いかどうかということでした。そうしたところ、元従業員のカルテには、事故発生日から約5か月経過した頃に、主治医が症状固定(治療終了)時期について触れている記載があり、「症状固定」と明記され治療をいったん中止とする旨も書かれていました。
そこから、主治医は通院治療は事故から5か月程度までが妥当と考えていたと推測し、裏付けとなる記載が無いか、カルテをさらに精査しました。
すると、事故から半年経過して以降、カルテの記載も「異常なし」や「リハビリ(実施)」など、同じ内容の繰り返しになっており、すでに日にち薬の段階になっていたことが主張できると考えました。
裁判ではこの点を指摘し、1年もの治療は本来必要ではなく、妥当な治療期間は5か月程度であった、と主張しました。
イ: 後遺障害等級について
後遺障害等級が何級かということは損害賠償額に非常に大きく関わる点になります。
すでに、国(労災)によって、後遺障害等級11級が認定されており、元従業員が有利な立場にありました。会社側による反論のためにはまず、「なぜ労災が後遺障害等級を11級と判断したのか」、を確認したうえで、それが誤りであることを指摘する必要がありました。
元従業員の後遺障害は、足指と足首の関節の動く範囲(可動域)が怪我をしていない側の足と比べて大きく制限されていると判断されたことが理由でした。このような労災の後遺障害調査は地方労災医員により行われます。そして、地方労災医員が診断した内容は「調査復命書」から確認することができます。
本件の調査復命書を精査したところ、元従業員の足指と足首の怪我をしていない側の可動域の測定数値が、健常な人の可動域角度よりも大きく曲がる内容になっているなど、かなり不自然な数値になっていました。加えて、この復命書の可動域測定数値と、元従業員が通院していた病院のカルテに記載された主治医測定の可動域測定数値とが大きく異なっていました。
そのため、可動域の測定結果については、疑問を差し挟む余地が十分にあると判断し、この可動域の測定結果の不自然性を裁判所にアピールしました。
また、会社は、第三者の専門医に意見を求める医療鑑定も行い可動域制限を生じるような怪我でないことの裏付けを取り、証拠として提出しました。
これらを踏まえ、足指と足首に可動域制限は生じていないことを主張しました。そして、元従業員の後遺障害は痛みやしびれ程度のものであり、それはレントゲン等の画像によって証明ができない神経症状であるため、最も軽い後遺障害である14級相当にとどまるものであることを主張しました。
6,解決結果におけるまとめ
本件は、訴訟を起こされてから和解成立まで1年9か月かかりました。交渉期間も含めると、約2年4か月にもなります。カルテの嘱託開示やカルテの反訳、医療鑑定など、時間と費用がかかり、会社側の負担も決して小さく無かったと思います。
ただ、妥協せず事実関係を突き詰めて裁判で主張した結果、治療期間の点、後遺障害の点で、事実上、国の労災認定が誤りであったことが認められた内容の和解案が裁判所から提示されました。
和解案は、治療期間5か月、後遺障害等級は14級であることを前提に従業員の請求額(約1930万円)を大幅に減額し、270万円という内容でした。
裁判所からは、元従業員の過失の点についても、会社側の主張を相当考慮してもらうことが出来ました。このような結果に依頼者にも大変喜んでいただくことが出来ました。
余談ですが、裁判終了後、会社では、従業員が危険な行為をしないように、改めて周知するための文書を作成することになり、咲くやこの花法律事務所にて、この文書の作成のサポートをさせていただきました。
本件でも明らかなように、国から労災認定されたからといって、必ずしも、それをそのまま受け止めて賠償に応じる必要はありません。
事実関係を精査し、証拠に基づいて、反論の余地がないかを検討することが重要です。また、会社が従業員に対して行った研修や指導について、記録を取るなど形に残すこともトラブル防止に役立ちます。
従業員の労災事故についてお困りの際は、是非、労働問題の実績と経験が豊富な咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。
労災の損害賠償請求については以下の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。
7,咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士への今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】労災におけるお役立ち情報
今回は、「労災事故の後遺障害の認定結果を覆し、請求約1930万円を1/7以下に減額した解決事例」についてご紹介しました。自社で労災関連の事案が発生した際に知っておくべき必要がある基礎知識については、以下のお役立ち情報も参考にしてみてください。
▶参考情報:労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ
▶参考情報:労災の休業補償の会社負担分についてのわかりやすい解説!
▶参考情報:会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について
▶参考情報:労災認定されると会社はどうなる?会社側弁護士が解説
▶参考情報:労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?
▶参考情報:労災認定基準についてわかりやすく解説
▶参考情報:労災で労基署からの聞き取り調査!何を聞かれるのか?
 06-6539-8587
06-6539-8587






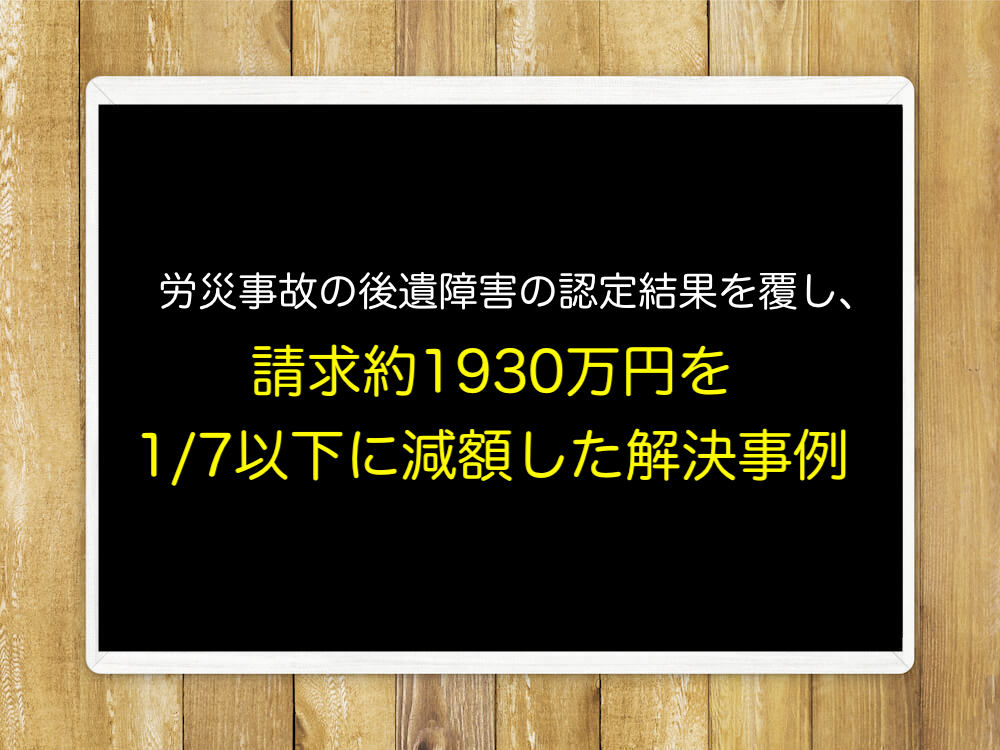

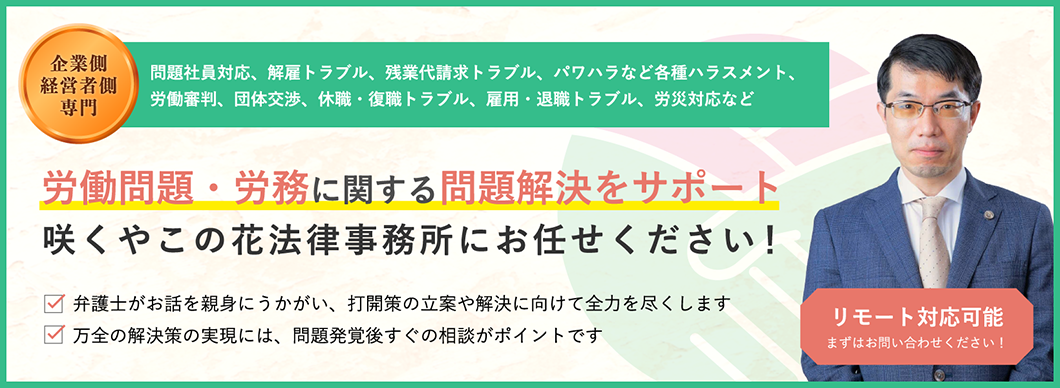
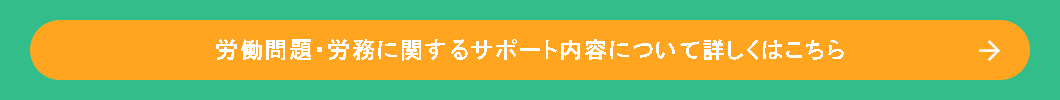
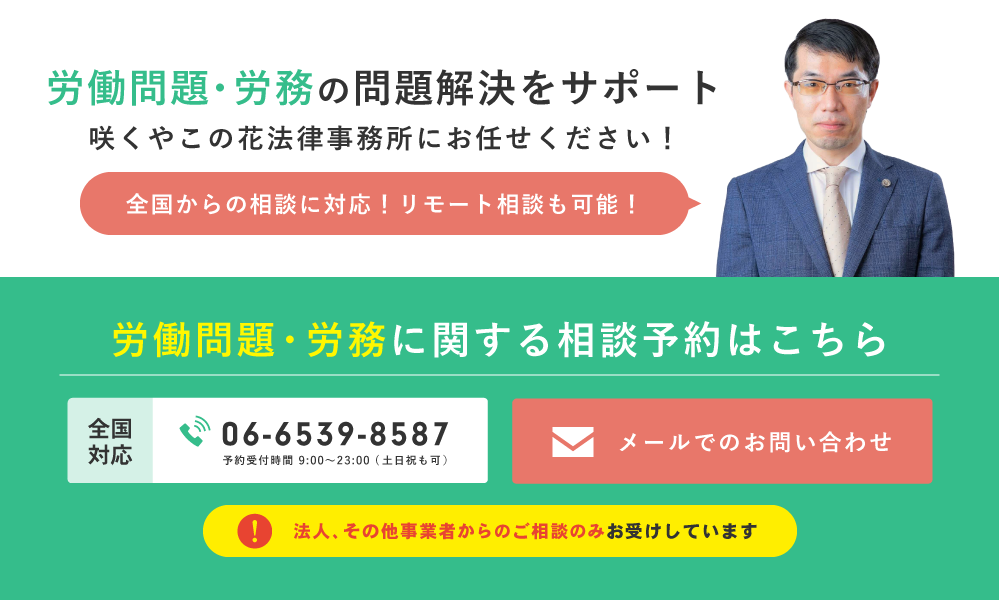
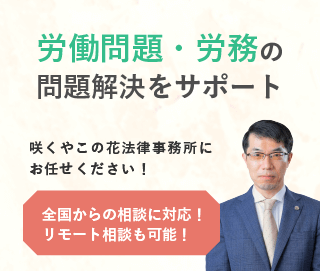





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















