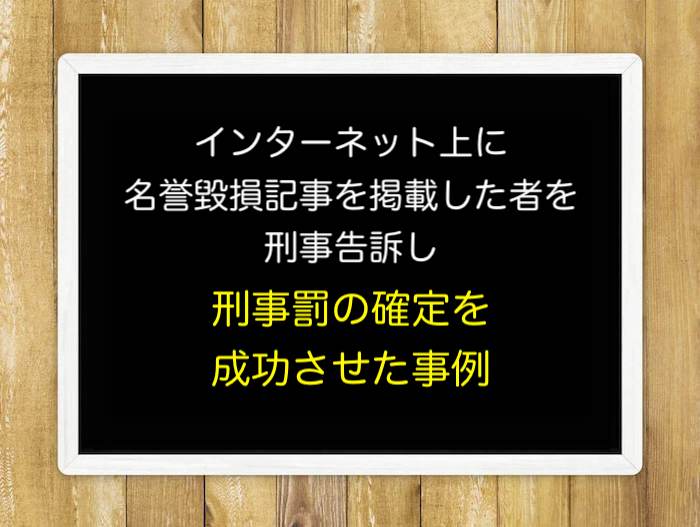
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 渕山 剛行
出身地:北海道札幌市。出身大学:大阪大学法学部法学科。主な取扱い分野は、「著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法、労務・労働事件(企業側)、債権回収、インターネット上の違法記事の削除請求、発信者情報開示請求、歯科医院関連、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
業種:広告配信、ウェブコンテンツ制作等
2,事件の概要
本件は、相手方がFC2ブログやAmebaブログなど複数のブログに、依頼者が詐欺行為を行っているなどと記載した記事を掲載した事案です。
事案の詳細は以下のとおりです。
依頼者の元仕事仲間だった者が、自らが運営するブログに、依頼者の氏名を明示した上で、概ね以下の内容を記載した記事を20個以上掲載していました。
- ●1,依頼者は詐欺行為を行っている
- ●2,依頼者は他人に平気で嘘を言う人間である
- ●3,依頼者は配偶者以外にも複数人と男女関係を持っている
記事が掲載されたブログは複数あり、全てのブログに同内容の記事を掲載していました。
掲載された記事の内容は事実とは異なるものでした。上記の他にも、依頼者の家族への誹謗中傷も記載されていました。複数のブログそれぞれに数十個もの誹謗中傷記事を掲載されたため、依頼者は、ひどい精神的苦痛に悩まされていました。
なんとかしてこのような状態を是正して欲しいとの思いで、咲くやこの花法律事務所に相談に来られました。
3,問題の解決結果
弁護士が告訴状を作成して警察署に提出し、告訴を受理してもらうことに成功しました。その後、ブログ記事を掲載した者に名誉毀損罪による刑事罰が科されました。依頼者の名誉を毀損するすべてのブログ記事の削除にも成功しました。
4,問題解決における争点(弁護士が取り組んだ課題)
以下では、問題解決において弁護士が取り組んだ課題について詳しく解説していきます。
(1)誹謗中傷記事に対しては適切な法的手段の選択が重要
インターネット上に誹謗中傷記事が掲載された場合、大きく分けて以下の4つの法的手段を取ることができます。
- ●1,書き込んだ人物を特定する「発信者情報開示請求」※1
- ●2,書き込んだ人物に対する「損害賠償請求」
- ●3,書き込まれた記事を削除する「削除請求」※2
- ●4,書き込んだ人物に刑事罰を与えることを求める「刑事告訴」
※1:「発信者開示請求」について詳しくはこちら
※2:「インターネットの誹謗中傷や名誉毀損記事の削除請求」について詳しくはこちら
●本件で刑事告訴を選択した理由
どのような手段が妥当かを念頭に置きながら、相談に来られた依頼者の話を聞き取ったところ、以下の事実が判明しました。
- ●1,記事を掲載した者(以下「相手方」といいます)の氏名・住所は既に判明している
- ●2,相手方は経済的に困窮しており、見るべき資産がない
- ●3,次々に新しい誹謗中傷記事を掲載し続けている。
これらの事実から、結論として、刑事告訴が妥当であるとのアドバイスをしました。
理由は以下の4点です。
- ●1,相手方は特定しているが、資力がないため、損害賠償請求をしても相手方に痛手がないこと
- ●2,記事の削除請求をしても新しい記事が掲載され続けて“いたちごっこ”になってしまう可能生が高いこと
- ●3,削除請求や損害賠償請求をするよりも、相手方に刑事罰を与えた方が、新たな書込みを防止できる可能性が高いこと
- ●4,名誉毀損罪が成立し、刑事罰が確定すれば、その結果をもって記事の削除請求を優位に進めることができること
(2)刑事告訴では告訴の対象とする記事の絞り込みが重要になる
誹謗中傷記事の掲載に対して刑事告訴をする場合には、その行為が名誉毀損罪や脅迫罪など、刑事罰の対象となる犯罪行為でなければなりません。
そのため、依頼者に誹謗中傷記事のすべてをピックアップしてもらい、それについて弁護士がどのような犯罪が成立するかについて検討を行いました。
●名誉毀損罪が成立するためには具体的な事実の記載が必要
名誉毀損罪が成立するために重要なのは、「人の社会的評価を低下させるだけの具体的な事実」が記載されていることです。具体的な事実を記載せず、単に相手方の依頼者に対する評価を記載しただけでは、名誉毀損罪は成立しません。
例えば、以下のような記載には名誉毀損罪は成立しません。
▶参考:名誉毀損罪が成立しない誹謗中傷の例
「~は、信頼できない人物だ」
「~はセコい」
「~は救いようのないバカ」
どのような内容であれば名誉毀損罪が成立するのかについては、過去の裁判例を踏まえた専門的な判断が必要です。そのため、名誉毀損罪が成立するかという観点から、弁護士が刑事告訴の対象とすべき記事を選定し、その内容が真実であるか否かについて、逐一依頼者と打ち合わせて確認を行いました。
(3)名誉毀損の刑事告訴は告訴期間に注意が必要
名誉毀損罪は、「親告罪」といわれ、刑事告訴をしなければ警察による捜査や刑事裁判による処罰が行われません。そして、告訴はいつでもできるわけではなく、名誉毀損罪のような親告罪の場合、告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。
本件では、最初の名誉毀損記事が掲載されたのが、6ヵ月以上前であり、依頼者は当初からその旨を知っていました。そのため、一部の記事については告訴期間が経過しているのではないかが問題となりました。
●告訴期間について弁護士から警察に説明することで告訴が受理された
結論として、本件では告訴期間は経過していませんでした。
裁判例上、「犯人を知った日」は、「犯罪行為終了後の日」で犯人を知った日と解釈されており、インターネット上の記事はその掲載がある限り犯罪が続いていることになります。
そのため、記事が掲載されている間は、犯罪は終了しておらず、告訴期間も経過しません。
この点は、告訴の受理に当たって、実際に警察官から告訴期間を経過しているのではないかとの指摘を受けました。告訴状の作成に当たって告訴期間の点は上記の通り検討済みでしたので、その旨を伝えたところ、すみやかに告訴が受理されました。
(4)弁護士が告訴状を作成した
上記の検討の結果、名誉毀損が成立する可能性の高い記事について告訴状を作成しました。
告訴状には法律上決まった方式はありません。そのため、告訴の要件を満たし、通常犯罪の捜査に必要な事実として以下のことを記載しました。
- ア 作成年月日
- イ 提出先の表示
- ウ 告訴人の氏名、住所(依頼者と代理人)
- エ 被告訴人の氏名、住所(相手方)
- オ 犯罪事実、罪名・罰条
- カ 犯罪の背景事情や経緯
- キ 犯人の処罰を求める意思表示
- ク 証拠資料の添付
●告訴状の作成に当たってのポイント
告訴状の作成に当たっては、特に上記「オ」と「カ」の記載がポイントでした。
上記「オ」では、犯罪事実を特定するために、「いつ、誰が、誰と、どこで、誰に対して、何をしたのか」について具体的に記載をしなければなりません。
本件では、名誉毀損罪に該当する可能性の高い記事だけでも1つのブログに20個近くがあり、さらに同内容の記事を掲載したブログが複数個ありました。
これらすべてについて上記犯罪事実の特定事項を記載すると、非常に犯罪事実の記載が読みにくく、冗長なものになってしまいます。
そこで、迅速に告訴受理をしてもらうため、告訴すべき記事を絞って記載し、読みやすくわかりやすい告訴状を仕上げることを心がけました。
以上のように、告訴状を作成するまでに、依頼者と弁護士が協力して、記事をピックアップし、名誉毀損が成立するかの検討・打ち合わせを繰り返し、わかりやすい告訴状を作成した結果、告訴状を警察署に提出してわずか1週間で告訴を受理してもらうことができました。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の見解をご説明しています。
(1)誹謗中傷記事に対抗するためには専門的な判断が必要
インターネット上に誹謗中傷等が掲載された場合にどのような法的手段をとるべきかの判断は、記事の内容、掲載方法・頻度、相手方の特定の有無、資力の有無など様々な事項を検討する必要があります。
それぞれの法的手段にも様々なメリット、デメリットがありますので、事案に応じて最も適切な方法を選択しなければなりません。
方法の選択には弁護士による専門的判断が必要です。本件でも依頼者から必要な事情を聴き取ったうえで、打ち合わせを行った結果、刑事告訴という手段を選択し、最終的に相手方に刑罰が科されました。
(2)迅速な告訴受理のためには、告訴状の作成がポイント
刑事告訴については、警察に告訴状を提出してもすぐには受理してくれず、なかなか捜査を開始してくれないという実情があります。
告訴状の不備や証拠不十分など様々な理由があるかと思いますが、ブログ記事の掲載行為に名誉毀損罪が成立するとして告訴する場合には、行為に名誉毀損罪が成立するのか否かの判断が難しい点が1つの理由であると思います。
名誉毀損罪が成立する範囲は一般的な感覚よりも狭く、法律に記載された要件をきっちり満たしていなければなりません。当然ながら、名誉毀損罪が法律上成立するものでなければ、告訴をしても警察は動いてくれません。
依頼者と弁護士が協力して名誉毀損罪が成立する記事を選定し、弁護士が作成する告訴状でわかりやすくこれらの点を警察に伝えることが迅速な告訴受理のためには重要です。
本件でも、告訴状の作成を綿密に行ったことにより、告訴状を警察署に郵送してから1週間で受理されました。
(3)告訴後も捜査状況の進捗確認が必要
告訴が受理された後も、警察がすぐに動いてくれるとは限りません。警察は常時膨大な数の事件をかかえているため、告訴が受理されてもなかなか捜査を進めないことがあります。
告訴をした後も、弁護士が随時捜査の進捗状況を確認し、警察に捜査の遅延は許さない姿勢を見せ続けることで、捜査が遅延しないようすることが重要です。
本件でも、弁護士が月1回程度警察に捜査の進捗を確認し、進捗内容を依頼者に報告しました。このことで、比較的早期に相手方に対して捜索差押えがなされ、送検、起訴、刑事罰の確定に至りました。
また、告訴後も警察の捜査期間中に相手方から新たな名誉毀損罪が成立するブログ記事が掲載されたことから、これらの点も弁護士を通じて警察に対して情報提供を行いました。
6,解決結果におけるまとめ
告訴状を郵送してから、1週間後に警察から連絡があり、告訴期間についての質問に回答後、告訴が受理されました。
その後、定期的な警察への進捗確認を行い、滞りなく送検、起訴、刑事罰の確定がなされました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなりました。
その後、刑事罰の確定等を根拠にして、依頼者らの名誉を毀損する記事のすべての削除に成功し(80個以上)、現在もその者からの書込みはありません。
7,誹謗中傷に強い咲くやこの花法律事務所の弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷や名誉毀損などに関するサポート内容は、「誹謗中傷に関する弁護士への相談サービスについて」のこちらのページをご覧下さい。また、お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回は、「インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰を確定させた成功事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した誹謗中傷トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・Google Mapに投稿された誹謗中傷のレビューの削除請求に成功した事例
・ヤフー検索のサジェストで表示された中傷ワードを削除依頼して非表示にした成功事例
・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例
・外部労働組合が記載したブログ上の誹謗中傷記事の削除と検索エンジンのキャッシュ削除に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






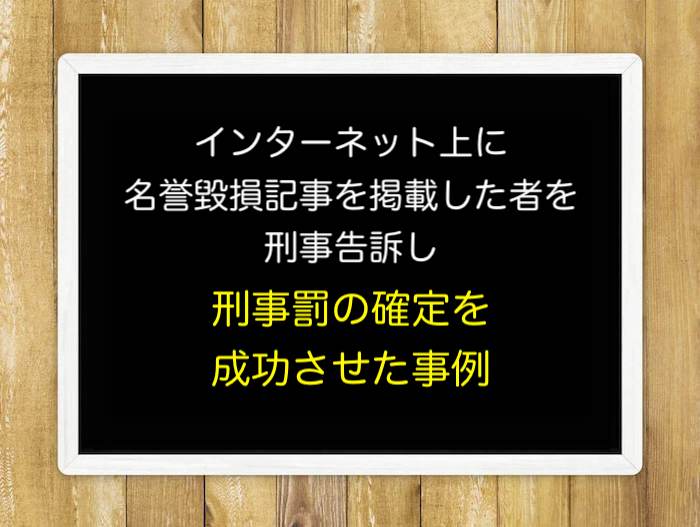

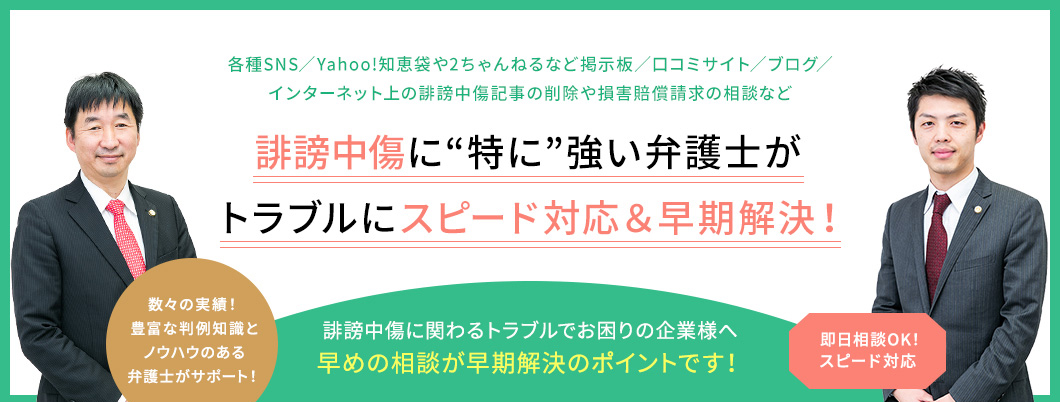

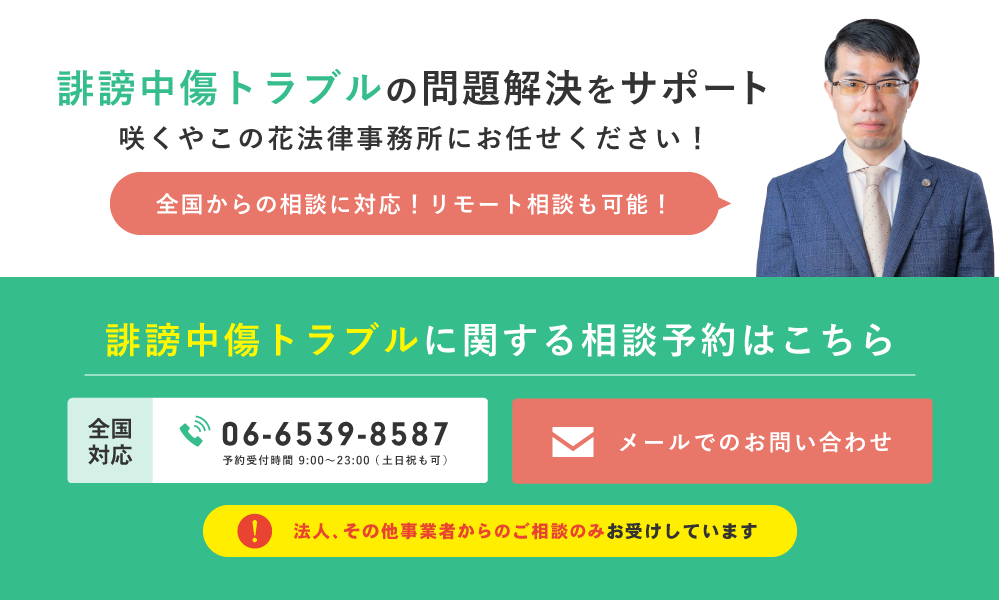
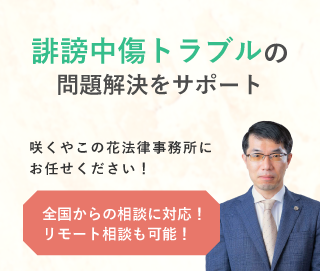





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















