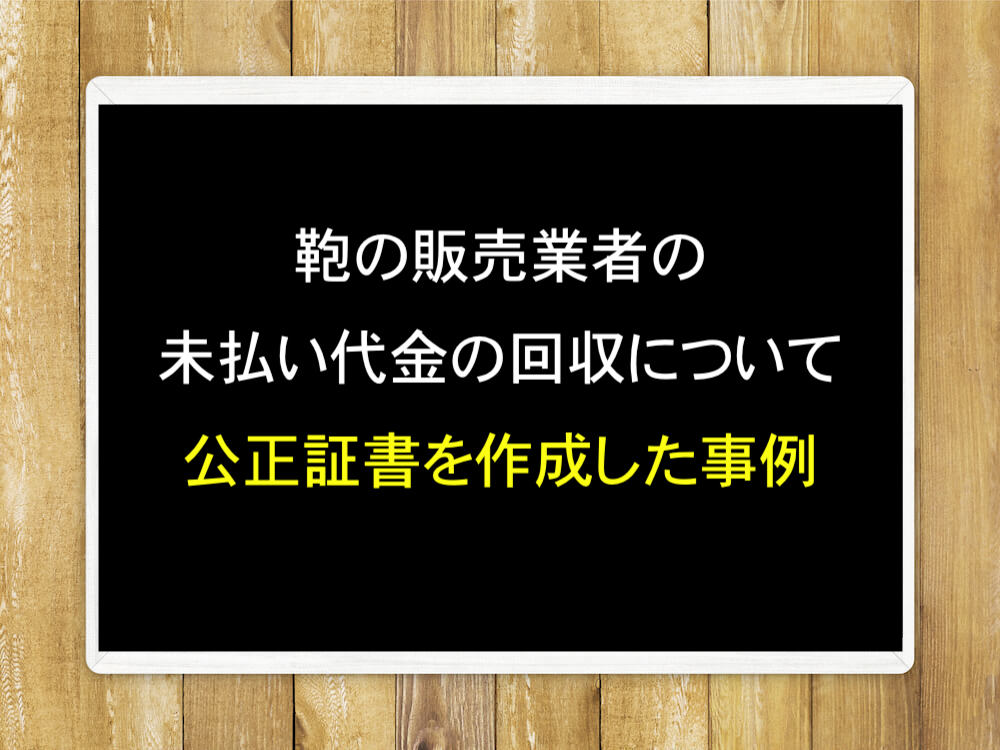
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 堀野 健一
出身地:大阪府岸和田市。出身大学:大阪大学。主な取扱い分野は、「労務・労働紛争の解決(従業員の解雇トラブルや従業員に対する退職勧奨、従業員からの残業代や未払賃金の請求)、不動産紛争の解決(不法占拠者に対する明渡の交渉・裁判・強制執行、賃料の回収、土地の境界の特定など)、システム開発紛争の解決、クレームの解決、就業規則・雇用契約書のチェック、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「卸売業」の事例です。
2,事案の概要
本件は、鞄の販売業者が、取引先に鞄を販売しましたが、その販売代金に未払いがあり、未払代金約230万円の支払いを求めた事案です。
販売業者と取引先とは3年ほど前から取引を開始しましたが、2年ほど前から取引先の代金の支払いが徐々に遅れるようになりました。そして、時間が経つにつれて、未払額は徐々に溜まっていき、2年で約230万円まで膨らんでいきました。
そうしたところ、取引先と連絡が取れなくなりました。
そこで、販売業者の代表取締役が、取引先の事業所及び取引先の代表取締役宅を訪れました。このとき、直接、取引先の代表取締役と話をして、その代表取締役から毎月3万円を返済していく旨の一筆を取りました。
その後、販売業者は、将来の支払いをきちんと受けることが出来るのか不安に感じ、回収の確実性を高めるために何かできることはないかと考え、弊事務所にお問い合わせいただき、ご相談にお越しになりました。
3,問題の解決結果
回収の確実性を高めるために、取引先と合意書を取り交わし、さらに、公正証書にて合意することも出来ました。
4,問題の解決における争点
以下では、本件に関する問題解決における争点について解説いたします。
(1)将来の支払が確保できるような合意書の取り交わしが必要
弁護士がご相談を受け、依頼者がもらってきた、取引先の代表取締役が作成した「一筆」を確認すると、そこには、毎月3万円を支払っていくという内容しか書かれていませんでした。将来の支払を確保する方法や支払いが遅れた場合のペナルティについて全く記載がなく、不十分な内容でした。
そこで、まずは、これらの点を記載した「合意書」を取引先と取り交わすことを目指しました。
(2)強制執行認諾文言付き公正証書の作成を提案
次に、上記のような「合意書」を取り交わしができたとしても、万が一、取引先が合意書に基づいた支払いをしない場合には、依頼者としては、財産の差押えなどの強制執行の申立てにより、回収をする必要があります。
もっとも、合意書を取り交わしているだけでは、すぐには強制執行はできません。まず、相手に対して裁判を提起して、裁判において勝訴判決を取った上で、その勝訴判決をもとに強制執行の申立てを行うことが必要になります。
その場合、裁判を提起して勝訴判決を取るための期間として、最低でも数カ月の期間が必要となります。また、もし取引先が争う姿勢を見せた場合には、より長期間を要し、1年程度を要することもあります。
つまり、単に合意書を取り交わしているだけでは、取引先が支払いをしないときに直ちに強制執行の申立てすることが出来ません。
しかし、そのような時間をかけていると、強制執行のベストタイミングを逃してしまう可能性があります。
このような場合、単に合意書を作成するだけでなく、公正証書による合意もしておけば、取引先が支払いをしない場合には、裁判などの手続を踏まなくても、直ちにその公正証書をもとに強制執行を行うことが可能です。このように直ちに強制執行ができる公正証書を「強制執行認諾文言付き公正証書」といいます。
本件では、これまでの経緯も踏まえ、合意書に基づく支払いがされない場合に備えて、強制執行執行認諾文言付き公正証書を作成することを依頼者に提案しました。
5,担当弁護士の見解
上記の各争点について、以下の点を検討しました。
争点1:「合意書の取り交わし」について
1,合意書案を弁護士が作成
まず、取り交わす合意書の案を弁護士が作成しました。将来の支払を確保する点や支払いが遅れた場合の対応の点について配慮した内容としました。
具体的には、毎月何日までにいくら支払うのかということに加えて、「(1)未払代金が総額でいくらであるのか」、「(2)支払いが遅れた場合にどうなるのか」、等を明記するようにしました。
(1)未払代金総額を明示して立証の負担を減らす
前述の通り、取引先(債務者)が支払いをせず、裁判が必要となった場合、裁判では想像以上に様々なことを立証することが必要になります。
例えば、取引先との基本契約や個別契約の内容、商品を納品したこと、納品日、納品した個数、納品した代金額などを、過去にさかのぼって1つずつ立証していくことが必要になり、その証拠の確保は相当の負担になります。
しかし、債務者との合意書において、未払代金総額がいくらであるかを明示して、その総額を債務者に認めさせておけば、万が一、裁判が必要になったときも、上記のような立証をしなくて済み、スムーズに勝訴判決を得やすくなります。
そのためには、合意書において、以下のように、債務の総額を明示することが重要です。
▶契約条項例:甲が依頼者、乙が取引先
「乙は、甲に対し、売掛金支払債務として、〇〇万円の支払義務があることを認める。」
(2)期限の利益喪失条項を設ける
取引先に対して代金の分割払いを認める場合は、支払が遅れた場合は直ちに全額を支払う義務を負うということを必ず合意書の中に入れておくことが必要です。このような条項を期限の利益喪失条項といいます。
この条項が入っていないと、分割払いの支払いが遅れたとしても、支払いが遅れている分のみしか請求することが出来ません。
▶参考例:
例えば、4月末と5月末を期限とする支払いがない場合には、将来にわたっても支払いがされない見込みも十分あると思いますが、期限の利益喪失条項がないと、6月時点で請求できるのは、あくまでその4月末分と5月末分だけとなってしまい、非常に不利益になってしまいます。
また、支払いが遅れた場合には、遅延損害金も請求すべきですが、これを民法で定められた利率(年3%)よりも高く設定しておくことが有効です。このように設定することで、支払遅延に対してペナルティを設け、取引先の支払いへのインセンティブを高めることが出来ます。
本件でも、合意書において、以下の通り、支払いが遅れた場合の対応を明示することにしました。
▶契約条項例:甲が依頼者、乙が取引先
「乙は、以下の(1)又は(2)の場合には、当然に期限の利益を喪失し、既払金を除く残債務を一括して支払うほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年15%の遅延損害金を支払う(1年365日として日割り計算を行う。)。
(1)分割払いを遅滞し、その遅滞額が○万円に達したとき
(2)乙が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、若しくは競売または破産の申し立てがあったとき」
2,合意書の取り交わし
作成した合意書を弁護士から取引先の事業所と取引先の代表取締役宅宛てに郵便で送付しました。そうしたところ、取引先に代理人弁護士が就任し、その弁護士から連絡がありました。
3,弁護士との協議
相手の弁護士に対しては、弁護士から「合意書を取り交わせないと、裁判をしていくことになる」旨等を伝えて交渉し、合意書の取り交わしの約束を取り付けました。
さらに、毎月の支払額の増額も要求しましたが、経営状況から難しい旨の回答がされたため、その話が本当かどうか確認するために決算書及び付属書類の提出を求めました。
そうしたところ、売上推移表の提出を受けることが出来、確かに売上が無いことは確認できました。そこで、毎月の支払額については、3万円のままという内容で承諾し、その他の点について、当方作成通りの合意書案の内容で了解させることができました。
争点2:「公正証書の作成」について
1,公正証書作成の約束を取り付ける
取引先の代理人弁護士には、「公正証書による合意が出来ないと、裁判をしていくことになる」旨等を伝えて、公証役場による合意を要求し、作成の約束を取り付けました。
公正証書による合意をするためには、公証役場で公正証書を作成することが必要です。さらに、取引先の代表取締役または相手方弁護士に出頭してもらうことも必要でした。
公正役場は、全国に点在しており、大阪であれば11か所あります。
裁判所のような管轄というものは無く、どこの公証役場で、公正証書を作成しても構いません。本件では、咲くやこの花法律事務所から最寄りの「本町公証役場」で公正証書を作成することとしました。
2,公正証書文案の作成
公証役場で公正証書を作成するにあたっては、事前に、公正証書の文案を作成しておく必要があります。
この文案を当事者双方があらかじめ確認しておくことで、合意内容を理解したうえで、公正証書の作成に臨むことが出来るようになります。また、弁護士が代理人として公証役場に出頭する場合に委任状が必要になりますが、その委任状に公正証書の文案を添付することが必要とされています。
今回は、取引先と取り交わした合意書があったので、これを公証人に提出し、公証人がそれをもとに公正証書の文案を作成しました。公正証書の文案が作成されたのち、弁護士が条項のリーガルチェックも行いました。
3,必要書類の用意
公正証書の作成に当たっては、必要書類が決められています。当事者が法人であれば登記事項証明書や印鑑証明書が必要です。
必要書類のうち、特に相手方の分については、相手方に必要書類を当日に持ってきてもらおうとすると、万が一、書類に漏れがあった場合に、公正証書の作成が出来なくなってしまいます
そのため、相手方には、可能な限り、事前に必要書類を郵送で送ってもらうと良いです。本件でも、取引先の登記事項証明書や印鑑証明書をあらかじめ郵送するように依頼し、事前に、送ってもらいました。
そして、これらを、当日、弁護士が公証役場に持参し、無事、公証役場にて、公正証書の作成が出来ました。
6,解決結果におけるまとめ
合意書の作成や強制執行認諾文言付き公正証書の作成については、いずれも、取引先に、作成に応じる法的な義務はありませんでした。
しかし、弁護士から取引先に書面で通知することや裁判を見越した交渉を行うことで、うまく合意書の作成や公正証書作成の約束を取り付けることが出来ました。
これにより、将来の支払の確実性が高まったとともに、万が一支払いが遅れたとしても、強制執行などスムーズな対応が可能になりました。
ご依頼をされる前の、「一筆」しかない状況に比べて、大きく有利な状況に持っていくことができました。未払代金の回収の問題でお困りの会社経営者の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「債権回収に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】債権回収テーマに関連した解決実績
今回は、「鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した債権回収の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・連絡不通の取引先から500万円回収!工場機械の仮差押えが決め手となった実例
・約束通り納品しない仕入先に対して代金返還を求めて裁判手続によることなく全額を回収した事案
・資力のない施主と粘り強く交渉して建築工事代金の全額回収に成功した解決事例
・配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
・相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
・施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例
・建設会社から債権回収のご相談を受けて、既に時効が完成していた工事代金について、一部回収に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






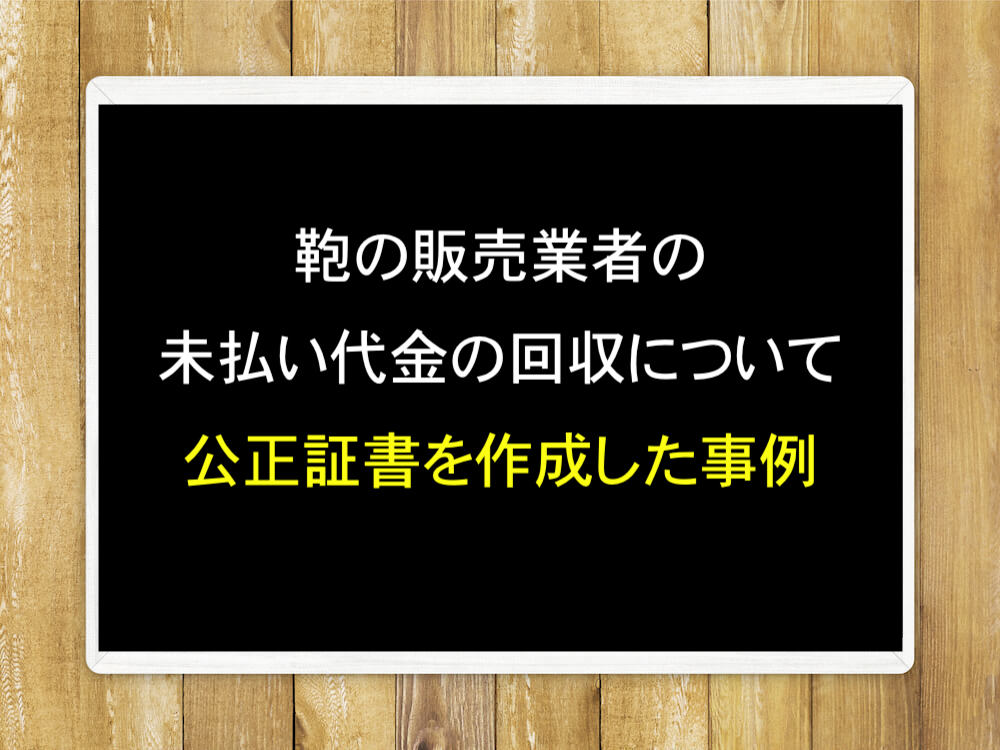

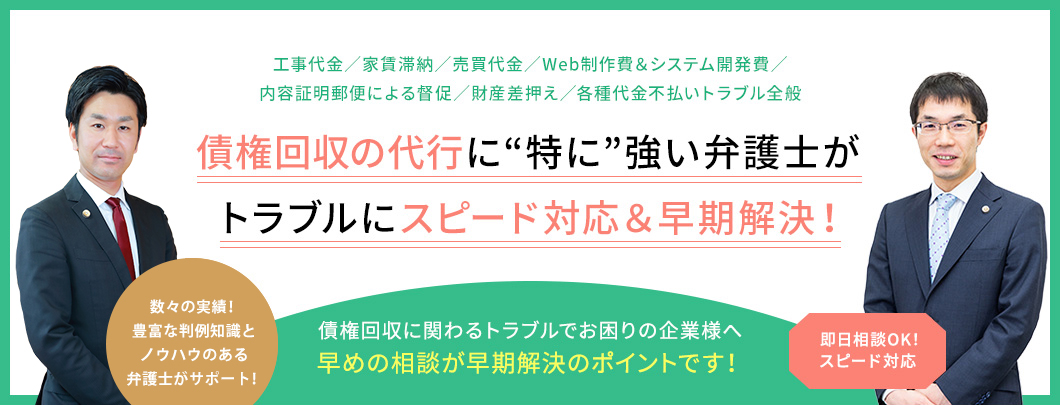
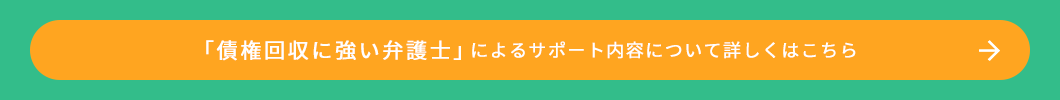
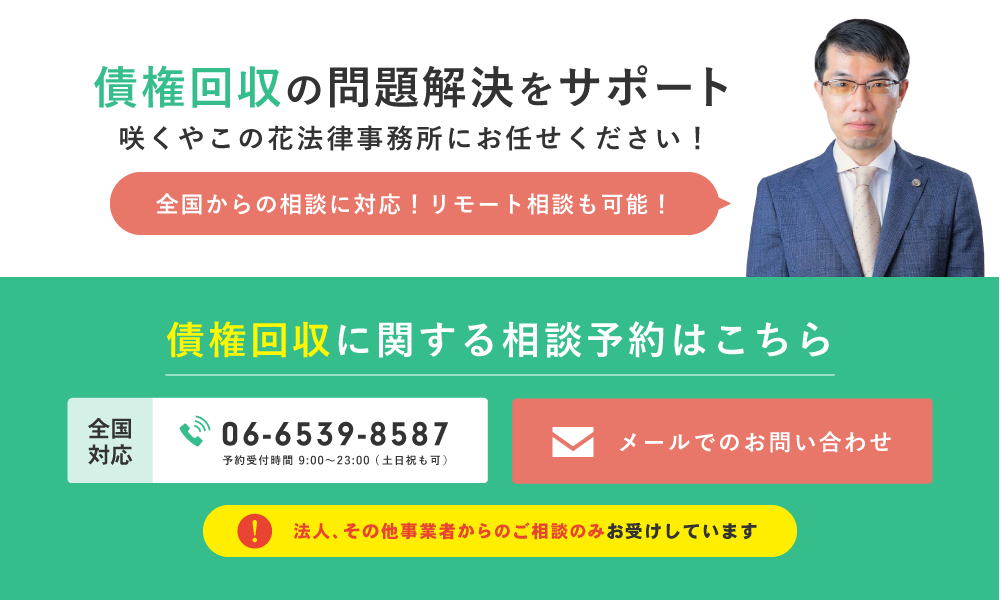






 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















