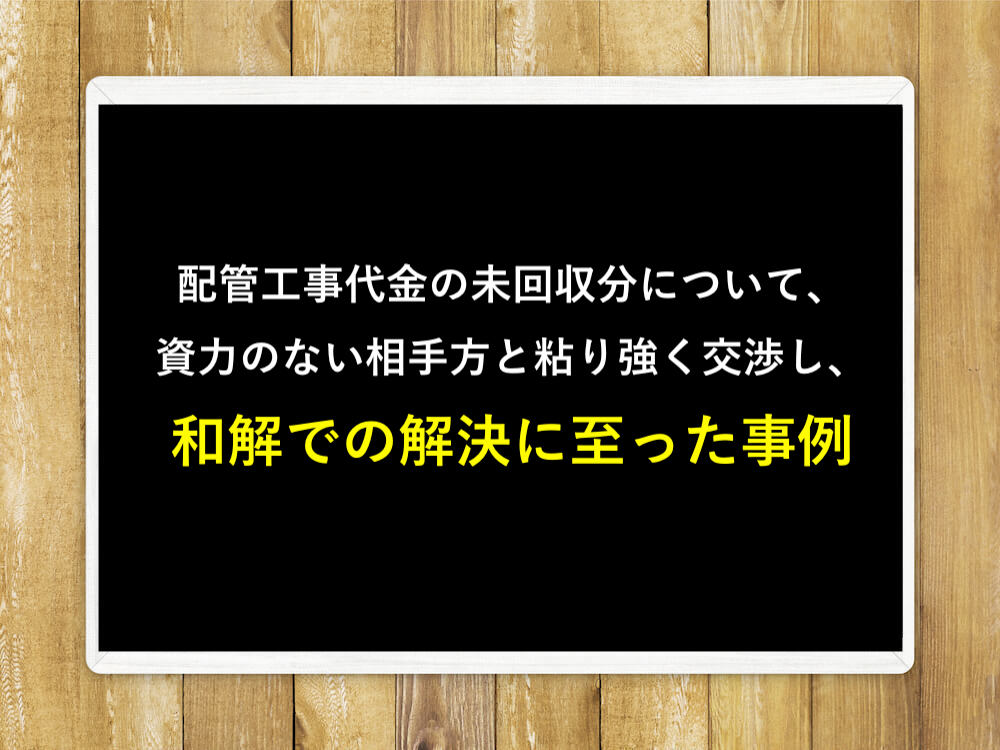
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 渕山 剛行
出身地:北海道札幌市。出身大学:大阪大学法学部法学科。主な取扱い分野は、「著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法、労務・労働事件(企業側)、債権回収、インターネット上の違法記事の削除請求、発信者情報開示請求、歯科医院関連、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「配管工事業」の事例です。
2,事案の概要
本件は、依頼者が施工を請け負った配管工事の工事代金について、本工事代金や、追加工事代金、材料費の立替分が当初の合意通りに支払われなかった事例です。
事案の詳細は以下のとおりです。
- ●1,依頼者(配管工事業者)は1300万円で配管工事(以下「本工事」といいます)を請け負いました。
- ●2,本工事の材料費は、注文者である相手方が依頼者に無償支給することになっており、依頼者が立て替えて購入したものは、購入費用を相手方が支払うことになっていました。
- ●3,その後、依頼者は、本工事に加えて、約30件ほどの合計700万円程度の追加工事も、相手方から依頼を受け、請け負うことになりました。
- ●4,工事完成間際に、相手方が、「本工事の代金は、1200万円だったはず」、「追加工事の内容は本工事代金に含まれている。追加費用は支払えない。」などと主張して、工事請負代金の一部しか支払わないとの主張をし始めました。
- ●5,依頼者は、相手方のこのような言動に請負代金が回収できないのではないかとの不安を覚え、咲くやこの花法律事務所に相談に来られました。
3,問題の解決結果
弁護士から相手方に対して未払い工事代金等を請求する内容証明郵便を送りましたが、相手方からまともな応答がなく、支払交渉ができませんでした。そのため、約800万円の請負代金を請求する訴訟を提起しました。
契約書がないことや、相手の資力に問題があることなど、大きな問題が複数ありましたが、粘り強い交渉の結果、400万円での和解により解決することができました。
4,問題の解決における課題(弁護士が取り組んだ課題)
以下では、本件に関する問題解決における課題について解説いたします。
(1)依頼者から工事の経緯を聴き取り、配管工事請負契約等の契約内容を特定
工事代金を訴訟で請求するためには、まずはどのような内容の請負契約が成立したのかを特定することが必要です。
一般的に以下の事項を具体的に明らかにする必要があります。
- ●1,工事の内容・期間
- ●2,工事場所
- ●3,工事代金
- ●4,代金支払日
- ●5,合意日
通常、これらの事項は工事請負契約書や注文書、注文請書によって特定することになります。
もっとも、本件では相手方が契約書の作成を拒んだなどの理由により、これらの書類が作成されていませんでした。
追加工事については、相手方から依頼者に注文書が差し入れられていましたが、工事内容が全くわからないものでした。
そのため、相手方への請求の為には、まずは依頼者がどのような請負契約をしたのかを特定することが必要でした。
本件の依頼者は、契約書や注文書を交わしていませんでしたが、依頼者自身の記録や依頼者が相手方に送った工事内容に関するメールが残っていました。
弁護士が、依頼者に対して請負契約の内容を特定する必要性を伝え、手持ちの資料に基づいて、依頼者に各工事1つ1つについて上記の「1,工事の内容・期間」~「5,合意日」の項目を整理した一覧表を作成してもらいました。
(2)契約内容を証明するための証拠を収集する
前述の通り請負契約の内容の特定を進めることと並行して、依頼者には契約内容を裏付ける根拠となる資料(証拠)が何かを特定してもらいました。
契約内容の主張を裏付ける証拠資料としては一般的には主に以下のものがあります。
- ●1,請負契約書
- ●2,見積書
- ●3,注文書・注文請書
- ●4,メール
- ●5,仕様書
- ●6,施工完了証明書
- ●7,設計図等の図面
- ●8,打合せ・交渉記録
- ●9,録音音声
このうち重要なものは、注文書などの相手方が作成した文書や、相手方の押印がある請負契約書など、契約内容について相手方の意思が読み取れるものです。
依頼者から、一方的に送りつけたメールや文書などで、相手方から返事がなく相手方が承諾したことの証拠がないものは、いくら大量にあったとしても、裁判では証拠としての価値が低いものと判断されてしまいます。
本件では、請負契約書や注文書等の決定的な証拠がなく、この点が非常に大きな問題点でした。
このような場合は、「4,メール」~「9,録音音声」のメールや打合せ記録、各種図面に加えて、その他あらゆる証拠を組み合わせることで、1つ1つの請負契約が成立したことを立証していく地道な作業が必要になります。
(3)依頼者と協力して証拠の整理を進める
本件では、まずは、依頼者に本工事の請負契約、材料費の立替払い契約、30個近くある追加工事等、1つ1つの契約について、これだと思う証拠を挙げていただきました。
その後、弁護士が、その1つ1つについて更に検討を加えました。
弁護士の検討では、裁判ではどのような資料をどのように組み合わせて主張することが有効かという観点から、必要証拠の洗い出しと組み立てを行いました。
例えば、1つの追加契約を立証するために、以下のような証拠を組み合わせて主張・立証していくこととしました。
- ●1,工事内容の明細の記載はないが、追加注文書という書面が相手から依頼者に提出されていること
- ●2,相手方から依頼者に差し入れられた文書に、工事内容の記載はないものの、「追加に関しては協議中である」旨の記載があったこと
- ●3,相手方から依頼者に差し入れられた文書に、工事内容は特定されていないが、「追加工事査定金額」という記載があったこと
- ●4,依頼者が立替払いをして購入した材料が追加工事に使われており、追加工事の費用の一部を相手方が支払っていること
- ●5,依頼者が、相手方の現場監督から追加工事の受領書をもらっていること
- ●6,依頼者が、相手方に対して追加工事の見積書をメールしていること
- ●7,工事現場での音声において、相手方が、本工事には追加工事の工事内容は入っていなかった旨を認めていること
このような証拠の整理作業を追加工事1つ1つについて丁寧に行っていきました。
(4)特定した契約をもとに、どの部分の代金が支払われていないを判断する
依頼者とともに、本件の契約内容を特定した結果、相手方との間で本工事契約、材料費の立替払い契約、約30個の追加工事契約が成立したことが明らかになりました。
そこで、次に問題となったが、どの契約の代金が未払いなのかを特定するということです。
本件では、工事期間中、相手方から各月末に一定額の支払いがありました。しかし、その支払金額は、当初の合意に満たない額でした。そのうえ、工事期間中に依頼者の立替払いや追加工事が次々と発生している中、相手方から毎月の支払がどの契約に対応する支払なのかの通知もありませんでした。
そのため、依頼者も、これまで支払われた金額がどの契約の代金に充てられるものなのか、わからない状況でした。
このように複数の支払うべき債務がある中、支払いの内訳が不明な場合は、民法の法定充当のルールが適用されます。具体的には民法489条4項に定められた以下の順番に支払われたものと扱われます。
- ●1,支払期日がきている債務と支払期日がきていない債務がある場合には、支払期日がきているものから順に支払われたものとします
- ●2,全ての債務が支払期日にある場合、又は全ての債務が支払期日にないときには、債務者にとって支払うことによる利益が多いものから先に支払われたものとします
- ●3,債務者にとってどの債務から支払われても利益が同じ場合は、支払期日が先に到来するものから先に支払われたものとします
- ●4,支払期日も、債務者にとっての支払いの利益も等しい場合には、支払額を各債務の額に応じて按分して支払われたものとします
本件では、弁護士が上記「3,債務者にとってどの債務から支払われても利益が同じ場合は、支払期日が先に到来するものから先に支払われたものとします」と「4,支払期日も、債務者にとっての支払いの利益も等しい場合には、支払額を各債務の額に応じて按分して支払われたものとします」のルールを適用すべきものと判断して算定したことで、法律上どの契約のどの部分が未払いなのかを特定することができました。
(5)訴訟を提起し、相手の反論に対して的確に対処する
工事代金を請求する訴訟では、1つ1つの工事ごとに相手方から様々な反論がなされます。
本件では、相手方から主に以下のような主張がなされました。
- ●1,本工事契約の金額は、1300万円ではなく、1200万円であったこと
- ●2,各追加工事は、1200万円の本工事に含まれていたこと
- ●3,依頼者が立て替えた材料費を相手方が支払う合意などしていなかったこと
- ●4,追加工事の注文書は、正式なものではなくこれを出さないと依頼者に工事を止められると思って出したものであること
- ●5,依頼者の工事には多くの不備があったため、「追加工事」とはその不備を修補するためのものであったこと
- ●6,相手方の現場監督には、追加工事を発注する権限がなかったこと
- ●7,依頼者の工事の不備のため、他業者に補修工事を依頼したのでその費用と、今回の工事代金を相殺すべきであること
この他にも細かい経緯等について多くの反論がありましたが、弁護士が依頼者に1つ1つ事実関係を確認し、これまで提出した証拠との関係や、新たに提出が必要な証拠を検討して再反論し、裁判を進めていきました。
(6)相手方の資力に問題がある場合でも粘り強く和解交渉を行う
訴訟提起後、何度も裁判で書面のやり取りをしたころに、裁判官から和解の提案がなされました。
これまでの弁護士の主張や、依頼者に裁判に出席してもらい直接裁判官に対して工事内容を説明してもらった点等が功を奏し、裁判官からは基本的にはこちらの主張を認める方向で考えていると伝えられました。
そのため、和解協議は、相手方が依頼者の請求金額に近い金額を支払う義務があるとの前提で進められました。
もっとも、相手方は、経営的に厳しい状況にあるとのことで、当初は100万円程度しか支払えない旨の回答をしてきました。
依頼者と弁護士で相談した結果、そのような金額では到底和解することができない旨を伝えました、そして、相手方に過去3年分の貸借対照表や損益計算書等の決算書に加え、総勘定元帳の提出を求めました。提出された決算書や総勘定元帳については、依頼者の税理士とも協力し、不合理な点を和解協議の中で指摘するなどして、何度も和解交渉の場が持たれました。
相手は、100万円から150万円に金額を上げるなど、大きく和解金額を上げてくることはありませんでした。
もっとも、これまで依頼者に有利に裁判を進めてきたために裁判官が強力に相手に金額を上げるよう説得をしてくれました。
このような状況であったため、依頼者としても譲歩をしつつも、強気の和解交渉を行うことができました。結局、和解協議は約半年ほど行われました。
相手の決算書には不合理な点がありましたが、経営状況が良くない点は明らかでした。そのため、仮に和解がまとまらずに請求額に近い金額を支払うような判決が出たとしても、支払いが期待できず、強制執行等をしてもいくら回収できるかは疑問があるというのが正直なところでした。
そのため、依頼者と何度も相談した結果、400万円での和解することに加え、相手方の会社代表者に連帯保証人になってもらうことで和解することになりました。
5,担当弁護士の見解
ここからは、担当弁護士の見解についてご説明していきます。
(1)請負契約の内容の特定や、立証手段の検討には弁護士の専門的な判断が必要
交渉や裁判で請負代金を請求するためには、まずは請負契約の内容を特定することが必要です。
そのためには、工事請負契約が成立するためにどのような事実を明らかにする必要があるのか、事実の裏付けのためにどのような資料が必要なのかについて専門的な知識が必要です。
さらに、本件のように追加工事が問題になる場合には、追加工事1つ1つについて特定が必要です。加えて、本工事と追加工事の区別という観点からも、工事内容を明らかにする必要があります。
特に契約書や注文書・注文請書等の当事者の合意内容を書面にしたものがない本件のような場合は、その立証は困難を極めます。
したがって、弁護士の専門的な判断によって、今後の裁判を見越して、請負契約の特定や立証が可能かどうかを判断することが必要です。
(2)弁護士が専門的な判断をするためには、依頼者の協力が不可欠
弁護士が上記のように、1つ1つの工事内容を特定し、立証の可否を判断するためには、依頼者に必要な情報の収集と整理、説明をしていただく必要があります。
特に契約書等の決定的な証拠がない場合は、依頼者が手持ちのあらゆる証拠の検討が必要になります。
そのため、契約内容を特定するためには、弁護士の指示のもと、1つ1つの工事について、工事日や期間、工事現場、工事内容、金額、合意日、未払い金額等の情報を整理していただく必要があります。
契約書があれば容易に特定できるようなことでも、これがない場合には、契約を特定し、証明するための作業に莫大な時間と労力がかかるのです。
どのような事件にも当てはまりますが、本件のような請負契約代金の請求訴訟においては特に、弁護士だけでなく依頼者の負担も相当に大きく、弁護士と依頼者が一体となって訴訟に取り組んでいかなければ、満足のいく結果を出すことはできません。
(3)訴訟での主張反論に加え、和解交渉でも粘り強く交渉を続けることが重要
本件では、裁判上での和解協議や、代理人間での和解交渉を半年近く行いました。
当初は、相手が100万円程度の和解金額からなかなか動かず、金額が上がらない時期が続きました。お金がないとの理由でしたので、当方の努力で解決できる問題ではなく、ある意味一番厄介な理由でした。
しかし、解決を焦らずに裁判官を味方につけたうえで、会計上の不備等も指摘して交渉を続けました。その結果、総額400万円に加えて代表者を連帯保証人として和解することができました。
実際に相手の経営状況は苦しかったのだろうと思いますが、ここまでの金額まで上げることができたのも、あきらめずに和解交渉を続けた結果であると思います。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、訴訟の提起までに工事の特定や立証資料の検討に大変な手間がかかり、訴訟でも数十ページにわたる書面での反論が必要になるなど、依頼者としても弁護士としても、決して楽なものではありませんでした。
結果としても、請求金額の半分程度の金額での和解となりました。
もっとも、不合理な理由で工事代金を支払わない相手方に対して自分の正当性を主張したいとの依頼者の想いを実現するため、一体となって事件を進めていきました。
裁判官からも依頼者の言い分が正しいとの言葉をいただき、請求金額の半分程の金額での和解でも依頼者に非常に満足していただけました。
最終的には、依頼者から、「依頼して、自分の正義が認められてよかった」、「気持ちが晴れ晴れした」とのお言葉をいただき、和解することができて、本当に良かったと思います。
工事代金の未払いでお困りの場合は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「債権回収に関する弁護士への相談サービス」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】債権回収テーマに関連した解決実績
今回は、「配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した債権回収の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・建設会社から債権回収のご相談を受けて、既に時効が完成していた工事代金について、一部回収に成功した事例
・資力のない施主と粘り強く交渉して建築工事代金の全額回収に成功した解決事例
・施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例
・連絡不通の取引先から500万円回収!工場機械の仮差押えが決め手となった実例
・約束通り納品しない仕入先に対して代金返還を求めて裁判手続によることなく全額を回収した事案
・相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
・鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






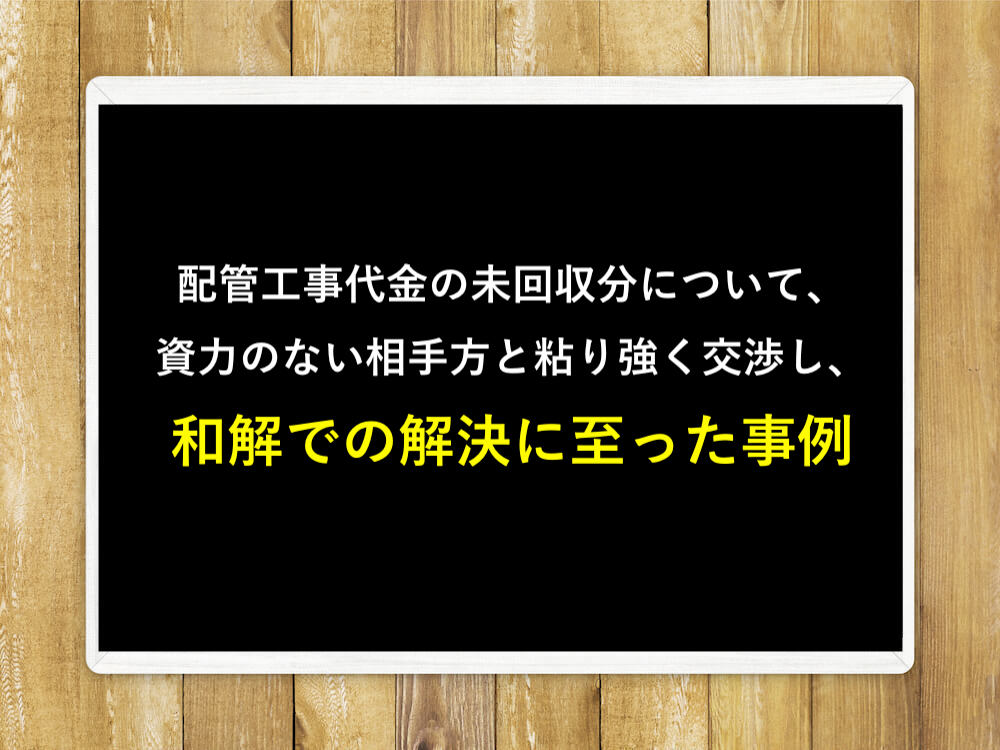

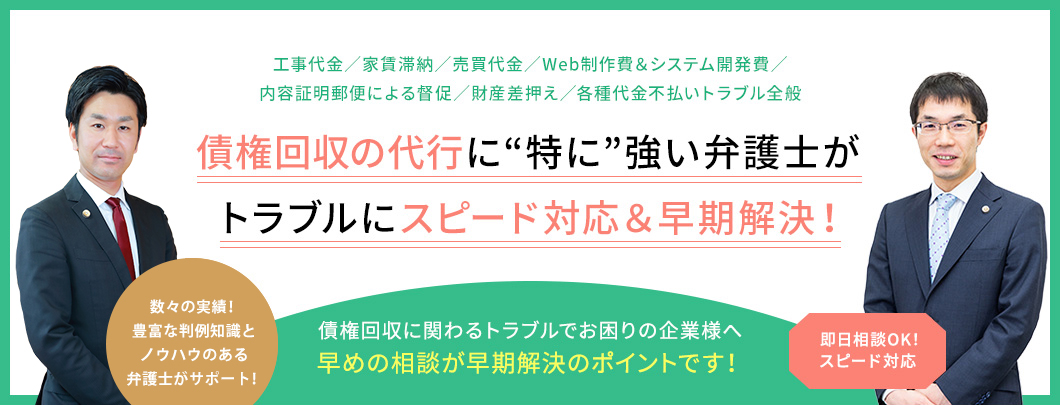
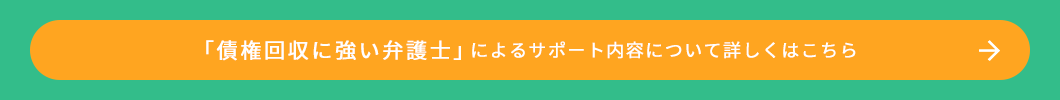
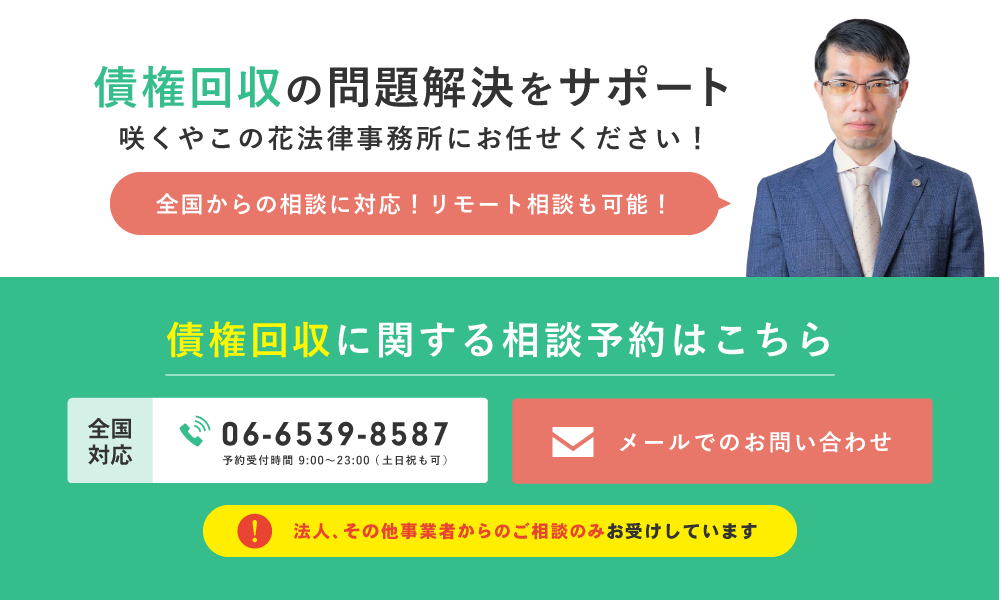






 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















