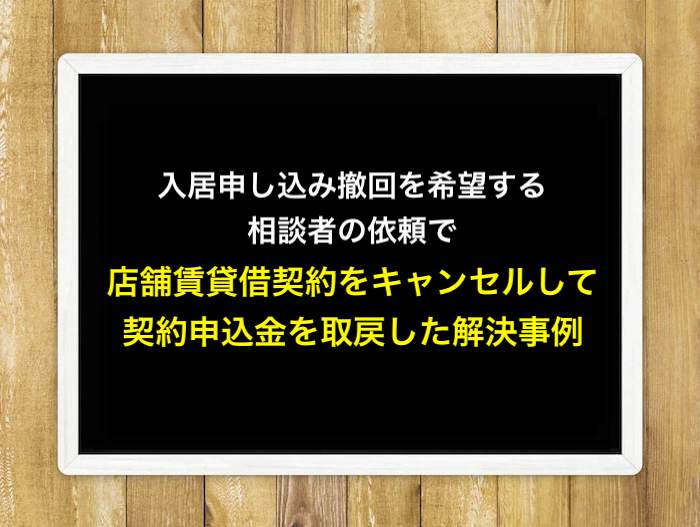
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕
出身地:兵庫県姫路市。出身大学:大阪府立大学総合科学部。主な取扱い分野は、「労務・労働事件(会社側)、保険業法関連、廃棄物処理法関連、契約書作成・レビュー、新商品の開発・新規ビジネスの立ち上げに関する法的助言、許認可手続における行政対応、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「観光施設等の経営」の事例です。
2,事件の概要
本件は、店舗物件への入居申し込み撤回を希望する相談者の依頼で、店舗賃貸借契約をキャンセルして契約申込金の取戻しに成功した事例です。
詳細な経緯は以下の通りです。
依頼者は、東京都内に新店舗を開設する計画を立て、都内で見つけた希望の店舗を借りるために、仲介業者に契約申込金を支払いました。
しかし、結局、依頼者は、条件が合わなかったので、正式に賃貸借契約をする前に、キャンセルすることにし、仲介業者に対して、既に支払った契約申込金を返すように求めました。
当初、仲介業者は、依頼者に対して、「返金の手続をします」とメールなどで約束していました。ところがなかなか返金されません。依頼者は、仲介業者に対して何度も返金するように求めました。これに対して、仲介業者は、依頼者に対して「返金の手続をする」「当社が責任をもって返金する」「週明けには返金する」などとメールで返信しました。しかし、返金の約束をしてから2か月以上たっても、結局依頼者に契約申込金が返金されることはありませんでした。
そこで、依頼者は、自分で督促しても、らちがあかないと考え、咲くやこの花法律事務所にご相談にお越しになりました。
3,問題の解決結果
弁護士の名前で契約申込金全額を返還するように内容証明郵便を送付してから1週間後に、仲介業者から契約申込金全額が返還されました。
4,問題の解決における争点
本件で弁護士が取り組んだ対応内容について、以下で詳しく解説いたします。
(1)契約申込金とは
契約申込金とは、賃貸借契約を締結する前に、物件を他の希望者に賃貸されることを防ぐために、契約希望者からオーナーに対して支払われる金銭です。
契約申込金という呼び方以外にも、例えば申込証拠金、申込金、予約申込金、予約金、売止料などの呼び方があります。5万円から10万円程度の金額の場合が多いとされていますが、不動産の価値によっては1000万円もの契約申込金の支払いを求められることもあります。
(2)契約をしていなければ契約申込金は返ってくるのか?
結論から申し上げますと、契約申込金は返ってくることが多いです。
1.東京地方裁判所平成27年9月11日判決
東京地方裁判所平成27年9月11日判決は、売買契約のキャンセルの場面で1000万円の契約申込金の返金を認めました。
●判決の内容:
「いわゆる申込証拠金は、売買契約締結前に当該物件を自己以外の第三者に売却されることを防ぐことを目的とするものであり、そのために当該物件を買受ける意思を有することを明確にすることを最小限の趣旨ないし機能とする」
「申込証拠金の趣旨は一般に上記のようなものであることから、売買契約が成立しなかったときには全額返還されるべきものであるとの趣旨の下で交付されていると考えられるのであり、これと異なる合意の存在が認められない本件においては、本件不動産の売買契約が締結されないこととなった以上、本件証拠金はその預託の趣旨に基づき受領者である被告サンセイから交付者である訴外会社に対して返還すべきこととなる。」
2.東京地方裁判所平成21年12月8日判決
東京地方裁判所平成21年12月8日判決も、賃貸借契約のキャンセルの場面で500万円の契約申込金の返還を認めました。
●判決の内容:
「契約締結に向けられて金員の授受がなされたが、契約が不成立になった場合、金員授受は法律上の原因を失い、渡された金員は返還されることとなる。本件においても、原告も他の賃借人候補者に先んじて本件物件についての賃貸借契約を締結できるよう本件金員を被告に交付したが、原告が翻意し、本件物件についての賃貸借契約が成立しなかったと認めることができるので、原告は、被告に対し、不当利得として、本件金員の返還を請求できるというべきである。」
3.返還を認めないケースも存在する
注意が必要なのは、契約申込金であれば絶対に返ってくるわけではないということです。
例えば、東京地方裁判所平成22年2月26日判決は、契約をしなければ返還すると約束しておらず、オーナー側が実際に不動産の賃貸借を検討していた他の希望者の入居申込みを断っていたことなどを重視して、契約申込金の返還を認めませんでした。
(3)相手方が宅地建物業者の場合
上記の裁判例を踏まえると、契約申込金であるというだけでは返還を認めなかったケースもありますので、単に契約申込金であることを主張して返還を求めるだけでは、対応として不十分です。
そこで本件では、仲介業者が宅地建物取引業者であったことに着目しました。
宅地建物取引業者の場合、以下のルールが適用されます。
- ●宅地建物取引業者は、賃貸借契約が成立するまでに重要事項を説明しなければならない(宅地建物取引業法35条)。
- ●宅地建物取引業者は、相手方が賃貸借契約の申込みの撤回を行った場合、既に受領した預り金を返還しなければならない(当時の宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号、現行の宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号)。
▶参考情報1:宅地建物取引業法35条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
以下、省略
・参照:「宅地建物取引業法」条文はこちら
▶参考情報2:宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
・参照:「宅地建物取引業法施行規則」条文はこちら
本件では、仲介業者は、依頼者に対して、まだ、宅地建物取引業法35条で義務付けられている重要事項の説明をしていませんでした。
そうすると、「宅地建物取引法35条」により、宅地建物取引業者は、賃貸借契約が成立したと主張することができません。そして、賃貸借契約が成立する前に依頼者は、契約をキャンセルしているので、宅地建物取引業法施行規則上、宅地建物業者は、預り金を返還しなければならないのです。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の方針について解説していきます。
(1)宅地建物取引業法に違反する旨を明確に指摘する
本件のように、法律による許認可を受けた事業者による支払拒否が、その事業者が守らないといけない業界の法律に違反している場合、その旨を明確に指摘するのがポイントです。
宅地建物取引業法、警備業法、保険業法等その業界にだけ適用される法律に違反した場合、事業者は、最悪のケースでは業務停止、許可取消等の可能性もあるからです。
本件では、契約申込金の返還に応じないことが宅地建物取引業法に違反する可能性があるので、具体的な条文番号を記載して、その旨を明確に指摘しました。
(2)弁護士から内容証明郵便で支払いを督促する
上記方針を立てた後、弁護士から仲介業者に内容証明郵便を送り、契約申込金を返すように督促しました。
内容証明郵便の中で、契約申込金を返還しないと宅地建物取引業法に違反する可能性があることを相手方に通知し、10日以内に支払うように請求しました。
内容証明郵便を送付した後、仲介業者から反論はありませんでした。弁護士の名前で契約申込金全額を返還するように内容証明郵便を送付してから1週間後に、仲介業者から契約申込金全額が返還されたのです。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、弁護士が仲介業者の業界に適用される法律に着目したことで、2か月半にわたって督促しても返還されなかった契約申込金全額を1週間で返してもらうことに成功しました。
債権回収については、相手方に適用される業界の法律に着目することが重要です。単にお金を払えと主張するだけではなく、お金を払わないことが法律にも違反していると指摘するわけです。
本件では、相手方は支払いを拒絶していなかったので、依頼者はそれを信じて強く請求できないという事情がありました。そのため、相談者が自分で相手に督促しても、時間だけがたち、回収がすすみませんでした。
そのような場合には、第三者である弁護士を代理人にたてることで、プレッシャーをかけて交渉することが重要です。債権回収でお困りの場合は専門家である弁護士までご相談ください。
また、債権回収については、適切な手段を選択することで回収率が大きく変わってきます。債権回収に関連するお役立ち情報については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
7,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「債権回収に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】債権回収に関連した解決実績
今回は、「入居申し込み撤回を希望する相談者の依頼で、店舗賃貸借契約をキャンセルして契約申込金を取戻した解決事例」についてご紹介しましたが、この事例と関連する解決実績も以下でご紹介しておきますので、参考にご覧下さい。
・約束通り納品しない仕入先に対して代金返還を求めて裁判手続によることなく全額を回収した事案
・契約上の返金義務を履行しない相手方に対し法的手段をとり、全額返金させた事例
・土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例
・資力のない施主と粘り強く交渉して建築工事代金の全額回収に成功した解決事例
・相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






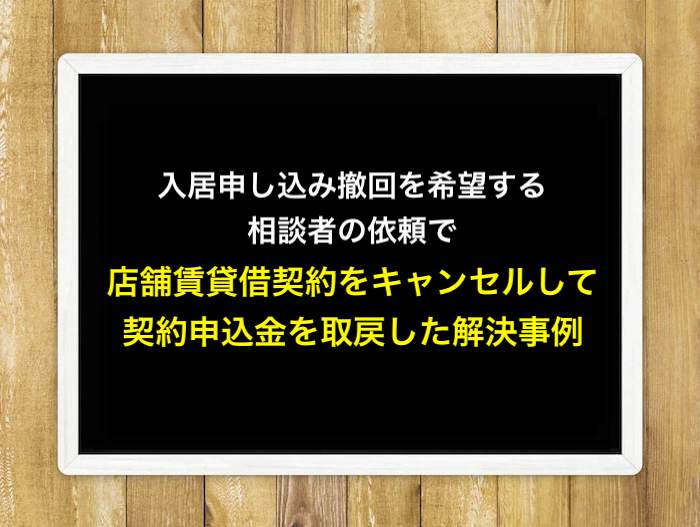

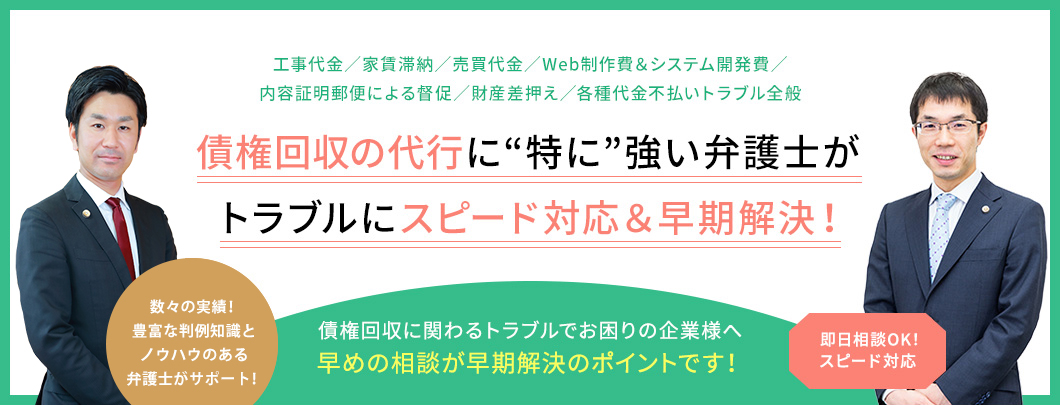
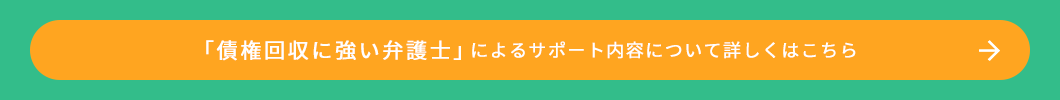
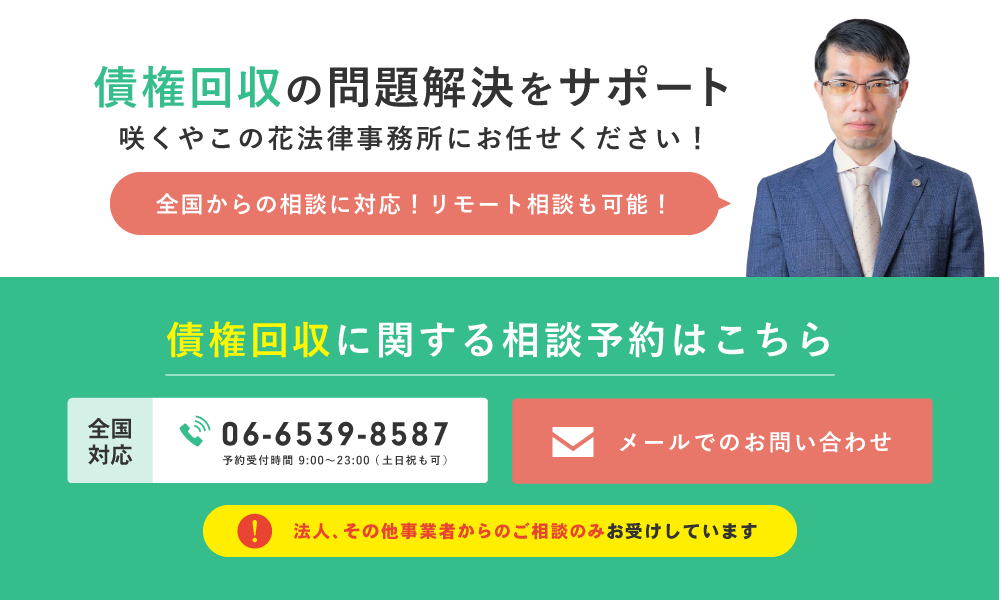






 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















