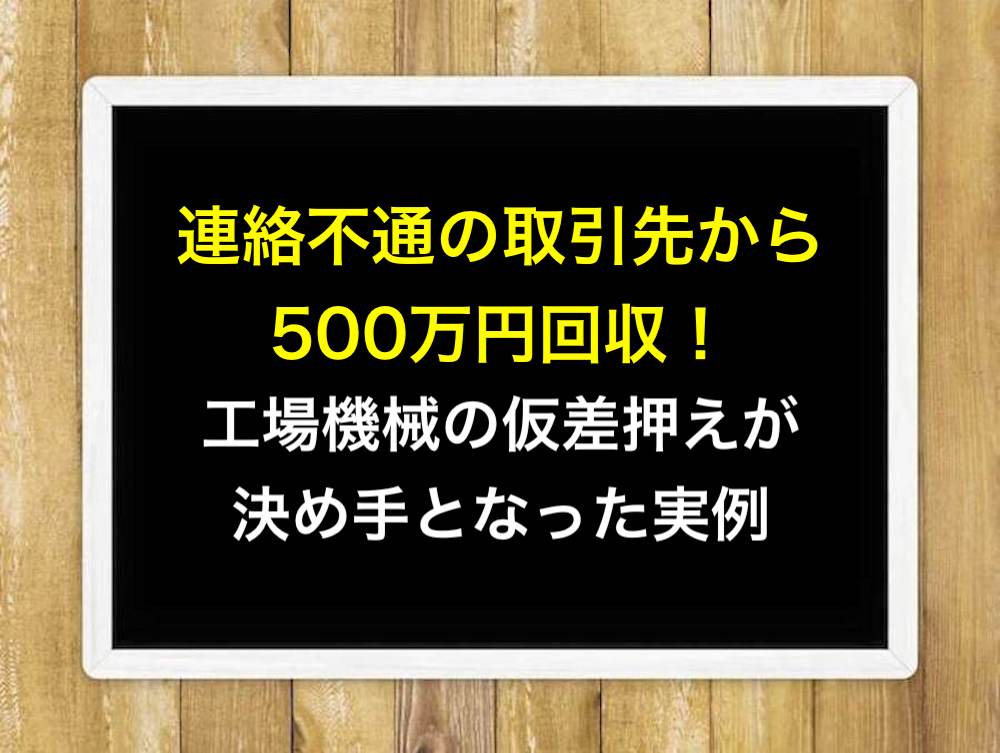
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 堀野 健一
出身地:大阪府岸和田市。出身大学:大阪大学。主な取扱い分野は、「労務・労働紛争の解決(従業員の解雇トラブルや従業員に対する退職勧奨、従業員からの残業代や未払賃金の請求)、不動産紛争の解決(不法占拠者に対する明渡の交渉・裁判・強制執行、賃料の回収、土地の境界の特定など)、システム開発紛争の解決、クレームの解決、就業規則・雇用契約書のチェック、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
依頼者は会社で、相手も会社でした。依頼者は自社の商品を継続して相手に販売していましたが、途中から売買代金が入金されなくなり、しかも相手と連絡が取れなくなってしまいました。依頼者は、このまま相手に逃げられるのではないか、相手が倒産してしまうのではないかと不安に思い、今後の対応も含めて、咲くやこの花法律事務所までご相談頂きました。
2,問題の解決結果
咲くやこの花法律事務所がご依頼を受け、仮差押えの手続きも利用して粘り強く交渉をおこない、最終的に、売買代金を全額回収することが出来ました。
3,問題解決における争点(弁護士が取り組んだ課題)
問題解決において以下の点が課題となりました。
(1)売買代金の金額について
本件では売買契約書はなく、納品書や請求書しかありませんでした。そのため、売買代金額について争いになる余地があり、代金額を確定させる必要がありました。
(2)回収方法について
相手からの支払いが止まっている状況からすると相手に資力があるか不明であり、また、依頼者が相手と連絡を取ることが出来なくなったという状況でしたので、どのように回収するかを考える必要がありました。
4,担当弁護士の見解
このような課題があることも踏まえつつ、以下で述べるように対応を進めていき、課題を解消しつつ、最終的に売買代金を全額回収することが出来ました。
(1)内容証明郵便を使った請求
1,まずは交渉による回収を目指す
売買代金の回収の方法は様々ですが、まずは相手と交渉したうえで、支払いを約束させ、その合意に基づいて回収することを目指すことが適切であることが多いです。相手と合意ができれば、金額を確定させることができますし、相手から任意に支払われることが(一応)期待できます。任意に支払われるのであれば、わざわざ裁判所を使って時間や費用をかける必要がなくなります。今回も、相手に連絡を入れて相手と話をして合意していくことを目指しました。
2,弁護士から内容証明郵便を発送
依頼者によれば、依頼者は相手と連絡がとれなくなったようでした。しかし、そのような場合でも、弁護士から内容証明郵便で請求書面を送って請求すると連絡が取れることがあります。
本件の未払金は約500万円でしたが、請求書面ではこの500万円を1週間以内に支払うよう求める内容を明記し、内容証明郵便で送りました。
しかし、支払期限である1週間が経過しても相手から支払いはありませんでしたし、相手からの連絡もありませんでした。
3,内容証明郵便を送っても連絡がない場合の対応
相手と話が出来ないと合意に基づいて回収することは出来ませんので、依頼者から相手の電話番号を聞いて、弁護士が電話を掛けることにしました。
相手の代表者、相手の従業員に電話を掛けましたが電話に出ませんでした。しかし、その後、電話を掛けた相手の従業員から折り返しの電話があり、話が出来ました。
相手と話をしたところでは、金額自体について争いは無く、支払いはするものの今すぐには支払えないということでした。しかし、すんなり引き下がらずに交渉し、相手に、5日以内に分割払いを前提とした返済計画を提出することを約束させ、その提出を一旦待つことになりました。
4,支払誓約書を提出させる
しかし、5日経っても相手から返済計画の提出はありませんでした。そのため、弁護士から相手に電話を掛けましたが、電話に出ない状態が続きました。
そこで、依頼者と相談の上、こちらから分割払いの条件を明記した支払誓約書を用意して相手に送りました。そうしたところ、相手から、支払誓約書が提出されました。
(2)支払誓約書に基づく請求
1,1回目の分割払いを得る
支払誓約書が相手から提出されましたが、まだ安心はできませんでした。これまでに約束を破ったり、連絡が途絶えたりするような相手でしたので、確実に支払いがされていくという保証は全くありませんでした。
支払いがされる可能性を出来る限り高めるために、1回目の分割払いの支払期限よりも少し前に、「必ず期限内に支払うように」との内容の通知文書を弁護士から送りました。
しかし、そこまでしても、1回目の分割払いの支払期限に支払いはありませんでした。そこで、すぐに弁護士から相手に電話をかけたり書面で通知をしたりして支払いを督促しました。その結果、支払期限の翌日に1回目の支払いがありました。
2,2回目の分割払いについて
また、2回目の分割払いについても同様に支払期限の少し前に、弁護士から「必ず期限内に支払うように」との内容の通知文書を送りました。
しかし、それでも支払期限内に支払いはありませんでした。今回も、すぐに弁護士が相手に電話をかけたり書面で通知をしたりして支払いを督促しました。そうしたところ、支払期限の10日後にようやく支払いがありました。
3,3回目の分割払いについて
そして、3回目の分割払いについても同様に支払期限の少し前に、弁護士から「必ず期限内に支払うように」との内容の通知文書を送りました。
しかし、それでも支払期限に支払いはありませんでした。しかも、今回は、弁護士から繰り返し電話をしたり、書面で督促したりしても、支払いも無ければ電話もつながらない、折り返しも無いという状況が続きました。
相手には書面にて、これ以上連絡が無ければ訴訟提起をしていくことも伝えましたが、それでも相手から連絡はありませんでした。
(3)仮差押えの検討と実施
1,訴訟提起を決断する
このように相手と連絡が途絶えましたので、任意に支払いを受けていくことがこれ以上は困難と判断しました。
そこで、依頼者と相談の上、訴訟を提起する方針で進めることとなりました。訴訟になると費用が掛かりますので、依頼者としても最初は躊躇はされていましたが、最終的に訴訟を進めていく決断をされました。
2,仮差押えを行う
もっとも、相手の資力は不明であり、訴訟を起こしたところで回収できるかどうかの不安がありました。
そこで、訴訟を起こす前に、まず仮差押えで相手の財産を押さえることにしました。「仮差押え」というのは、後に訴訟を起こしたとしてその訴訟中に相手に財産が無くなってしまい勝訴しても回収が出来ないという事態を防ぐために、裁判所を使ってあらかじめ相手の財産を仮の形で押さえておき、勝訴した際にその財産から強制的に回収できるようにするという制度です。
この仮差押えは、裁判所に申立てをおこなって、裁判所に認めてもらうという手順を踏む必要があります。
3,仮に差し押さえる財産の候補を洗い出す
今回の事案では、仮に差し押さえる財産の候補としては、以下のものが考えられました。
- ア:相手名義の預金口座にある預金
- イ:相手の第三者(取引先)への売買代金債権
- ウ:相手の工場内にある機械
4,債権額を3つの財産に割り付ける
この時点での相手の未払いの金額は約270万円でした。
複数の財産を仮差押えするには、未払いの金額を各財産に割り付ける必要があります。つまり、約270万円の未払いの売買代金の場合で、仮に押さえしようとする財産が3つあるとすると、それぞれの財産ごとに、100万円、100万円、70万円などと割り付ける必要があります。
そして、この割り付けた金額の範囲でそれぞれの財産を仮に押さえることができます。
例えば、ある財産の仮差押えのために100万円を割り付けたのであれば、100万円を上限として、勝訴判決を得たのちの強制執行において、その財産から支払いを受けることが可能です。
本件では依頼者と相談の上、今回は「ア:相手名義の預金口座にある預金」、「イ:相手の第三者(取引先)への売買代金債権」、「ウ:相手の工場内にある機械」のいずれも仮差押えすることになりました。
そこで、どの財産にいくら割り付けるかが問題となりました。依頼者が、相手の工場を事前に見に行き、相手の工場が稼働していることを確認していたため、工場に機械はあることは確実視されました。これに対して、相手の預金口座は残高があるか不明でしたし、第三者(取引先)への売買代金債権も現時点で存在するかは不明でした。
そこで、仮差押えが成功する可能性が一番高いものは機械であると判断して、多くの金額を機械の仮差押えに割り付けることにしました。
また、この機械の仮差押えは、預金口座や売買代金債権の仮差押えとは異なり、実際に相手の工場に予告なく執行官(裁判所の職員)と一緒に行って仮差押えをすることになります。突然行くことによる相手へのインパクトは大きく、また、実際に相手と会って話ができればそれにより交渉を進展させられる可能性もあります。その意味でも、機械の仮差押えを行うことが重要であると判断しました。
機械に割り付けた残りの金額のうち、預金口座の預金の方に多めに割り付けて、売買代金債権はその残りを割り付けました。
5,預金口座には約7万円の残額があり、これを仮に差し押さえることが出来ました。
売買代金債権はありませんでしたので、仮に差し押さえることは出来ませんでした。機械については、執行官と相手の事業所に行く日程調整等をすることになりました。
(4)機械の仮差押えの場を利用した交渉
1,執行官とともに相手の工場を予告なく訪問
機械の仮差押えは、執行官とともに相手の事業所を予告なく訪問して実施します。
事前に執行官と訪問する日時を調整し、また同行が必要な方を確認してこちらで必要な方を用意しました。当方からは、本件の担当弁護士である私のほか、代表者、従業員2名、機械の査定業者2名が同行しました。
相手の工場は山の上の方にあり、特に目印となるものもなく、かつ電波も届かないということであったため、執行官とは一度山のふもとで集合して、一緒に自動車で向かうことにしました。
2,仮差押えを執行する
相手の事業所につくと、施錠はされておらず、工場も営業している様子でした。執行官だけでまず立ち入っていき、その後、執行官の承諾を得て立ち入りました。相手は観念した様子で、執行官に抵抗したり、仮差押えに反対したりということもありませんでした。
そのため、仮差押え自体は粛々と進んでいきました。
3,相手に未払い代金を支払うよう追及
こちらとしては、これまで連絡がつかなかった相手ですので、話をする良い機会でした。
そこで、執行の機会を利用して、この場で返済の話をすることを相手に要求し、相手と工場の横にあった事務所で話をすることになりました。
当方から未払いの代金を払うよう追及したところ、相手からは銀行口座への仮差押えが銀行との取引関係上で不都合があるということで、銀行口座の仮差押えに割り付けていた70万円は支払うので、仮差押えを取り下げてもらいたいという話がされました。相手は銀行との関係を気にしている様子でした。
こちらとしては、銀行口座の残高である約7万円の仮差押えを維持しておくよりも、いま70万円の支払いを受ける方が良いため、70万円の支払があることを条件としてこの話に応じることとしました。
そして、この70万円が支払われるとして残金についてどのように払うのかを追及しました。これに対し、相手は、残金も支払っていくつもりであり、いま弁護士に相談しているので、その弁護士を通して話をしたい、とのことでした。
しかし、「弁護士に相談している」や「弁護士に依頼する予定」などと言いつつ、実際には相談していないことや依頼していないこともよくあります。そこで、本当に弁護士に相談しているのかを確認するために、相談している弁護士名を聞いておきました。また、速やかにその弁護士から連絡するように伝えました。
弁護士に依頼するということでもあったので、その場では話を終えました。そうすると、1週間もしないうちに、その弁護士から受任した旨の連絡がありました。また、仮差押えの日から1週間後に70万円が支払われました。70万円の支払いがありましたので、相手との約束にしたがって、銀行口座の仮差押えについては、取り下げることとしました。
(5)相手の弁護士との交渉と弁護士の辞任
1,残った未払金について分割払いの合意をする
残った未払いの金額は約200万円でした。これについて、その後相手の弁護士と協議をし、改めて分割払いを誓約させる内容で合意しました。しかし、1回目の分割払いは期限にありましたが、2回目の分割払いがされませんでした。
そこで、相手弁護士に繰り返し連絡して支払いを督促しました。そうしたところ、相手の弁護士が相手の代理人を辞任しました。
2,全額の回収に成功する
相手の弁護士が代理人を辞任したため、その後は相手と直接やり取りをすることとなります。
そこで、早速相手に連絡したところ、相手と話は出来て、今後の支払いについて協議をし、改めて相手に支払誓約書を提出させました。また、相手が依頼者と同業者であったので、依頼者の希望もあり、代金の返済の代わりに商品を譲渡させて、それを代金の返済に充当させることもしました(これを代物弁済と言います。)。この代物弁済の形で、相手に金銭が無いとしても、商品があるのであれば、それをもらって返済に充てることが可能です。
以上のような結果、最終的に、売買代金を全額回収することが出来ました。依頼者は、回収までに時間を要した点で苦労されていましたが、全額回収に至り安堵されていました。
5,解決結果におけるまとめ
本件では、仮差押えも利用しつつ相手と粘り強く交渉を続けていった結果として売買代金の全額を回収することが出来ました。
回収の可能性を高めるには、請求の手を緩めることなく、仮差押えなどの法的な手段も含めて取れる手段は順次取っていくことが重要です。売掛金の回収でお困りの際は咲くやこの花法律事務所に早めにご相談ください。
6,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する弁護士への相談サービスへの問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回の解決事例は、「連絡不通の取引先から500万円回収!工場機械の仮差押えが決め手となった実例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した債権回収トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・資力のない施主と粘り強く交渉して建築工事代金の全額回収に成功した解決事例
・約束通り納品しない仕入先に対して代金返還を求めて裁判手続によることなく全額を回収した事案
・配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
・鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例
・相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
・未払い設計料や工事代金の回収依頼を受け、施主のショッピングモールに対する預り金債権を仮差押えできた事例
・施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






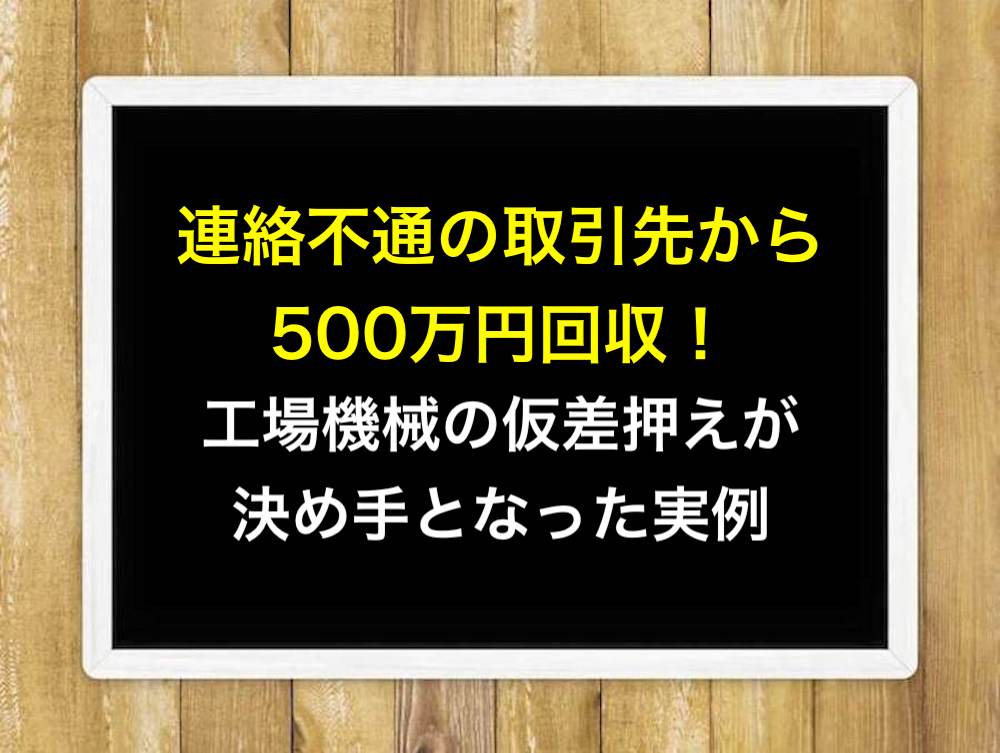

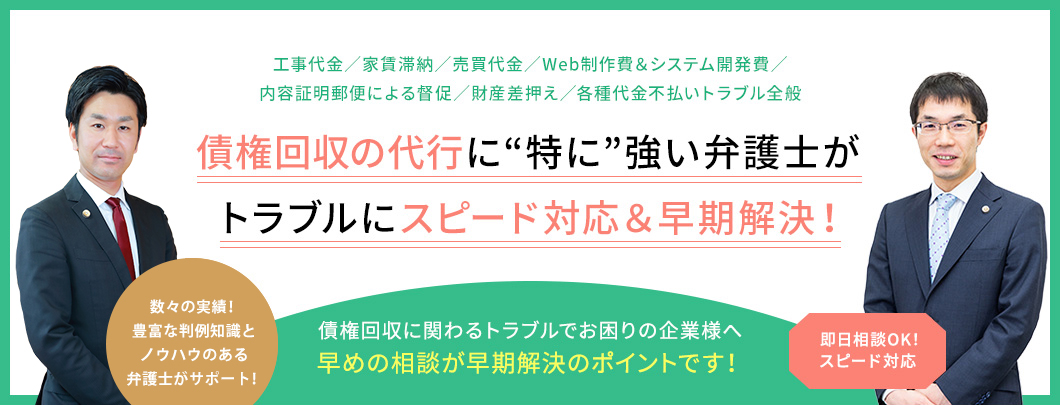
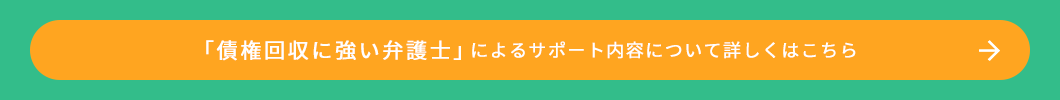
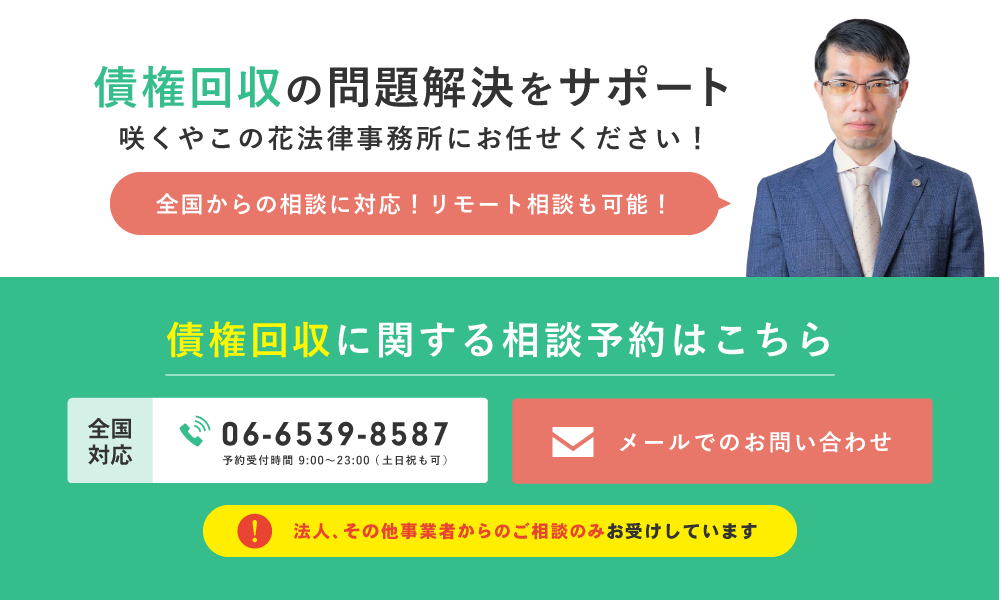






 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る
















