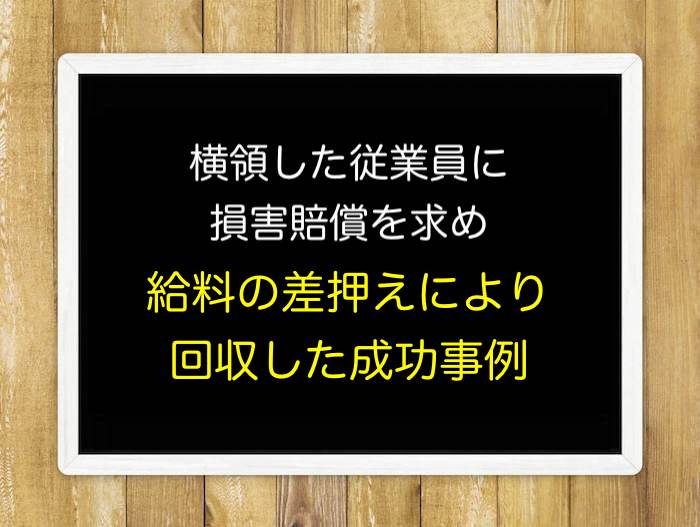
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
本件は、集金した売掛金を横領した従業員に対する損害賠償請求について、咲くやこの花法律事務所が依頼を受けたケースです。
会社は、従業員が取引先から集金した売掛金を横領していたことが発覚したため、従業員を解雇しました。その後、被害を受けた約300万円を何とか回収したいとのことで、ご相談にお越しになりました。
この従業員は解雇後に別の会社に転職しましたが、この転職先の給料を差押えることにより、横領金の回収を行いました。
2,問題の解決結果
まず、弁護士が会社の代理人として、元従業員に損害賠償を求める通知書を送付しました。すると、元従業員が横領を認めましたが、資金がなく一括で弁償することができませんでした。そこで、弁護士が元従業員との間で、横領金を分割して弁償するという内容の公正証書を作成しました。しかし、その後、元従業員は分割金を支払わなくなりました。
そのため、裁判所に対し、公正証書に基づく強制執行を申し立て、元従業員が新たな勤務先から支払いを得ていた給料を差し押さえることに成功しました。
3,問題解決における争点
横領された金銭をどのようにして確実に回収するかが問題となりました。
具体的には、以下の3つが問題になりました。
- ●1.いかにして元従業員に横領の事実を認めさせるか
- ●2.元従業員が横領の事実を認めた場合、いかにして証拠化するか
- ●3.一括での弁済が困難な場合、いかにして確実に弁済させるか
以下、弁護士と元従業員との交渉経緯を踏まえ、「1」から「3」について、順に説明します。
4,担当弁護士の見解
(1)内容証明郵便による通知書の送付
まず、元従業員に対し、横領によって生じた損害の賠償を求める通知書を弁護士名義で送付しました。
通知書を迫力あるものにするためには、普通郵便ではなく、内容証明郵便を選択することが重要です。また、会社名ではなく、弁護士名義で送付することが重要です。そうすることで、受領者に対し、通知書を放置すれば、民事訴訟、刑事告訴等の法的手続を取られるかもしれないとプレッシャーを与えることができます。
さらに、通知書に説得力を持たせるためには、事実を具体的に記載することが重要です。
本件のケースでは、会社の保管する請求書、領収書等の資料を分析し、会社の経理担当者との打合せを重ねました。資料の分析と打合せを経て、横領の対象となった集金を特定し、集金した日、集金した取引先、集金金額を具体的に列挙した通知書を作成することができました。
(2)債務残高確認書の取得
通知書に記載した期限の直前になって、元従業員より電話がありました。電話の内容は、通知書に記載してあることは間違いないが、全額をすぐに支払うことができないのでどうすればよいか、というものでした。
期限が迫って慌てて連絡してきたようで、この段階では具体的な返済方法が定まっていない様子でした。しかし、この段階で具体的な返済方法の確定を急ぐべきではありません。まずは、後になって言い逃れできないよう、通知書に記載した具体的事実を元従業員が認めたことを証拠化しておくことを優先すべきです。
弁護士は、横領の事実と支払うべき金額を記載した債務残高確認書という書類を元従業員に郵送し、署名捺印の上、返送するよう求めました。債務残高確認書には、集金した日、集金した取引先、集金金額をあらためて列挙し、横領した合計金額について、「賠償義務があることを認めます。」と記載しておきました。
その後、債務残高確認書が返送されてきました。
弁護士は、元従業員を事務所に呼び出して面談し、具体的な返済方法を協議しました。すると、元従業員は一括で支払うだけの資金がないと述べました。しかし、支払能力がないという元従業員の説明を鵜呑みにするわけにはいきません。
弁護士は、元従業員に対し、分割による返済を認める条件として、現在の勤務先、仕事の内容、毎月の給料、給料の使い道などについて説明を求めました。その結果、確かに、一括での返済は現実的でなかったため、やむを得ず、分割払いに応じることにしました。
(3)公正証書の作成
分割払いに応じるとしても、分割払いが滞ったときの対策をしておく必要があります。そのためには、公正証書を作成しておくことが有効です。
「(2)債務残高確認書の取得」で説明した債務残高確認書を取得しておけば、たとえ元従業員が支払いを怠ったとしても、訴訟を起こし、勝訴判決を得ることは可能です。
勝訴判決を得れば、元従業員の財産を差し押さえることができます。しかし、訴訟を起こさなくても、直ちに相手方の財産を差し押さえることができる方法があります。それが公正証書です。
公正証書とは、公証役場で、公証人の立会いのもと作成する文書のことです。公正証書に、「この公正証書に書かれた債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けることを認めます。」という条項(強制執行認諾条項)を入れておけば、訴訟を起こさなくても、直ちに財産を差し押さえることができます。
今回のケースでも、元従業員が長期の分割払いに応じるか不安があったため、公正証書の作成を条件に分割払いに応じることにしました。
その後、弁護士と元従業員が公証役場に出頭し、公証人の立会いのもと、会社の損害金約300万円を分割で支払うという内容の公正証書を作成しました。もちろん、強制執行認諾条項も入れておきました。
(4)給料の差押え
しかし、元従業員から分割金が支払われることはなく、連絡も取れなくなってしまいました。
そのため、弁護士は、事前に確認してあった元従業員の勤務先の情報をもとに、給料の差押えを行うことにしました。給料の差押えは、裁判所に差押えの申立書を提出して行います。
公正証書を作成しておけば、直ちに財産の差押えをすることはできます。ただし、差し押える財産がどこにあるかは、自ら見つけなければなりません。例えば、預金は、金融機関名だけでなく支店名まで特定できなければ差押えをすることができません。また、給料についても、勤務先が特定できなければ差押えをすることができません。
なお、給料は、原則として、手取額の「1/4」までしか差押えをすることができません。債務者といえども、最低限の生活は保証されなければならないからです。
今回のケースでは、弁護士が元従業員と面談した際に、現在の勤務先を聞き出していたため、スムーズに給料の差押えを実行することができました。その後、毎月、給料の1/4が元従業員の現在の勤務先から会社に支払われるという状況が続いています。
5,解決結果におけるまとめ
本件では、最終的に元従業員の給料の差押えに成功しました。
一般に、従業員が会社のお金を横領したのであれば、会社に返さなければならないのは当然です。しかし、従業員が横領したことを認めようとしない場合や、横領を認めたとしても既に使い込んでしまっている場合など、現実的に回収が難しいことは多々あります。
そのようなときは、従業員が認めざるを得ないほどに、徹底的な証拠収集をしなければなりません。その上で、従業員に具体的な事実を記載した通知書を送付し、速やかに現実の支払いに向けた交渉を開始すべきです。
仮に、従業員が横領を認めたとしても、現実の回収のためには、従業員がいかなる財産を持っているか想像力を働かせて調査する必要があります。自宅住所等の登記を調べて不動産を所有していないかを調べることも有効でしょう。弁護士会経由で金融機関に照会をかけ、預金口座のある支店や残高を調査することもできます。また、今回のケースのように勤務先を特定することも有効です。
さらに、万が一に備えて、従業員が入社する際に身元保証人を立ててもらうという方法もあります。そうしておくと、不幸にも従業員による横領等が発生した場合には、身元保証人にも支払いを求めることができます。身元保証人には迷惑をかけられないとの思いから、従業員がお金を工面して速やかに支払いに応じるという効果も期待できます。
従業員による横領でお困りの企業様は咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
6,咲くやこの花法律事務所の業務上横領に強い弁護士へのお問い合わせ
咲くやこの花法律事務所の業務上横領に強い弁護士のサポート内容は「業務上横領に強い弁護士への相談サービスについて」のこちらのページをご覧下さい。
また、弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,【関連情報】業務上横領に関するお役立ち情報
今回の解決実績は、「横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例」についてご紹介しました。なお、業務上横領に関する対応については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。
・業務上横領についてわかりやすく解説
・社内で業務上横領が起きたときの証拠の集め方!4つのケースを解説
・従業員による業務上横領や着服の刑事告訴・刑事告発のポイント
・身元保証書とは?従業員の不正発生時に役立つ正しい作り方を解説【書式付】
・従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き
・【未然に防ぐ対策方法】経理従業員の横領・不正防止のためにやっておくべきポイント
・業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説
 06-6539-8587
06-6539-8587






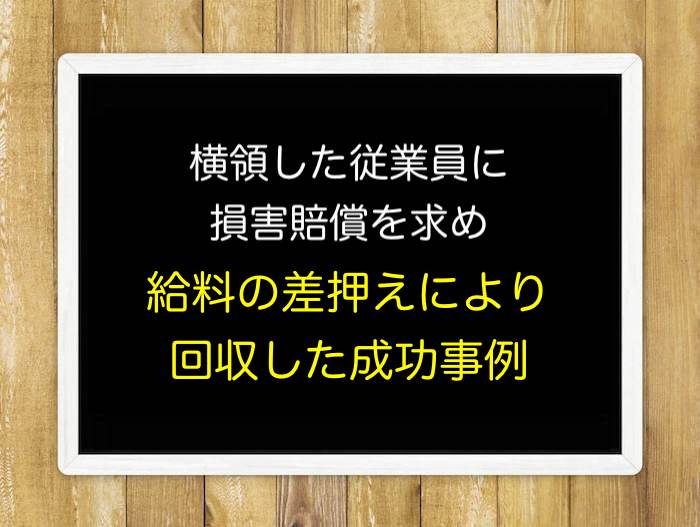

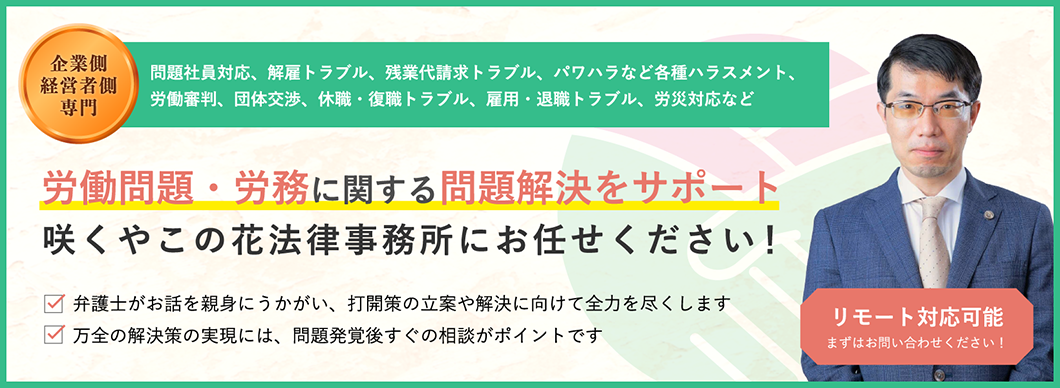
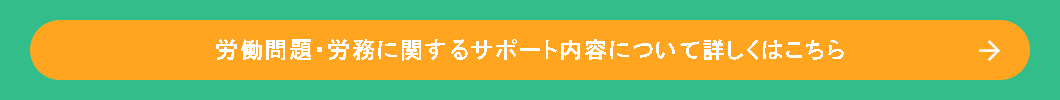
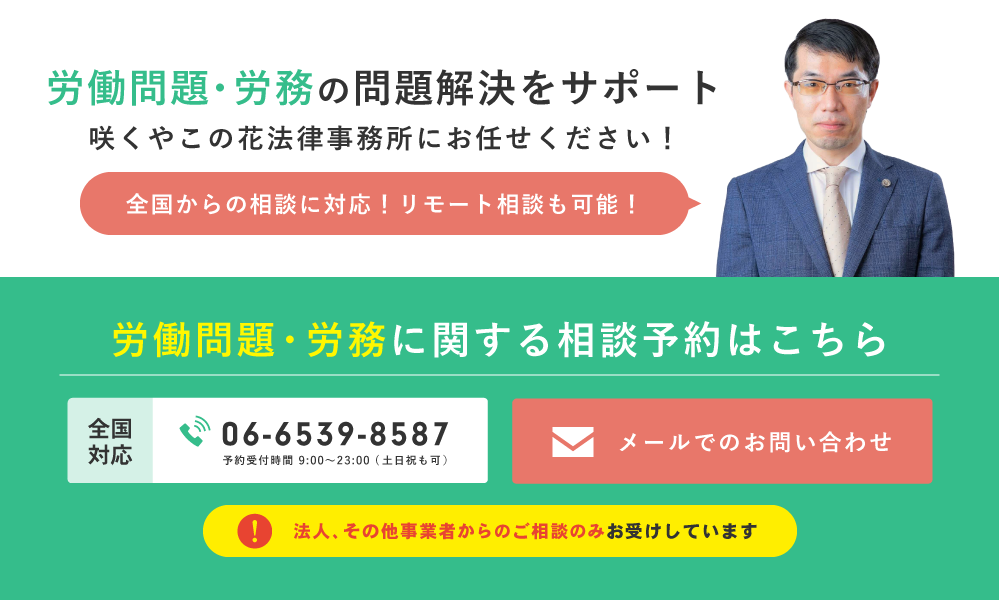
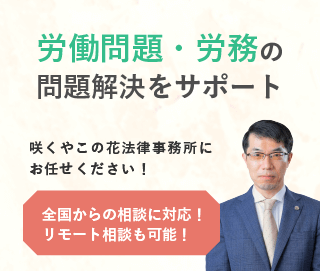





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















