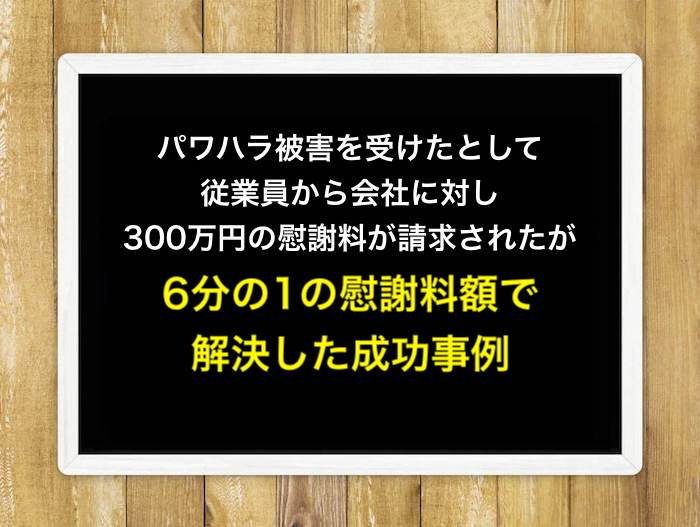
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 弁護士 堀野 健一
出身地:大阪府岸和田市。出身大学:大阪大学。主な取扱い分野は、「労務・労働紛争の解決(従業員の解雇トラブルや従業員に対する退職勧奨、従業員からの残業代や未払賃金の請求)、不動産紛争の解決(不法占拠者に対する明渡の交渉・裁判・強制執行、賃料の回収、土地の境界の特定など)、システム開発紛争の解決、クレームの解決、就業規則・雇用契約書のチェック、顧問弁護士業務など」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,事件の概要
本件は、従業員が上司や同僚から嫌がらせや暴言などのパワハラ(パワーハラスメント)を受けたとして、会社に安全配慮義務違反があると主張し、会社に対して裁判を起こして、慰謝料の請求をした事案です。
従業員(原告)が訴訟で主張した「他の従業員からの嫌がらせや暴言」については、一部が録音されており、暴言等の存在自体については事実であることが確認されました。
もっとも、これらの暴言等が、パワハラ(パワーハラスメント)にあたるかどうかや、暴言等による原告の精神的苦痛の程度については反論の余地がありましたので、こちらについて弁護士が訴訟において反論を行いました。
2,問題の解決結果
判決の結果、請求された慰謝料の額を6分の1に減額して解決に至りました。
3,問題解決における争点(弁護士が取り組んだ課題)
本件の争点は以下の通りです。
(1)最初に録音データの提出を相手に要求した
会社から訴訟についてご相談いただいた当初、原告は暴言等の録音データを裁判所に証拠提出していませんでした。
しかし、暴言等が少し前のことであるにもかかわらず、原告が訴訟で主張する暴言等の内容がかなり具体的であったので、弁護士は、会社からご相談をお受けして、原告の手元には録音データがあるのではないかと感じました。
また、同時に、弁護士は、原告が訴訟戦略上、あえていったんは会社に録音された発言の存在を否定する主張をさせたうえで、後から録音データを証拠提出して、会社の主張に反論するという方針を考えているのではないかと予想しました。
そこで、弁護士は、そのような原告の方針を崩すため、裁判において、原告に対し、「録音データがあるのであれば提出されたい」と要求しました。
そうしたところ、案の定、原告は録音データを持っており、原告から裁判所に録音データが証拠提出されました。
弁護士が、この録音データを、加害者と主張されている発言者に聴いてもらったところ、間違いなく発言者の声であることがわかりました。
そこで、録音に残っている発言は事実として認めた上で、以下の2点を争点として訴訟で争う方針をとりました。
(2)2つの争点について会社側の反論を行った
争点1:
言動が違法(いわゆるパワーハラスメント)と評価できるものか
過去の判例上、正当な指導の範囲内の発言はたとえ厳しいものであっても、適法と判断されています。
そこで、本件でも、上司の発言が正当な指導の範囲内といえるものであったか、それとも、指導を超えて違法と評価されるものか、が争点となりました。
争点2:
原告の精神的苦痛の有無、程度
仮に言動が正当な指導の範囲を超えており、違法と評価されるものとしても、それにより原告がどの程度精神的な苦痛を受けていたかによって、慰謝料の金額は変わります。
そのため、原告がどの程度の精神的苦痛を受けたのかも争点となりました。
4,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の見解について詳しく解説していきます。
上記の各争点について、会社側の立場から、以下の通り主張して反論しました。
争点1:
「言動が違法と評価できるものか」について
1,正当な指導のための発言であることを主張
まず、会社側の立場で、原告が問題としている言動は正当な指導の範囲内のものだという主張を行いました。
過去の判例上、指導の範囲内のものかどうかは、発言の内容だけで決まるものではなく、
- ●発言を行った場所や状況
- ●発言の目的
- ●指導の対象となった問題行動の重大性の程度
- ●発言後のアフターフォローの有無
などを総合的に考慮して判断されます。
そこで、発言を行った場所や状況に照らして、どういう目的でした発言であるか、なぜそのような発言になったのかなどを裁判所で丁寧に説明しました。
2,嫌がらせ目的、退職強要目的という主張に対する反論
原告側は、録音された言動について、原告に対する嫌がらせ目的や退職させる目的での発言であると主張しました。
これに対して、会社側の立場から、そもそも原告に対する発言ではない部分が含まれていることや、原告に対する発言部分もあくまで売上の数字を意識づけるために言ったもの等で指導の範囲内である旨の主張を行いました。
3,録音データの発言者に証人として証言してもらった
さらに、会社側で、上記の主張を裏付けるために、録音された発言の発言者に、証人として裁判所に出頭してもらい、証言をしてもらうことにしました。
そのため、弁護士は、訴訟が始まった早い段階で、発言者に、裁判所で証言してもらうことになると説明して、承諾をもらっておきました。
そして、実際の証言の際には、録音データに残っている発言ごとに細かく、
- ●どこでされた発言か
- ●誰に対する発言か
- ●どういう目的で言ったのか
などを質問し、証言してもらいました。
ただし、録音の中には、指導の範囲を超えたと評価せざるを得ない言動もありました。
これについては、次の争点「原告の精神的苦痛の有無、程度」において反論をすることになりました。
争点2:
「原告の精神的苦痛の有無、程度」について
1,過去の申告書等を証拠として提出した
会社側の立場から、録音された発言について、原告の精神的苦痛は無かったのではないかという主張を行いました。
この主張の根拠としては、以下の事情がありました。
原告も含めた全従業員が会社へ定期的に提出する申告書という書類に「パワハラを見聞きしたことがあるか」という質問事項がありました。しかし、原告はその質問に対する回答を何も書いていませんでした。
また、会社では、社内及び社外にパワハラ相談窓口を設置していましたが、原告からその相談窓口に連絡されたことはありませんでした。精神的苦痛を受けたのであれば、その申告書に自分の被害のことを記載するはずであるし、パワハラ相談窓口に連絡するはずと思われました。
そこで、弁護士は、会社から、上記の申告書や、社内及び社外相談窓口に関する規程を取得し、証拠として裁判所に提出しました。その上で、原告が申告書に自分の被害のことを記載しておらず、また、パワハラ相談窓口に連絡していないのは、精神的苦痛が特に無かったからではないかという主張を行いました。
2,会社側弁護士による反対尋問で矛盾点を指摘する
裁判では、原告の言い分に対して、会社側の立場で質問する「反対尋問」を行うことができます。
本件の原告に対する反対尋問では、弁護士から、上記の申告書について改めて質問を行い、被害のことを何も記載していないことが不自然であることを裁判官に印象付けました。
具体的には反対尋問において、弁護士が原告に申告書を提示し、「パワハラを見聞きしたことがあるか」という質問に対して、何も記載していないことを突きつけ、原告の訴訟での主張が過去の申告書の記載内容と矛盾していることを指摘しました。
3,裁判所の提示した和解案に原告が応じなかった
多くの裁判では、判決になる前に、裁判所が主導する形で和解の提案が行われます。本件でも、判決に至る前に、裁判所からの提案により、和解の協議を行いました。
裁判官としては、原告がパワハラと主張する言動のうち、録音されている発言以外の言動についてはその存在の認定が難しいこと、録音されている発言について必ずしもすべて問題があるわけではないこと、一方で指導目的との認定が難しい言動もあること等を理由に、和解金額として70~80万円を考えているとのことでした。
この裁判官の考えを踏まえて、原告と会社が、和解について検討をすることになりました。しかし、最終的に原告が和解に応じないという強硬な態度を示したため、和解に至らず、判決に進むことになりました。
5,解決結果におけるまとめ
(1)判決では会社側の主張が考慮され請求額が大幅に減額された
判決においては、会社の反論も考慮され、裁判官の判断として、請求額の6分の1にあたる50万円の支払を命じられるのみにとどまりました。
判決に対しては控訴が可能です。
▶参考情報:「控訴」とは、1審の判決の見直しを求めて2審での審理を求める手続をいいます。
1審の判決を受けて会社と弁護士で相談を行い、その結果、会社として、請求額から大幅に減額となったことや控訴したときの見通し等の諸事情を踏まえ、控訴はしないこととしました。
原告が強硬に和解に応じなかったことから、原告側から控訴されることを予想していましたが、控訴はされませんでした。
そのため、判決が確定して事件が終了しました。
(2)会社がパワハラで訴えられた場合の対応のポイント
従業員が、上司などの言動についてパワーハラスメントであるなどとして、会社の安全配慮義務違反を根拠に、会社に対し慰謝料請求するというケースはよく見られるご相談事例の1つです。
このような事案では、以下の点がポイントとなることが多いです。
- ●1,従業員が問題としている上司の言動がそもそもあったか否か
- ●2,その言動があったとして違法と評価できるか否か
- ●3,違法と評価できるとして、それによる精神的苦痛の有無、程度
これらの各ポイントについて、説明をしていきます。
1,「従業員が問題としている上司の言動がそもそもあったか否か」について
この点については、録音、手帳のメモ、友人へ相談したメールなど種々の証拠が提出されることがあります。
このうち手帳のメモや友人に相談したメールなどについては、あくまでパワハラを主張している従業員による記録ですので、記録されているような発言をしたとされる加害者が発言の事実を否定する場合は、発言の存在自体が争点となります。
これに対し、録音が残っている場合については、客観的な証拠として、その内容が判決でそのまま認定される傾向があります。
そのため、録音が証拠として提出された場合には、前述の「2,その言動があったとして違法と評価できるか否か」や「3,違法と評価できるとして、それによる精神的苦痛の有無、程度」のポイントで争うことになります。
2,「その言動があったとして違法と評価できるか否か」について
この点については、「指導としての言動であって違法ではない」と示せるかがポイントです。
指導と評価されるか又は指導を超えると評価されるかについては、言動がされた際の状況、言動が業務に関連するか否か、言動の目的などに照らして個々の事案ごとに判断されます。
これらの点について、裁判で具体的に説明していくことが重要になります。
3,「違法と評価できるとして、それによる精神的苦痛の有無、程度」について
この点については、「精神的苦痛を受けていれば、通常取るはずの行動をとっていないこと」を示せるかがポイントになります。
例えば、相当程度の精神的苦痛を受けたのであれば、家族、友人、会社の同僚や部下などに相談をしたり、程度によっては病院に通院したりすることが通常です。
このように、通常取るはずの行動をとっていないことを示すことが出来れば、それを根拠に、精神的苦痛は無かった又は小さいという主張をしていくことが可能です。
このようにパワハラという一見、会社側に分が悪い事件であっても、丁寧に主張していくことで、十分反論が可能です。
パワハラを理由とする慰謝料請求の訴えにお困りの場合には、早期に咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
なお、パワハラで訴えられた時の会社側の対応の流れなどについては以下で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
6,咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「労働問題に関する弁護士への相談サービス」への問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,【関連情報】この事例に関連した解決実績&お役立ち情報
今回は、「パワハラ被害で従業員から会社に対し300万円の慰謝料が請求されたが、6分の1の慰謝料額で解決した成功事例」について、ご紹介しました。他にも、パワハラなど、今回の事例に関連した解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・教職員が集団で上司に詰め寄り、逆パワハラが生じていた学校から弁護士が相談を受けて解決した事例
・内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例
また、パワハラについては、以下で詳しい解説記事を公開していますので参考にご覧ください。
・パワハラに強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
・パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について
・パワハラ防止法とは?パワハラに関する法律のわかりやすいまとめ
・パワハラやハラスメントの調査方法について。重要な注意点を解説!
・パワハラの証拠の集め方と確認すべき注意点などをわかりやすく解説
・パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説
・逆パワハラとは?正しい対策方法3つを解説します。
・パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点
 06-6539-8587
06-6539-8587






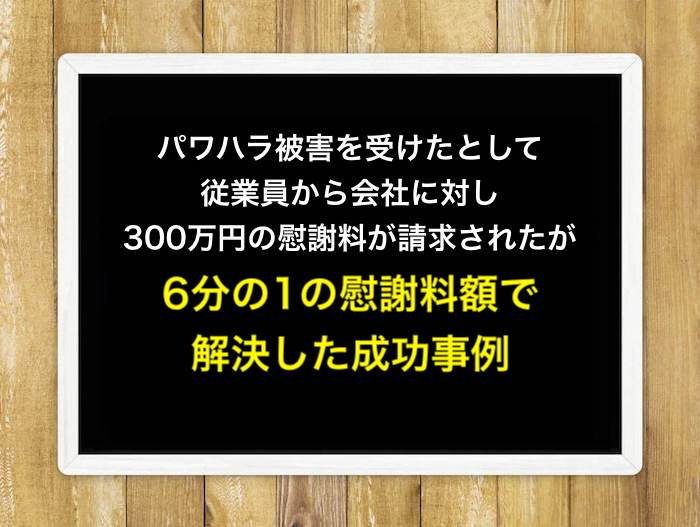

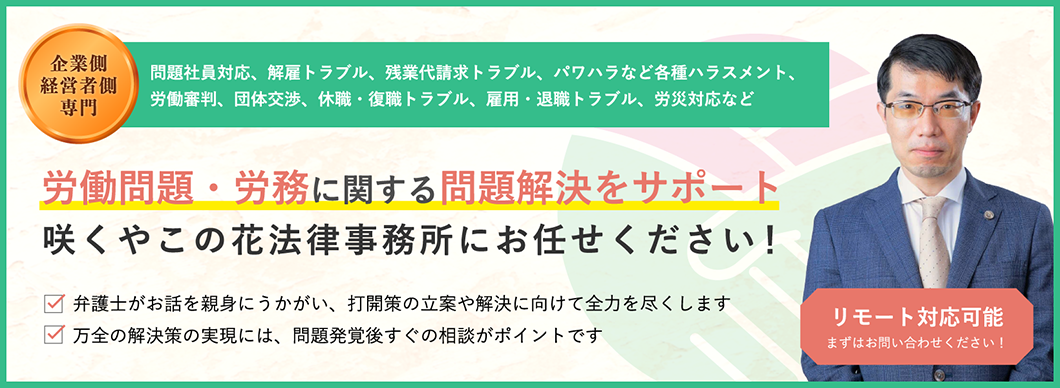
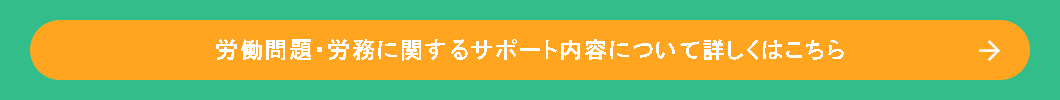
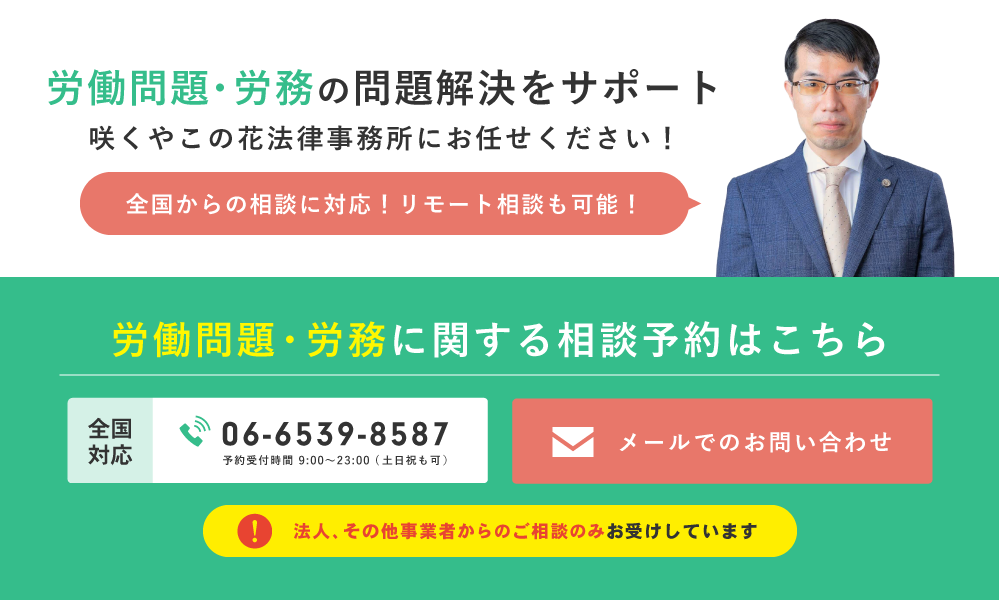
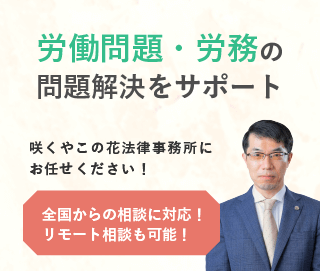





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















