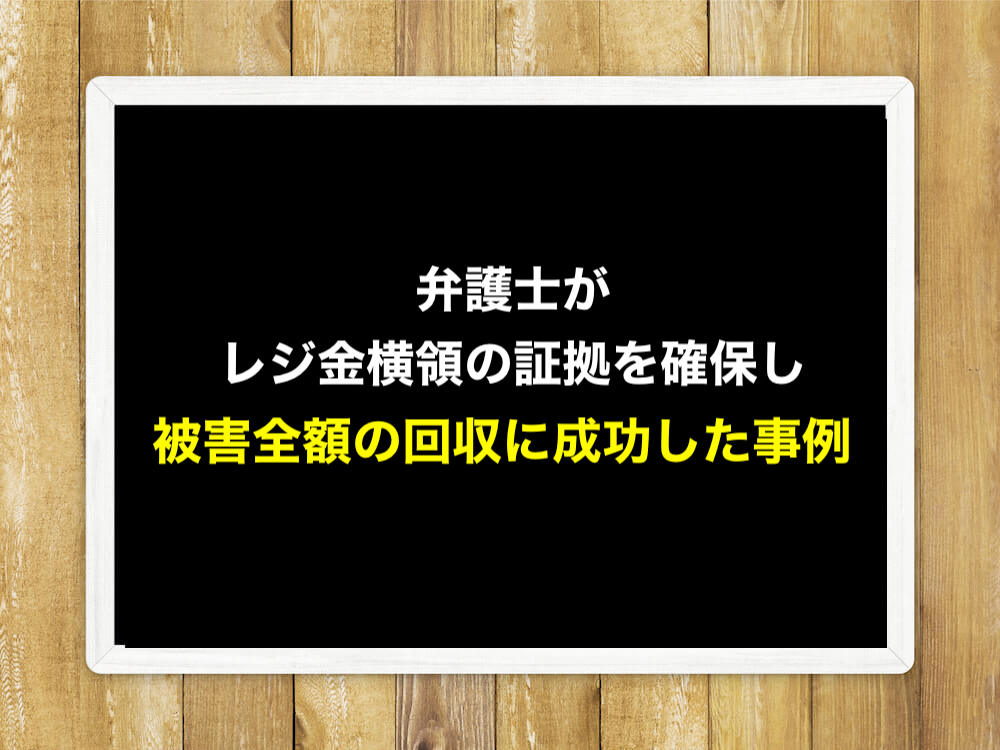
この解決実績を紹介する弁護士

咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。
弁護士のプロフィール紹介はこちら
1,業種
「内科医院」の事例です。
2,事案の概要
本件は、内科医院から横領の疑いがある従業員に対する損害賠償請求についてご相談いただいた事件です。
咲くやこの花法律事務所が依頼を受け、従業員に横領を認めさせ、最終的に横領された約320万円全額の回収に成功しました。
ご相談時、医院は、受付業務を行う従業員Aがレジ内の現金を抜き取っているとの疑いを持っていました。お金を抜き取る瞬間の動画等の決定的な証拠はなかったものの、状況からして、従業員Aが現金を抜き取っている可能性が極めて高いという状況でした。
従業員Aが横領を認めなかった場合には被害額回収の難航が予想されるため、少しでも回収の可能性を高めたいと咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
3,問題の解決結果
本件の問題の解決結果について、以下で詳しく解説いたします。
(1)まず電話相談で詳細な聴き取りを行った
医院が遠方であったため、お電話でのご相談でした。
まず、弁護士は、レジの入出金の流れを把握するため、丁寧なヒアリングを行いました。その上で、医院がどのような経緯で、従業員Aに疑いを持ったのかを確認しました。
ヒアリングの結果、何らかの理由でレジ内の現金が継続的に行方不明となっていることは間違いありませんでしたが、それが従業員Aによる横領であると断定するだけの証拠はありませんでした。
しかし、従業員Aの出勤日にのみレジ内の現金不足が発生しており、レジのシステムを新型に変更した直後に従業員Aが退職を申し出たという経緯からして、従業員Aによる犯行である可能性は極めて高いと思われました。
弁護士が損害賠償請求を行う場合、「内容証明郵便」による通知書の送付という方法を用いることがあります。
しかし、本件のように横領についての証拠が不十分な場合は、内容証明郵便を送るのではなく、横領が疑われる従業員と面談してその場で犯行を自白させたほうが回収の可能性が高くなります。
ただし、面談で従業員Aが横領を否認した場合、裁判での立証に困難を伴うことも予想されます。そのため、いかに横領を自白させるかという点が課題でした。
(2)医院の希望により面談への立会いを行った
医院は、従業員Aとの面談に弁護士が立ち会うことを希望されました。従業員Aは機転が利くため、院長が個別に面談しても、様々な言い訳をしてくることが予想されるとのことでした。
そのため、遠方ではありましたが、弁護士が医院に赴き、従業員Aとの面談に立ち会うことにしました。
(3)面談前の証拠収集が重要
面談で横領を自白させるためには、事前の十分な証拠収集が必要です。
本件でも、弁護士は、事前に医院から、レジの売上集計表やカルテ等の資料を取り寄せて、不自然な点を徹底的に調査しました。その上で、あらためて医院と電話で打合せを行い、面談時に従業員Aに示す資料を整理しました。
従業員Aの言い分をあらかじめ想定したうえで、面談時にその言い分と矛盾する資料を証拠としてAに突きつけて、Aが嘘をついていることを指摘したうえで、自白を迫る必要がありました。
(4)債務承認弁済契約書を事前に準備する
仮に従業員Aがその場で犯行を認めた場合、横領した事実を認める文書に直ちに署名させる必要があります。そのため、複数のパターンの債務承認弁済契約書を準備しました。
債務承認弁済契約書とは、支払義務を認め、かつ、返済方法を記載した契約書です。
具体的には、以下の3パターンを用意しました。
- ●1,債務を承認し、横領した金員を一括で返済する内容の文書
- ●2,債務を承認し、横領した金員を分割で返済する内容の文書(分割の内容は空欄)
- ●3,債務を承認するが、返済方法は追って協議するという内容の文書
「1,債務を承認し、横領した金員を一括で返済する内容の文書」に署名させるのがベストですが、金額が大きいため、署名をためらう可能性があります。しかし、その日のうちに署名させなければ、いったん横領を認めても、あとで自白を撤回するおそれがあります。そのため、「2,債務を承認し、横領した金員を分割で返済する内容の文書(分割の内容は空欄)」、「3,債務を承認するが、返済方法は追って協議するという内容の文書」の文書も用意し、当日の展開に応じて柔軟に対応することにしました。
(5)面談当日に自白をさせることに成功
従業員Aとの面談は、休日の前日の営業終了後に行うことにしました。休日の間に従業員Aが家族と返済方法について相談する機会を与えるために、休日の前日に面談を設定しました。
弁護士は、医院の営業終了時間に余裕をもって、医院の会議室で待機しました。
そのうえで、従業員Aとの面談を開始しました。弁護士から、証拠としてカルテを1つずつ示しながら、カルテが残っているのに治療費を受け取れていない患者がいることを指摘し、思い当たることがないか、従業員Aに説明を求めました。
これに対して、従業員Aは、「受け取り忘れたのかもしれない」などと不合理な言い訳を重ねましたが、弁護士は特に反論することなく、従業員Aの説明を聞いていました。
従業員Aに十分に説明させた後、弁護士から、予め整理しておいた証拠資料の一部を従業員Aに示しました。その証拠資料は、ある特定の1週間にインフルエンザの予防接種を行った患者から一切報酬を受け取っていないことを示すものでした。
従業員Aに対し、「インフルエンザの予防接種は特にお金の受取りを忘れやすいのですか」と尋ねたところ、従業員Aはじっと下を見て黙り込みました。
しばらく様子を見た後、弁護士から、さらに、「過去2年さかのぼって調査した結果を整理したら、これだけの分量になりました」、「インフルエンザの予防接種や自由診療の報酬など単価の高いものばかりでした」と分厚いファイルを証拠として示しました。
その上で、弁護士から「先ほどのあなたの説明に間違いはないですか、もし間違いがあれば、今日この場で訂正してください」と伝えたところ、従業員Aは自らの犯行を自白しました。
弁護士は、従業員Aに対し、直近2年分の横領金を速やかに弁済すれば、医院としてはそれ以上さかのぼって調査するつもりはないと伝えました。
すると、従業員Aは家族にも頼んで、何とか一括で支払うと答え、前記「1,債務を承認し、横領した金員を一括で返済する内容の文書」の債務承認弁済契約書に署名しました。
(6)面談後に一括で回収に成功した
面談後、従業員Aの配偶者から弁護士事務所に、2,3日中に振り込みますと謝罪の電話がありました。その後、被害額全額が一括で振り込まれました。
4,問題の解決における争点
本件では、従業員Aにいかに犯行を自白させるかが課題となりました。
素直に犯行を認めさせるためには、あらゆる言い訳を想定した調査を尽くし、その言い訳に先回りするような証拠資料を準備しておくことが重要です。
また、面談時に不合理な言い訳が出た場合には、すぐに反論し、追及したくなりますが、ぐっとこらえて、あえて不合理な言い訳を重ねさせることが重要です。
不合理な言い訳を重ねさせた上で、それと矛盾する資料を示すと、言い逃れができなくなります。
5,担当弁護士の見解
以下では、担当弁護士の方針について解説していきます。
(1)従業員Aが素直に自白するかは不明であった
従業員Aが自白しなかった場合、訴訟を起こして、従業員Aによる犯行をこちらが立証しなければなりません。
本件では、状況証拠からして立証が不可能とは思いませんでした。それでも、最終的に裁判を起こして判決を得るまでには1年近く要します。そのため、一度の面談で従業員Aに自白させることに注力しました。
横領が疑われる従業員との面談では、訴訟における反対尋問の経験が役立ちます。反対尋問では、不自然な証言が出ても、すぐに不自然であることを指摘してはいけません。
不合理な内容であっても証人に十分に証言させた上で、その証言と矛盾する事実を端的に示すという方法が最も効果的です。
本件でも、従業員Aに十分に言い訳をさせた上で、その言い訳と矛盾する証拠資料を端的に示しました。
(2)その場で債務承認弁済契約書に署名させる
自白を得た場合、直ちに債務承認弁済契約書に署名させることが重要です。
家族の援助が得られるかわからない等の理由で、弁済方法が決まってから合意書を交わすという予定にしてしまうと、後になって自白を撤回してくる可能性があります。そのため、複数パターンの債務承認弁済契約書を準備しておき、自白後の相手の態度を見て柔軟に対応し、その場で署名させる必要があります。
その場で返済方法が決まらない場合であっても、少なくとも債務を承認する内容の文書に署名させることが重要です。
(3)債務承認弁済契約書の内容を事前に検討しておく
債務承認弁済契約書には、相手方にとっても「早く署名したい」と思える条件を加えておき、その内容を説明します。
本件では、以下の条件を入れておきました。
- ●(1)弁済完了を条件に刑事告訴しない
- ●(2)直近2年分の横領金を弁済すれば、その他の弁済は不問とする
さらにさかのぼって調査をすれば追加で数十万円程度の損害が特定できたと思われますが、医院と相談のうえ、調査の労力と早期解決のメリットを考慮し、直近2年分の回収にとどめることにしました。
6,解決結果におけるまとめ
本件では、最終的に従業員Aから約320万円を取り返すことができました。
横領、詐欺等の不正行為があると判断した場合、どのようにして会社の判断を従業員に伝えるかは、慎重に検討する必要があります。
特に面談で問いただした際に否認されると、その後も、従業員の心理として、「やっぱりやりました」と申告することは困難です。また、一度疑惑を伝えると、従業員が証拠隠滅を図ったり、逃亡したりする可能性があります。
そのため、従業員が気付かないうちに社内で十分な調査、分析を尽くし、どのような流れで従業員に切り出すか、十分に検討しておく必要があります。
従業員が否認した後に弁護士に相談しても、その後の選択肢が限られてしまいます。従業員の横領については、疑わしいと思った段階で、ご相談ください。
7,咲くやこの花法律事務所の業務上横領被害に関する弁護士への問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の「業務上横領被害に関する弁護士への相談サービス」の問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,【関連情報】この事例に関連した解決実績
今回の解決事例は、「弁護士がレジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した横領、詐欺等の不正行為に関する解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・弁護士会照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ、支払いを誓約させた事例
・横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例
・横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた解決事例
・EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
 06-6539-8587
06-6539-8587






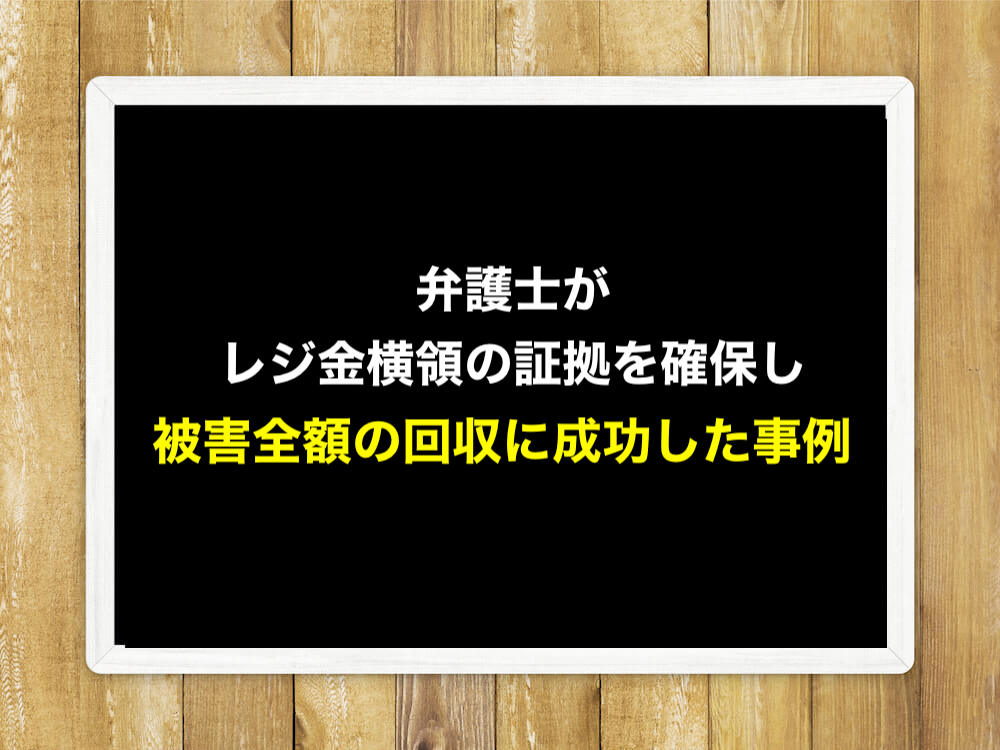

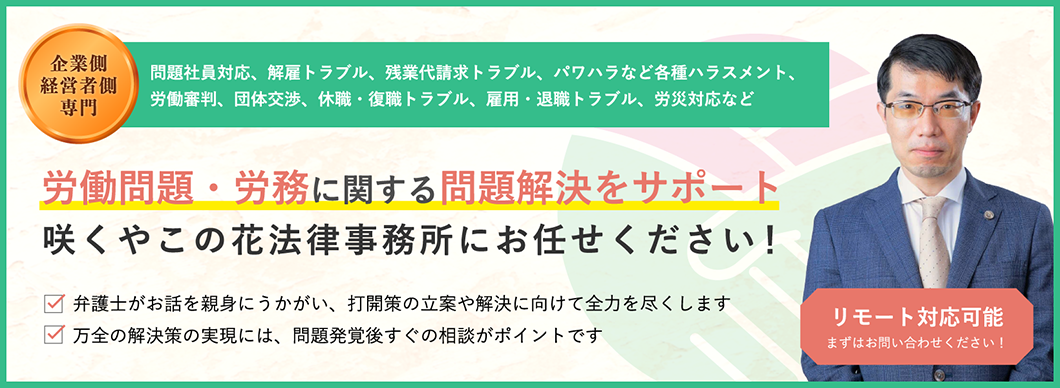
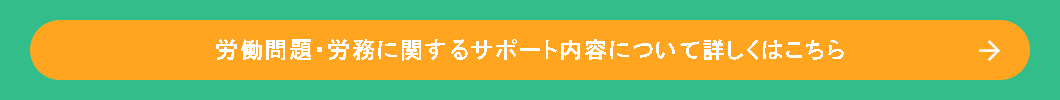
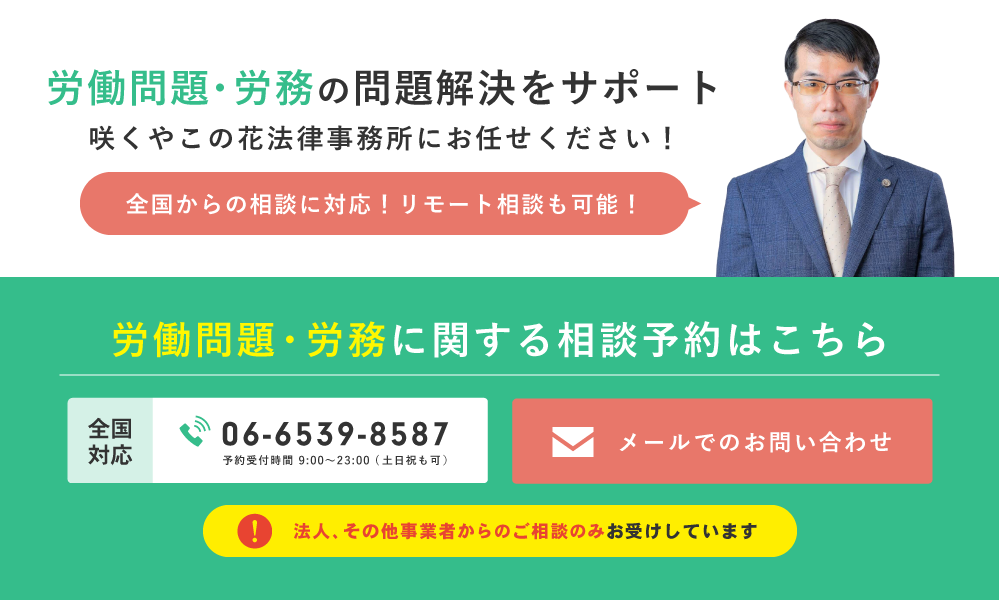
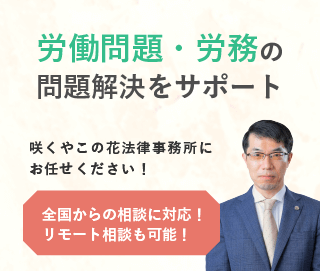





 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る



















